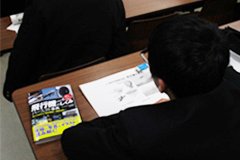航空宇宙
はじめに
本校は、昭和11年4月に名古屋市立機械専修学校として開校し、改称および統合を繰り返し、現在の名古屋市立工業高等学校として平成28年度に創立80周年を迎えました。長い歴史の中で、昭和14年には名古屋市立航空工業学校として開校した経緯があります。
近年では、平成22年度から「航空機産業の次世代を担う工業高校生育成事業」の参加と飛行機同好会の活動を通し、飛行機製作に取り組みました。その結果、平成29年1月には本校で開発された有人動力機が無事初飛行しました。
様々な背景の中、電子機械科では、航空宇宙産業の次世代を担う工業高校生の育成として、3年生総合選択科目において「航空宇宙」科目を設置し、平成30年4月に開講しました。学科を問わず、航空宇宙に興味・関心が高い生徒が受講しています。
科目の目標
航空機やロケットの発展の歴史、飛行原理、構造・装備システムの特徴を学び、部品や組み立ての製造技術や品質保証等についても理解を深める。
授業は極力実例に基づき実施するとともに工場見学も取り入れ、航空機製造技術者としての基礎的教養を身につける。
学習内容(概要)
航空機・ロケット産業界より外部専門講師(2名)をお招きし、基礎的知識から専門的知識まで幅広く学びます。また、各学期には航空機・ロケット組立工場の工場見学を実施し、より理解度を深めます。
第14回
航空機・ロケットの製造映像
- ボーイング777、787の組立の映像
- 加工時におけるひずみによる材料の変化映像
- ロケットの組立映像
- 機械加工による航空機部品の製造映像
今回は、映像による学習です。機密情報が多いため具体的な内容までは紹介できませんが、貴重な映像を見て、実際の様子が手に取るように理解できました。
第13回
板金加工技術
- 航空機に使用される金属
- 板金加工の要素
- 代表的な板金部品と使用部位
- 航空機板金成形法の実際

実際の航空機・ロケット写真から各部位で使用されている金属材料や各部位の板金成形法を学びました。航空機・ロケット製造における成形技術は様々な技術が用いられ、その種類の多さを知ることができました。また、機械工作における金属材料のひずみについて、理解することができました。成形加工では様々な工夫を凝らして製造されていることも分かりました。実機(航空機)成形部品も実際に手にとって見ることができ、より理解が深まりました。
第12回
三菱重工業株式会社 複合材主翼センター見学
名古屋市港区大江町にある複合材主翼センターへ見学に行きました。 2班に分かれ、多くの社員の方に丁寧な説明を受けました。


第11回
川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー見学
名古屋第一工場へ見学に行きました。2017年入社の本校OBも駆けつけてくれ、一緒に記念撮影をしました。

第10回
航空機部品 複合材加工
- 複合材の概要
- 複合材の製造工程概要と主要設備
- 品質管理工程


民間航空機においては、複合材(CFRP、GFRP、GLARE等)がアルミニウム合金にかわり多量に使用されるようになりました。「複合材の概要」では、その構成、複合材製品(スポーツ用と、一般産業用途、航空宇宙用途)を映像で確認しながら学習しました。その他、特徴、製造工程も工程ごとに映像で確認しながら理解を深めました。不適合事例も挙げ、検査法と合わせ品質の欠陥について理解を深めました。
生徒の感想(一部)
- 元の材料にもよるが、個々の材料の良いところを組み合わせて作られるので、良い製品ができる。
- 製造法も様々な方法があり、とても驚いた。これからも知らないことを知ることが楽しみです。
- 繊維の種類によって特徴が変わることに感心しました。自分が思っていた以上に複合材は奥が深くてより興味を持ちました。
- 複合材のサンプルを実際に触てみたり、複合材が使われている航空機の部位や部品を知ることでより一層理解が深まった。
第9回
航空機組立の概要
- 航空機の最終組立
- 航空機組立の特徴
- 航空機の組立方式
- 非剛性部品の組立
- 組立作業の3大要素
- シール作業、塗装作業
- 組立の最新技術動向

航空機組立の特徴として、①部品点数が多い、②軽量化に伴う非剛性部品の組立、③リベット組立が主体など、他にも多くの要素を考えて最終組立をしていることを学びました。中でも、航空機構造組立はリベット組立が主体であるため、位置決め・穴あけ・打鋲の各種類や工程方法について理解を深めました。また、最新技術を駆使していることやシミュレーションによる組立性の検討も行われ、最適工法の確立をしていることを学びました。
興味を持った航空機組立(生徒の感想より)
- 最終組立です。数多くのパーツが合体することにロマンを感じます。工場見学が楽しみです。
- 胴体パネルの結合です。この場面でミスがあると危険なので、この作業をする人はすごいと思います。
- 組立3大要素の打鋲について、リベットといえば一般鋲だけと思っていたが、その他にもハイロックファスナー、ロックボルトがあり、更にブラインドリベットもあり、その目的、使用用途に合わせて選んでいることが分かりよかったです。
- リベットの装着作業をやってみたいと思ったので、リベットについて学習できたことがよかったです。
- シミュレーションによる組立の検討で、製品や加工のシミュレーションだけではなく、作業者の動き方や作業方法のシミュレーションも行っていることに興味を持ちました。
第8回
航空機の装備システム
- コックピット、エンジン
- 油圧、操縦系統、着陸装置
- アンテナ、与圧、空調系統
- 電気系統、灯火

飛行機の中で長時間過ごすため、様々な装備やシステムが備えられています。コックピット、エンジン(ジェットエンジンの種類と構造等)、油圧・操縦系統ではフラッペロン、エルロン、エレベーター、ラダー等の各種舵面の動作、着陸装置(ノーズ・ランディング・ギア、メイン・ランディング・ギア)の衝撃吸収や摩擦熱対策、約20種類ほどある各種アンテナ、与圧(室内の気圧調整)や空調システム、電気系統(メイン発電機やエンジンが停止し且つ補助動力装置が作動しなくなっても着陸に必要な油圧と電力を確保する装置RATなど)、航空機と周囲を照らす灯火系統について学習しました。
興味を持った装備システム(生徒の感想より)
- 着陸時には、相当な荷重と摩擦が発生しているのに、その負荷等に耐えられる構造の着陸装置に興味を持った。
- 灯火システムで、思っていたより様々な意味があり驚きました。また、子どもの頃からよく空を見上げるとチカチカと輝く飛行機が飛んでいたが、その光には様々な効果があることが分かった。
- 電気系統で、熱や着氷などの対策がされていて、もう少し詳しく調べてみたいです。
- アンテナが様々な部分に取り付けられて、用途や目的が違うことが分かりました。
- コックピットで、様々な情報を得たり、指令を与えたりと数多くの計器、スイッチ類が多くあり、それを機長と副操縦士で操作していることがすごいと思った。
第7回
航空宇宙の構造②
- 作用する外荷重
- 構造に働く部材荷重
- 飛行機の静強度
- 飛行機の疲労強度

航空機に作用する外荷重では、運動荷重、突風荷重など多くの荷重が作用します。また、航空機自体の重量(自重)も重要です。強度試験、破壊試験等を経て実際に空に飛び立ちます。安全で快適に運航するためには、様々な荷重について知ることが重要です。
第6回
航空宇宙の構造①
- 旅客機の構造部位
- 主翼
- 胴体
- 構造部位に使用される材料

主翼および胴体の構造について、外観からでは分からない内部構造の学習をしました。また、各部の名称が英語表記さている場合が多いため、航空機関連の仕事に就く場合には、その学習も併せて行うと海外の人たちとの仕事がスムーズに行えます。生徒からはブラックボックスについての質問が出ました。フライトデータレコードとボイスデータレコードがあり、事故が起きたときに回収しやすいように頑丈で色もオレンジ等で分かりやすくなっています。事故の時にクローズアップされますが、定期的にデータを収集し、機体の状態などを普段からチェックしています。
第5回
紙飛行機を作り飛ばしてみよう
前回までの学習で、飛行機に働く力(揚力、重力、推力、抗力)を理解し、飛行機が飛ぶ理論を学びました。また、各舵面の働きから上昇、下降、旋回などの理論も学びました。 今回は、それらの知識を活かし、割り箸を胴体とし、主翼、水平・垂直尾翼をケント紙で作りました。考慮する点として、機体の重心や翼のバランスを考えて組み立てました。さらに各舵面を各々が工夫してオリジナルの紙飛行機を作りました。
作った後は飛行実験です。きれいな飛行姿勢で飛ぶ機体、すぐに墜落してしまう機体、右に曲がってしまう機体など、様々な機体がありました。飛行ごとに、各舵面を操作したり、上反角やコンターを調整したりして、今回の授業目的を達成していきました。


生徒の感想(一部)
- 紙を折って飛行機を作ると思ったが、主翼、胴体、水平・垂直尾翼がついた紙飛行機ですごく本格的でした。
- 主翼の位置の大切さやフラップ、エルロン、ラダー役割や角度の調節など、多くのことが理解できました。
- 主翼を取り付ける位置が重要で、後方につけた方が飛びやすかった。自分が思っていたより安定して飛ばすことができた。
- 頭の中で考えるより、自分でどのように飛ぶかを実際に確かめることで、今まで以上に舵面の効き方が分かった。
- 飛距離にも個人差があったので、他の機体を見るのも良かったです。
- 最初はきれいに飛ばず、すぐに落ちてしまいましたが、コンターや上反角を付けたり、エレベーターを真っ直ぐにすることで飛ぶようになった。今回の実験で飛行機のすごさを改めて感じた。作る人も操作する人もとても高い技術だと思った。
- 主翼の角度や各舵面を調整するだけで飛距離や動きが変わっていくので興味深かった。これからそういった知識をどんどんと身につけて、自分だけの紙飛行機を作りたい。
- 飛ばすたびに主翼の位置や各舵面に工夫を加えることによりしっかりと飛ぶようになった。飛ばなかったときは、何がダメなのかをしっかり考えて調節できた。




第4回
航空機の飛行②
- 上昇/降下、旋回
- 飛行機の構成部位の働き
- 課題

第3回
航空機の飛行①
- 飛行機のかたち
- 飛行機に働く力(揚力、重力、推力、抗力)
- 揚力-飛行機はなぜ浮くのか
- 抗力-前進を妨げる空気抵抗
- 第2回で実施した課題の解説(生徒一人ひとりの解答および疑問に対して)

第2回
航空宇宙発展の歴史②
- 日本で開発・製造した自衛隊機
- ヘリコプター(各部の名称、操縦など)
- 日本で開発・製造したロケット(H-IIBなど)
- ロケットの飛翔(ロケットの原理など)
- 衛星
- 課題(航空宇宙発展の歴史について、2項目の課題を調査・研究)

第1回
航空宇宙発展の歴史①
- 航空関連業務の相関関係(民間航空機を参考に)
- 航空機の運航および整備に従事するために必要な国家資格
- 航空機を開発する上で、技術者と芸術家のデザインの違い(B787を参考に)
- 航空機開発の国際協力体制、分業体制(B787、A380を参考に)
- 空を飛ぶもの(虫、鳥、動物、飛行機、ロケットなど)
- 航空機の歴史(熱気球から飛行船、グライダー、そして飛行機)
- 日本で開発・製造した民間航空機(YS-11、FA-200、MU-2、Honda Jetなど)
- 日本が開発・製造に参加した航空機(B787、Global7000、ERJ195など)