|
学習の評価がかわる 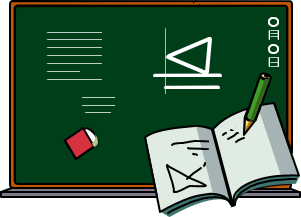 |
|
相対評価から絶対評価に評価方法が変わりました |
|
 相対評価と絶対評価 相対評価と絶対評価 |
|
集団の中でどのぐらいの位置にいるかで表していた「相対評価」から、目標にてらして学習の到達度をみる、いわゆる「絶対評価」になります。
|
|
相対評価 |
|
絶対評価 |
|
クラスや学年の中でどのくらいの順位にあるかを基準にしてつけられています。「相対」というのは「ほかの人と比べて」という意味です。 |
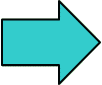 |
一人ひとりが勉強の目標にどれだけ近づいたかをみることになります。ほかの人と比べるのではなく、勉強の内容をどれだけ分かっているかを基準にします。 |
|
 「絶対評価」に改めた理由 「絶対評価」に改めた理由 |
|
例えば、1年生の数学で分数の計算を習うときに、教師が考えていた目標に、クラスの全員が達したとします。相対評価なら、生徒の中でのわずかな差を見つけて五段階の評定をつけないといけません。一人一人ががんばって分数の計算ができるようになっても、他の人がもっとできるようになっていたら通知表で「1」がついてしまうことがあったわけです。これが絶対評価だと、他の人と比べることはありませんから、全員が計算をできるようになれば(目標に達していれば)「3」以上は必ずつきます。逆に、理解できていなければ全員が「1」になることもあります。このように、絶対評価のよいところは、一人一人が勉強の内容を理解しているかどうかをきちんと測ることができる点です。また、最近は生徒数が昔より減って、クラスや学年の人数も少なくなっているので、相対評価をつけるのが難しくなってきています。相対評価はある程度の人数がいないと正確さがなくなってしまうからです。また、新学習指導要領では教育内容を厳選し、基礎・基本の確実な定着を重視していますから、学習指導要領に示されている内容を確実に習得したかどうかの評価を一層徹底することが必要になりました。そのためには、目標に照らし合わせた「絶対評価」の方が優れています。
※文部科学省は「目標に準拠した」と言います。
|
|
 どのように評価するのか どのように評価するのか |
|
(1) 観点別評価について |
|
科の目婦に照らして実現の状況が「十分満足」か‖「おおむね満足」か‖「努力を
要する」か判断して、A、B、Cの三段階に評価します。
|
|
A=「十分満足できると判断されるもの」
B=「おおむね満足できると判断されるもの」
C=「努力を要すると判断されるもの」 |
|
(2) 評定について |
|
観点別評価と同様に、目標に準拠した評価 (絶対評価)で行います。評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、観点別評価の結果から総括的に判断して行います。必修教科では5段階の評定となります。
|
|
5 「十分満足できると判断されるもののうち、特に高い程度のもの」
4 「十分満足できると判断されるもの」
3 「おおむね満足できると判断させるもの」
2 「努力を要すると判断されるもの」
1 「一層努力を要すると判断されるもの」 |
|
(3) 評価方法の工夫 |
|
この評価を行うためには、まず単元ごとに、その内容がどの目標(観点)を達成するのに役立つかを調べ、目標(評価規準表)を作成しています。これが評価の際の規準となります。また、今までの学習後の評価(総括的な評価)だけでなく、授業の中で分析的な評価をする必要があります。 |
|
|
|
ホームへ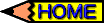 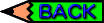 本校の教育課程の特色へ 本校の教育課程の特色へ |