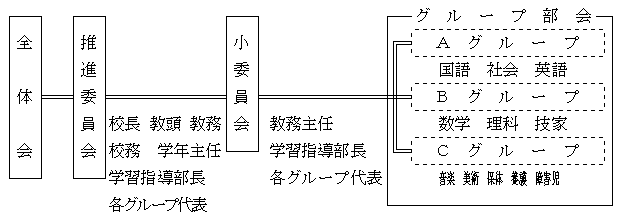
見つめよう自分を! 伸ばそうよさを!
-基礎・基本の定着を図る教育の実践-
1 学校のようす
本校は、名古屋市の北東部に位置し、学級数17(うち障害児1)、生徒数 593名、職員数37名(平成15年12月
1日現在)の中規模校である。学区には、八竜湿地など豊かな自然が残っている。また、近くには、志段味古墳群や大森城跡などの史跡があり、棒の手や鉄砲術などの伝統芸能が受け継がれている古い歴史のあるところでもある。現在は、地域ごとの運動会や学区あげての資源回収など、住みよい環境づくりを目指した活動が盛んであり、保護者や学区の人々は、学校教育に対して関心が高く協力的である。
このような環境の中で育った生徒は素朴であり、友人にも恵まれ明るくのびのびとした学校生活を送っている。しかし、学習意欲はおう盛であるが、基礎・基本が十分に身に付いていないため表現力や思考力など発展的な力が発揮できない場面も見られる。
一昨年度までは体験活動を重視し、生徒の心の育成に努めてきたが、昨年度から基礎・基本の定着を図る中で生徒の能力を引き出すための創意・工夫に取り組んでいる。
2 研究の内容
(1) めざす子ども
基礎・基本を身に付け、それをもとに表現力や思考力など様々な能力を伸ばすことのできる生徒。
(2) 研究の方法
全体の授業を進める教師と個別指導をする教師が協力をして評価を行っているが評価をした後、生徒の基礎・基本の定着を図るためにそれをどう生かすか検討している。
① 全教職員の研究を進めるための指導体制
下図のような組織により、各教科の基礎・基本や評価の方法を検討する。また、個々の教師が年一回以上授業研究を行い、基礎・基本の定着が図れたか検討し合う。
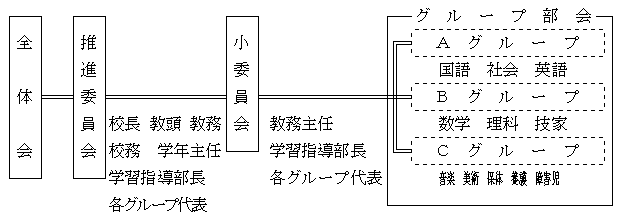
② 学級2分割の少人数指導
1年の数学、英語で年間を通じ、週3時間すべての授業について、各学級を2分割し少人数指導を実施する中で、少人数の編成方法や指導法について研究を進める。
③ TTによる指導
2年の理科で年間を通じ、週1時間TTによる指導を実施し、生徒の興味・関心や習熟度に応じた指導法について研究を進める。
④ 補充・発展的な選択教科
2年では、国語、社会、数学、理科、音楽、保体、技術、英語の8教科14コース、3年では、国語、社会、数学、理科、音楽、保体、家庭科、英語の8教科24コースで実施し、必修教科の内容とかかわらせ、補充・発展的な学習に応じた教材開発に努める。
3 実践事例:1年英語科少人数指導
(1) 少人数指導の分け方とその理由
1年5学級の各学級を等質に2分割にする。等質に分割することについては、小学校の総合的な学習の時間等で英語を学習してはいるが能力差が少なく、生徒の実態を十分に把握しにくいためである。
(2) 生徒の実態
下のグラフは、4月、英語を学習し始めたときのアンケート結果である。多くの生徒は頑張って「英語を勉強したい」と答えたが、16%の生徒が「あまり勉強したくない」と答えている。
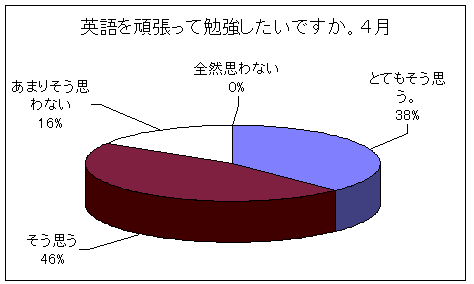
その主な理由は次のとおりである。
・勉強がもともと苦手だから英語も勉強したくない。
・単語や文を覚えることがいやだから。
・すでに塾で英語を習っているから、学校でこれ以上勉強したくない。
英語を頑張って勉強したいと思う生徒の気持ちを持続させ、あまりそう思わない生徒を頑張ろうという気持ちに変化させるためには、基礎・基本の定着を図り、分かる喜びを味わわせることが大切であると考える。
(3) 基礎・基本の定着を図るための手だて
① 教師が授業の中で、できるだけ既習の英語を使う。
教師が授業の中でできるだけ日本語を使わず、既習の英語を使うようにする。このことによって、学習した英語をどう使うとよいのか生徒に提示することになり、生徒の英語を使う機会を増やすことになると考える。
② 既習事項の英問英答を全員と毎時行う
毎時の授業で全員と英問英答することは、生徒が既習事項を理解しているかどうかを把握しやすい。また、正確に答えられない生徒にはヒントを与え、最終的に自分の力で表現できるように粘り強く問答の練習をする。
③ すらすら言えるまで音読を何回も行う
ペア読みやシャドゥーリーディング(CDの後について同時に読む)などの読み方の練習方法を工夫し、英語独自のリズムや音を口にする楽しさを味わわせるようにする。そして、暗唱まで近づけ既習事項の定着を図る。
④ 生徒個々の良さを見付けほめることを大切にし、失敗を気にしない雰囲気づくりに努める
間違いを指摘するだけでなく、答えたことをほめ、やる気をなくさせないようにする。これによって、英語が通じる喜びや英語で対話する楽しさを味わわせ、のびのびとコミュニケーションできる雰囲気をつくることができると考える。
(4) 授業の様子
授業の冒頭で、英語で友達とペアであいさつをした後、互いに自分で考えた質問をしあった。そして、教師が何を友達に聞いたか尋ね、正しく問答できたか確認した。
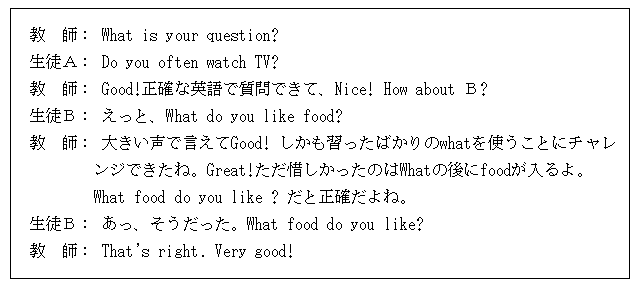
その後、教科書を教師の後について音読した。教科書を閉じて、暗唱に一生懸命に挑戦する生徒が何人かいた。一方、読み方を教科書に必死にメモしている生徒もいた。また、シャドゥーリーディングではCDが聞こえなくなるほど大きな声で音読する生徒もいた。それを教師がほめると、声を出すことをはずかしく思っていた生徒も必死で大きな声で音読しようとした。
(5) 生徒の変容
4月と12月のアンケート結果を比較すると、全体的に英語の勉強を頑張ろうと答えた生徒が増えている。その主な理由は次の通りである。
・ 英語をたくさん話すうちに英語がわかるようになってきておもしろくなった。
・ 発音が難しかったけど、友達と確認するうちにできるようになってうれしい。
・ 毎回同じことを繰り返すので英語を覚えることができ、先生に質問されても困らなくなった。
しかし、頑張ろうと思っていた 135人の生徒の中で、12人の生徒が、がんばろうと思わなくなったと回答した。
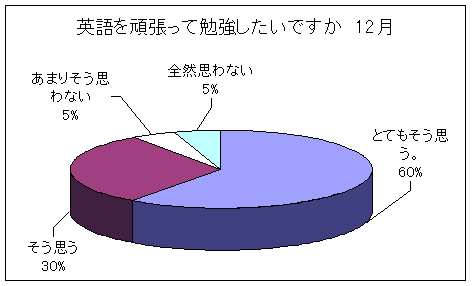
| 【4月と比べ12月の方が意欲が後退した生徒】 ・とてもそう思う→あまりそう思わない2人 ・そう思う→あまりそう思わない 7人 ・そう思う→全然思わない 3人 ・あまりそう思わない→全然思わない 6人 |
また、全然頑張ろうと思わないと答える生徒も出てきた。その主な理由は次の通りである。
・繰り返し読むことがつまらない。
・何回も当たるから、いつも緊張していないといけないし、疲れる。
このように学習を繰り返し行うことは効果もあるが、逆効果になることもある。今後、一人一人の性格などを今まで以上につかみ、学習効果を上げていきたいと考える。
4 個に応じた指導のポイント
本校は、名古屋市の北東部に位置し、学級数17(うち障害児1)、生徒数 593名、職員数37名(平成15年12月
1日現在)の中規模校である。学区には、八竜湿地など豊かな自然が残っている。また、近くには、志段味古墳群や大森城跡などの史跡があり、棒の手や鉄砲術などの伝統芸能が受け継がれている古い歴史のあるところでもある。現在は、地域ごとの運動会や学区あげての資源回収など、住みよい環境づくりを目指した活動が盛んであり、保護者や学区の人々は、学校教育に対して関心が高く協力的である。
このような環境の中で育った生徒は素朴であり、友人にも恵まれ明るくのびのびとした学校生活を送っている。しかし、学習意欲はおう盛であるが、基礎・基本が十分に身に付いていないため表現力や思考力など発展的な力が発揮できない場面も見られる。
一昨年度までは体験活動を重視し、生徒の心の育成に努めてきたが、昨年度から基礎・基本の定着を図る中で生徒の能力を引き出すための創意・工夫に取り組んでいる。
(1) 生徒理解について
基礎・基本の定着を図れたかどうかは、テストや観察等を通して把握することはできる。そして、定着が図れていない生徒を指導するには、繰り返し同じことを学習させるだけでなく、その生徒が何につまずいているのかを把握する必要がある。指導法や教材を見直さなければならない場合もあるが、その生徒の性格などを考え指導しなければならないときもある。日ごろから生徒の活動の様子を観察するとともに生徒の自己評価を活用することも大切であると考える。今後、自己評価の活用について研究していきたい。
(2) 少人数の学級集団の編成について
今年度は、学級を等質の2分割で授業を行った。中学校で本格的に学習する英語においても、学習を進めていくと次第に学力差が出てくる。少人数であることから今までよりは個に応じた指導はしやすいが、より的確な指導をするためには習熟度別の学級編成を考えていく必要がある。そのためには、生徒や保護者の理解を十分得なければならないとともに、評価方法についても検討していかなければならないと考える。