|
|
愛のあふれる学校づくり
平成25年4月1日(月)〜 |
あたたかい春の日差しが、気持ちの良い日となりました。
修了式では、次の2点の話をしました。
1点目は、卒業式で、卒業生に、
ひたむきな時を 重ねて 重ねて
確かな道を 見付けよう
自分大好き 自分大好き
と歌ったことを伝え、皆さんにも「自分大好き」を続けてほしいと話しました。
2点目は、「命を大切にしよう」ということです。
つい先日、西区の中学生が、転落死をしたという悲しい事件がありました。子どもたちには、以前にも朝会等で「命の話」をしてきています。「どんなにつらいことがあっても、命は大切にしましょう。そして、誰かに話をしましょう。支えてくれる人は必ずいます。決して、ひとりぼっちではないことを信じましょう。家族や友だち、学校のみんなを信じましょう。」と話しました。
青少年育成協議会主催、女性会協賛で、卒業生を祝ってくださいました。
卒業生の参加者は約40名でした。開会セレモニーに始まり、「おこしもの」づくりと餅つきを体験し、おいしいぜんざいも、いただきました。
私の実家では、毎年「ひな祭り」が近付くと、母と妹と一緒に、「おこしもの」をつくっていましたので、そのころのことを思い出し、とても懐かしく思いました。私は、アンパンマンと男びな女びなの型でつくりました。
卒業生の子どもたちは、型からはみ出ないようにとても集中したり、自分のイニシャルを色の粉で付けたりして、夢中で取り組んでいました。また、餅つきでは、杵の重さにとまどいながら、リズミカルにつくことを頑張っていました。楽しそうに、かけ声を掛けている場面もありました。
卒業生のために、大勢の方々にご尽力をいただきました。ありがとうございました。
卒業生の子どもたちが、将来、苗代の卒業生のために尽力してくれる日が来たら、うれしいなと思いました。
久しぶりに、家族で映画を観ました。
主人公が、実力を発揮できずにオペラのアリアをうまく歌えなくても、病気で大好きな歌が歌えなくなってしまう時期があっても、仕事を失っても、交通事故にあっても、それでも、苦しみながら、一歩一歩、夢に向かって歩いていく姿に、とてもパワーをもらいました。
そして、人は誰かを支える力をもっていると同時に、誰かに支えられているということをあらためて強く感じました。
春の恵みを届ける雨が降る中、卒業式が挙行されました。
子どもたち、学区・保護者・職員の皆様のお陰で、とても素敵な卒業式となりました。ありがとうございました。
私が何よりもうれしかったのは、「歌い終わるまでは、泣かないでほしい。」と、最初の練習で私が話したことを6年生が、しっかり守ってくれたことです。
ご来賓の方々からは、「歌声のすばらしさに感動した。」「本当によく声がでていた。」「歌っているときの表情が、一生懸命でよかった。」と、たくさんほめていただきました。とても誇らしく、うれしく、子どもたちに感謝したい気持ちでいっぱいになりました。
5年生の頑張りも、素晴らしかったです。昨日の最後の練習以上に、声がしっかりとまとまり、素敵だったからです。
「苗代小むつみ会」の方々が、送り出しで、交通安全の見守りをしてくださいました。雨の中、本当にありがとうございました。
三連休の後は、修了式です。6年生はいません。寂しい気持ちもありますが、在校生の素敵な姿をたくさん見ることができるのが楽しみです。
今日は、卒業式最後の練習でした。5・6年の子どもたちと卒業式の最後の確認をしながら、6年生の子どもたちとふれあう貴重な時間を過ごしました。
これまで、証書授与練習では、子どもの良さを一人一人にその場で伝えてきました。そんな時、子どもは、とても素敵な笑顔をみせてくれました。それが、うれしくて、うれしくて、練習に参加するのが楽しみでたまりませんでした。
もちろん、歌も一緒に歌っていました。せっかくの機会ですから。
午後の準備では、5年生の「ひたむきさ」を強く感じました。頼りになる5年生の姿をたくさん見付けることができました。来年度も楽しみです。
明日も、いつも通り、みんなが自分らしく、練習の成果を発揮してくれることを期待しています。私も自分らしく、みんなの力を合わせて「卒業式」をつくっていきます。
| 平成26年3月18日(火) 「むつみ会」の方々に感謝 |
昨日は、いつも以上にうれしいことがたくさんありました。
朝会で不在だったせいか、応接室の前を通る子どもたちが、下校時にいつも以上に声を掛けて話をしてくれました。楽しかったです。
それから、苗代小学校の子どもたちをずっと支えてくださっている「むつみ会」の方々が、卒業式の登校や下校で、交通安全の見守りをしてくださるというお知らせをいただきました。卒業する子どもたちに、「おめでとう」いう声も掛けてくださるそうです。とてもうれしいことです。きっと卒業生も、笑顔で「ありがとうございます。」と答えてくれることでしょう。有り難いことです。
さあ、明日は、卒業式の最後の練習と準備が予定されています。かぜ気味の人はマスクを着用し、あたたかい服装で明日の練習や準備に参加しましょう。そして、20日の当日まで、体調を万全に整えて式に臨んでほしいと思います。私も、気を付けます。
1〜4年生までの在校生の皆さんも、今日を含めてあと2日になった6年生とのふれあいの時間を大切にしましょう。
| 平成26年3月17日(月) 「学校大好き」の野球部の子どもたち |
今日は午前中の出張があり、朝会での離任式や表彰を教頭先生にお願いしました。 講師の先生方には、離任式不在のお詫びと、今までの御礼をお話ししました。そして、ディスクドッジの表彰は、とてもうれしく思っています。
午後、運動場に大きなトラックがやってきて、たくさんの土を運び込んでくれました。運動場の土が雨で流されたり削れたりして、子どもたちがケガをしやすくなっていたので、土を買って入れたからです。運動場には、ところどころ土の山ができました。それを、野球部の子どもたちや先生方で、平らにならしてくれました。その様子を見ていると、とても楽しそうに、一生懸命に作業をしてくれていました。私は、これも「学校大好き」の姿だと思いました。
これで、運動場の水たまりも、みんなの擦り傷もきっと減ると思います。みんなのために、ありがとうございました。
| 平成26年3月14日(金) ひまわり1組さんの演奏会 |
2限、ひまわり1組さんが、「ルパン三世のテーマ」の演奏会に、5年4組の皆さんと一緒に私も招待をしてくれました。鍵盤ハーモニカを演奏した子どもたちは、5本の指を「ラシドレミ」と速くスラスラと動かしたり、手の形を丸くして同じ強さで正確に鍵盤をひいたりしてくれました。とても上手でした。そして、リコーダーを演奏した子どもは、主旋律をきれいに吹き、シャープやフラットの付いた運指の難しい音も完璧に吹きこなしていました。3人とも、とても素晴らしい演奏でした。5年4組の子どもたちからは、演奏の良さをほめる感想がたくさん発表されました。素敵な演奏を聴かせてもらえて、とてもうれしく思いました。
午前中、守山東中学校ブロックの青少年育成推進会議が開催されました。
平成24年度と25年度の2年間をかけて、守山東中学校が本会の事業として実施された「キャリア教育」についての事業報告をお聞きしました。生徒が、「自分が働くための価値観を十分に活かして、未来へチャレンジする自分」を見付ける授業を中心にご報告いただきました。ご報告をうかがいながら、今年から苗代小学校が目指している、「自分大好き」につながっているなということを感じました。
その後、学校評価について、三小中学校からそれぞれ報告をしました。
苗代小学校は、創立40周年記念の要覧やアンケート結果の資料をもとに、「自分大好き、友だち大好き、学校大好き」を目指し、特に授業を通しては、コミュニケーション能力の育成を目指していること。また、学区や地域の方々のご協力を得ながら、命の大切さを学ぶ稲やパンジーの栽培等を頑張っていること、薬物乱用防止教室や防犯教室等を継続して実施していることなど、子どもたちの健全育成への取り組みについてお伝えしました。また、学校のことを知っていただくために、ホームページで情報発信を継続していることや、年間4回実施したアンケート結果について報告をしました。今後も、学区や地域との連携をお願いしたいという思いも話させていただきました。
年2回ではありますが、警察や、区役所の方々も参加されるので、守山区内の情報をお聞きできる良い機会となっています。
1限、体育館で「6年生を送る会」を行いました。在校生は、「6年生へ、これまでありがとう。」の気持ちを込めて、発表をしようというめあてをもって頑張ってくれました。
○ 1年生 ー 鳴子を鳴らし、楽しそうに踊ってくれました。ポーズを入れ、楽しいせりふも交えた明るい発表でした。1年生の成長を感じました。
○ 2年生 ー ポンポンを使って、かっこよくダンスをしてくれました。歌を口ずさむ子どもたちの表情も、自信満々で、とにかく素敵でした。
○ 3年生 ー いろいろな楽器が、主旋律を演奏する部分があり、きれいで正確に演奏できていました。気持ちが一つにそろっている演奏でした。
○ 4年生 ー 堂々とした指揮者とリズムのはっきりした、素敵なピアノの伴奏にのって、みんなの演奏や歌が、始まりました。原曲に、自分たちで歌詞をつけたそうです。
6年生への思いが、歌声で丁寧に表現できているのが素敵でした。
○ 5年生 ー 「6年生からのバトンをしっかり受け継ぎます。」という強い思いを子どもたちの一生懸命な歌声から感じました。私は、頼もしい5年生だなと思った途端、うれし涙が、こぼれました。
在校生の発表が終わり、お返しに6年生が、「ビリーブ」を合唱してくれました。
いつもながら、声量のある歌声と、綺麗なハーモニーは素敵です。
私との卒業式の最初の歌の練習で、「歌い終わるまでは、泣かないでね。」と話した私の言葉を気にしながら、涙をこぼしながらでも笑顔で歌ってくれた子どもたちの表情が忘れられません。なんて、素敵な子どもたちでしょう。
会の運営をしてくれた子どもたち、素敵な演奏や発表をしてくれた子どもたち、それを支えてくださった職員の皆さん、みんなみんな、本当にありがとう。
苗代小学校での貴重な思い出の1ページが、増えました。
先週8日(土)に、私は、東日本大震災直後から医療の分野で関わって見えた方々の講演を聴く機会がありました。
その話から、現場の情報をいかに収集し、どのように体制づくりをし、指示を確実に届けるようにすべきかという点で、大変参考になりました。その中で特に心に残った言葉は、「極限状態だからこそ、相手の立場に立ち、譲り合うことが大切である。」「情報は、刻々と変化して当たり前と考え、その場に応じて最善を尽くす。」「被災者の心の痛みは癒えることはあっても、決して消えない。でも、前に進もうとしている方々は大勢いらっしゃる。だから、いつまでも東日本大震災を忘れないでいることが、その方々を支えることになる。」です。
「東日本大震災」を忘れない、風化させないという気持ちを大切にするということで、苗代小学校では、3月11日に避難訓練をしています。
子どもたちの避難の様子です。避難の放送があってから、4分32秒で出席者全員の避難を確認しました。
子どもたちには、次のことを今日も指導しました。
・放送などの指示をしっかり聴く。
・「おかしも」の合い言葉を守って、避難する。
・地震は、まず頭を守る。火事は、煙を吸わないように口を押さえる、。津波は高い場 所に避難する.
災害は、ひとごとでも、よそごとでもありません。自分の問題として考えるべきです。
まず自分にできることから、準備を心がけましょう。
昨日、開催された「名古屋ウイメンズマラソン2014」をもとに、次のような話をしました。
自己の記録に挑戦するランナーたちの素晴らしさ。完走する等、自分の目標に向かって自分自身とたたかいながら走るランナーたちの素晴らしさ。道路や信号付近で交通整理をし、見学者が道路付近に入らないように見守る方々、テレビ放送をする方々等、ランナーを支える大勢の方々の素晴らしさをまのあたりにしたからです。
今、6年生は卒業を控え、1〜5年生も学年のまとめということから、マラソンでいえばゴール間近にいます。6年生が安心して卒業できるよう、1〜5年生は「しっかり頑張ります。任せてください。」という態度で、過ごそう。
まず、みんなが一生懸命練習に取り組んでいる「6年生を送る会」を成功させること、そして、今やるべきことをきちんとやっていきましょうと伝えました。
12日(水)の「6年生を送る会」が楽しみです。
| 平成26年3月7日(金) 桜の飾り付け と PTAの会議 |
昨日の一斉下校・現地指導の後、職員で、体育館の壁に桜の飾り付けをしました。
東西の壁面が、桜の花びらが風に舞って飛んでいくような雰囲気になりました。私はまるで、夢や希望に向かって、春風に乗った子どもたちが元気に羽ばたいていくような気分を感じました。学年末の成績処理のまっただ中、職員の皆さんが子どもたちのために和気あいあいと作業をしてくださったことに、とても幸せを感じました。
子どもたちは、きっと喜んでくれるでしょう。
午前中、第5回 PTA運営委員会、第2回 全体委員会が開催されました。
私は、皆様のご協力に感謝するとともに、今年度PTA活動を進められる中で、皆様が深められた会員同士のつながりを今後も子どもたちのために生かしていただきたいと話しました。
4月28日(月)10:50〜のPTA総会まで、まだまだご多用な時期は続きますが、どうぞよろしくお願いします。
午前中、守山東中学校の卒業式に参加させていただきました。
「卒業生と在校生がつながっているな。」という思いを強くもった素敵な卒業式でした。 感動の涙がたくさんこぼれた生徒さんが多く、最後の歌声は心配でしたが、ベースの声が、ソプラノの声をしっかり支えている、きれいな優しい歌声でした。
5限に、分団会議、一斉下校、現地指導がありました。
一斉下校のあいさつの中で、4月からは、新1年生が分団に加わります。6年生は、中学校に進学します。今日の卒業生と在校生のように、苗代小の子どもたちもずっとつながりをもっていてほしい、出会ったらあいさつがきちんとできる子どもたちでいてほしいと話しました。
校外指導部員の皆様、風の強い中、ご協力いただきましてありがとうございました。
今朝は雨降り。歩道橋の北側に職員が2名。南側には学区の方が見守りに立ってくださいました。私も子どもたちに声を掛けながら子どもたちの様子を見守っていました。 実に、子どもたちは淡々と順番を待ち、整然と登校してくれています。素敵な子どもたちばかりです。そして、学区の方や職員たちにも大感謝です。
学校に着き、土間を見に行きました。長靴をはいてくる子どもも多いので、靴箱の上は長靴が並び、自分の靴箱に横向きにして工夫して入れている子どももいます。
また、傘立てには傘が入れてあります。西土間で、傘を閉じないで入れている子どもの傘が数本ありました。傘立てのスペースはとても狭いので、傘は開いたままだと、その上から別の子どもの傘が入ることがあり、傘の骨が曲がったり、自分の傘をすぐに取り出せないことがあります。狭いスペースを有効に使う工夫を学ばせる必要があると感じました。家庭では、きっと傘が乾きやすいように開いたまま置いておくことも多いと思いますが、学校のスペースではそれができません。自分の傘も友だちの傘も大切にするために、そして、スペースを有効活用できるようにすることにも気付かせたいと思う雨の朝でした。
勝手に傘をさわって悪いとは思いましたが、傘がかわいそうだったので、今朝は、開いたままになっていた傘を閉じて、入れ直しておきました。「あれ?なぜ?そうか!」と思ってくれる子どもがいたらうれしいです。
昨日、5年4組の「ひとつだけの花」の器楽合奏を聴かせてもらいました。交替で、5年2組と5年1組が演奏を聴きに来ました。演奏を聴いた後、みんなからすぐに大きな拍手がおきました。
じっくりと練習を積み重ねた演奏に仕上がっていました。それぞれのパートでよく目立って演奏する部分が、特に素敵だったからです。
以前、同じ5年4組の「ルパン三世のテーマ」の器楽合奏も聴かせてもらいました。その時の演奏も素敵でしたが、緊張感と真剣さを強く感じました。今回は、演奏から自信たっぷりで演奏する余裕や、器楽合奏をすることが楽しいという気持ちが大勢の子どもたちから感じることができました。
とてもうれしい時間でした。
今日から卒業式の全体練習が始まりました。
一つ一つの動作や呼びかけの言葉、歌。その一つ一つを表現する楽しさを味わいながら、よりよい卒業式にしていきたいと思います。子どもたちとみんなで、努力します。
応援をどうぞよろしくお願い申しあげます。
今日は、残念な話とうれしかった話をしました。
残念な話の内容は、今みんなが使っている机や椅子は次の学年の子どもが使う品である。自分が使い始めた時よりもきれいにして、次の学年の子どもに渡してほしい。それも学年のまとめとして大切なことだと考える。という内容です。
うれしかった話は、学区の方が、6年生の子どもたちや職員から親切にされたことをとても喜び、私に話しに来てくださったという内容です。(2月27日の内容参照)
一週間の始めになぜこんな残念な話をしたかというと、みんなで何度も指導しており善悪は理解をしているものの自分の気持ちをコントロールできずに正しく行動できていない、まだまだ不十分な状況があるからです。このまま、この学年を終わらせたくないというのが正直な気持ちです。
子どもだけでなく、大人もそうですが、正しく行動するということは周りの支えがあれば容易にできる場合があります。逆に、正しくない行動を何度も繰り返せば、自暴自棄になり、それが正しくないと思わなくなったりすることもあります。大人であれば、犯罪につながり、罰せられることもあります。そんな取り返しのつかないことにならないよう、子どもたちは、家庭で躾け、学校で学んでいるはずです。学校生活の中では、これからもそんな子どもの話をじっくり聴き、保護者や職員だけでなく、もっと友だち同士でも支え合ってほしいと私は願っています。
今年度、自分の子どもではないけれどとても気になる、言えば逆に自分の子どもが仕返しされるかもしれないから自分の名前を出さないでほしい、先生の見ていないところで正しく行動できない等と保護者や学区の方から話をうかがうことがありました。その方のお気持ちはよく理解できますし、貴重な情報をいただけることは、指導に生かしていくとができたので大変有り難かったです。しかし、来年度は、このようなつながりを大切にしつつ、継続して一緒に取り組んでもらえる人間関係に高めていけたら思っています。
どうしたら、本人が自分から正しく行動できるのか、周りのみんながその気持ちを大切にして支えてあげられるのかが大切だと思っています。そして、根本的には、自分がより良く成長していこうと努力し続けるしかないとも考えています。
人は、支え合って成長していくものだと思っています。
天候のせいで、昨日、今日と朝の運動タイムは、「スクールダンササイズ」を行いました。職員室に居ても、教室からステップを踏んだりジャンプをしたりする音が、聞こえてきます。
今日は、職員室でもゼロ学年の職員たちが、一緒に取り組んでいました。
とてもハードな動きで、かっこよく動くには、かなり難しくて練習が必要です。
子どもたちとの会話のネタになり、もちろん教材研究にもなっていますが、朝運動をすることは、とても気持ちがいいです。
子どもたちのケガが、いつもよりも減ったらうれしいなと思いました。
| 平成26年2月27日(木) 優しい6年生 卒業に向かって |
昨日、学区の方が来客されました。一昨日、東門付近で転ばれたそうです。その時、6年生の子どもたちが、その方のケガを心配して声を掛けたり、先生を呼びにいったりしてくれた親切な行為に大変感謝され、御礼を伝えに来てくださいました。
その方は、いつもそっと子どもたちの登下校を見守ることで、子どもたちから元気をもらっていると話されました。そして、見知らぬ私に、ちゃんとあいさつをしてくれるので、とてもうれしいとも話してくださいました。
苗代小の子どもたちや、対応してくださった先生がほめられることは、校長としてとても幸せなことです。 恥ずかしいですが、その方が話してくださるまで、この出来事について全く知りませんでした。
転んだケガの痛みが残る中、わざわざ来校していただき、こちらが申し訳なく有り難く思いました。
4限、体育館で6年1組と3組が、合同体育を行いました。楽しそうにプレーする子どもたちを見て、心が和みました。そして、授業の最後に、担任が、「来週からは、体育館で卒業式の練習がはじまります。ここで体育をやるのは最後かもしれない。体育館にも感謝の気持ちを込めてあいさつしよう。」とおっしゃいました。6年生にとっては。一つ一つの出来事が、卒業式へのステップとなります。
子どもたちが、「卒業」を意識してますます自分を高めていってほしいと思いました。
今日も放課になると、子どもたちが応接室前に来て、遊びをしながら、私に話かけてくれました。その中に、6年生も含まれています。たわいもない会話をするだけなのですが、とても「幸せなとき」を過ごしています。6年生には、明るく、元気に卒業のときを迎えてほしいと願っています。
卒業式に向けて、具体的な内容や練習日程も決まってきています。学級では、少しずつ練習も始まっているようです。
今年度は、卒業証書授与の様子を少しでも見やすいようにしたいと考え、フロアーの中央に壇を設置し、その壇上で卒業証書授与を行います。これから練習を進める中で、お子様からもお話を聴いていただけることと思います。ご理解のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。
本日、学校だより3月号を配布しました。
その中で、2月7日(金)締め切りで回収させていただきました「保護者アンケート」結果を掲載させていただきました。
また、約70名の方から、子どもたちの成長を記したうれしいお言葉や、ご家庭での子どもたちの様子、登校時の姿や、いろいろな視点からのご意見等をいただきました。その中には、継続して指導すべき点もありましたので、担任や担当者にも伝え、気を付けて見守り、今後も指導していきます。
貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
今年度は、年に4回アンケートをさせていただきましたが、今回のアンケート回収率が最も高かったです。ご協力ありがとうございました。
| 運動会のアンケート |
665名 |
回収率 79.2% |
| 授業参観のアンケート |
433名 |
回収率 51.5% |
| 学芸会のアンケート |
651名 |
回収率 77.5% |
| 保護者アンケート |
731名 |
回収率 87.0% |
今日は、うれしいことに、表彰から朝会がスタートしました。
その後、今朝、登校途中で転んでしまった子どもと、その時、とても親切にできた高学年の子どもに出会い、心がぽかぽかしたことついて話しました。また、先週の授業参観で、とても立派に発表している子どもたちがたくさんいて感心したことと、保護者の方々から、声が小さい子どもがいてせっかくの発表が聞きとりにくかったと、お聞きしたことを伝えました。そこで、 あと一ヶ月の間に、いつもはきはきと大きな声で、話せるようにしましょうと話しました。
| 平成26年2月21日(金) 授業参観・学級懇談会 その2 |
昨日に引き続き、今日は低学年の授業参観・学級懇談会がありました。
今日も、大勢の保護者の方々が、お越しくださいました。大変、風の冷たい中、本当にありがとうございました。
昨日も感じましたが、今日も子どもたちが自信たっぷりで発表する姿をたくさん見ることができました。応援、ありがとうございました。
| 平成26年2月20日(木) 授業参観・学級懇談会・学校評議員会 |
今日20日(木)は高学年、21日(金)は低学年の授業参観・学級懇談会があります。 また、今日は、学校評議員様をお招きし、学校評議員会も実施します。
9月と同様、授業の様子を参観していただき、子どもたちのよさを見ていただいたり、感想をお聞きしたりします。また、今年度実施した保護者アンケートや職員の学校評価についてお話しして、ご意見をうかがい、今年度の取り組みを振り返って、次年度の学校運営の参考にさせていただきます。
今後も、学校の具体的な取り組みを知っていただき、学校と連携して、子どもたちの成長を支えて頂けたらと思っています。
保護者の皆様には、ご多用の中、2月7日(金)締め切りの保護者アンケートに、ご協力いただきましてありがとうございました。このアンケートの集約結果につきましては、以前もお知らせしましたが、「学校だより3月号」でお知らせします。各アンケートについては、読ませていただき、緊急に指導すべき点については、担任や学年を中心に話を聞き、取り組みをはじめたり、継続指導をしたりしているところです。
| 平成26年2月19日(水) お世話になった方々に感謝する会 |
苗代小学校の子どもたちや学区のためにご尽力をいただいている方を代表して、苗代学区連絡協議会会長様、毎日の交通指導をしてくださっている交通指導員様、子どもたちに読み聞かせをしてくださっている宙の会の代表者様の3名をお招きしました。
3名の方々にご挨拶を頂きました。
学区連絡協議会会長様は、これからも「元気で明るく楽しい学区」をつくっていきたいと思ってみえることや、学区とのつながりで、3年生は、小幡駅に植えたパンジーづくりを頑張ったこと、4年生は学区の方々と矢田川の河川敷の清掃を頑張ったこと、6年生は提灯パトロールのペットボトルづくりを頑張ったことをほめてくださいました。
交通指導員様は、何よりも、みんなが交通事故にあわないようにと強く願っていることや、子どもたちに元気にあいさつをしてもらえると元気がでてくる等という内容を手品をまじえて語ってくださいました。
宙の会の代表者様は、「宙の会」の言葉の由来は、子どもの想像力は宇宙のように無限である、子どもたちへの読み聞かせを通して子どもたちの想像力を豊かにしていきたいと考え活動をしている等と話してくださいました。
この会の中で、子どもたちはお客様に対して優しい笑顔を浮かべ、あたたかい拍手をするとともに、話を集中して聴くことができていました。
苗代小学校の子どもたちが大人に成長した時、この方々のように、学区の子どもたちと進んで関わり、学区の子どもたちの成長を支えるつながりをもっている方々になっていたらうれしいなと思いました。
本日は、会に出席して頂き、ありがとうございました。そして、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
今日の放課、運動場を見ていたときのことです。先生たちが、子どもたちにまじって一緒に遊んでいました。子どもたちは、もちろん大喜びの様子です。先生たちが、はりきりすぎてケガをしないといいなとは思いましたが、とてもほのぼのとして、心があたたかくなりました。
風は、まだまだ冷たいですし、雪の予報も出ていますが、なんだか今日の日差しは、とてもあたたかく感じられました。
みんなの笑顔は、やはり素敵です。
| 平成26年2月17日(月) 朝会の話 校章をデザインした方との出会い |
朝会で、ソチオリンピックメダリストの話を通じて、「自分大好き」の姿について話しました。そのメダリストとは、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦選手とノルディックスキー・ジャンプの葛西紀明選手です。2人のインタビューの様子を見て、これが、「自分大好き」の姿で、素敵だなと思ったことを伝えました。
羽生選手については、フリーの演技がベストの演技ではなかったことを振り返っていた点です。彼は、東日本大震災を乗り越え、スケートをあきらめずに頑張ってきたそうです。そして、自分が頑張ることで、震災にあった人々に元気を与えることができると思ってやってきたそうです。
また、葛西選手については、45歳になっても49歳になってもチャレンジしたい、と語っていました。また、7回もオリンピックに出場していますが、これまでに自分のフォームを見直し、つらい出来事があっても努力し続けてきたそうです。
2人に共通するのは、逆境にあってもあきらめず、こつこつと努力し続けてきているということです。メダリストになるには、もちろん他の人よりも優れた成績をあげなければなりませんが、そのために、まずは、「自分が自分に勝つ」と言うことができなくてはならないと、私は思っています。
子どもたちにも、職員にも、「自分大好き」とは、「自分の長所や短所も自分らしさと認めること。そして、自分のやるべきことや自分の良さを生かして、こつこつと継続してやり続ける自分でいられるように努力し、そんな自分を大好きに思うこと」だと考えています。
そのために、互いにみんなで声を掛け合って励ましたり、良さを認めてほめたりすることが大切です。
卒業式・修了式まで、あと約1ヶ月。
子どもたちへの応援を引き続き、どうぞよろしくお願い申しあげます。
今日、偶然にも苗代小学校の校章をデザインしてくださった方とお会いする機会を得ました。校章の入ったペーパーウェイトをお孫さんから見せてもらい、とてもうれしかったとお電話をいただいたからです。私も、校章をデザインされた方に直接お会いすることができて、とても光栄でした。
| 平成26年2月14日(金) 雪の日の登下校の見守り |
私が朝起きた時、まだ雪はなかったのですが、自宅を出るときはたくさんの雪が降っていました。
いつものように、小幡駅から子どもたちと一緒に歩いたり、歩道橋で声をかけたりしながら、見守りました。歩道橋では、いつも見守りをしてくださっている学区の方が、今日も立ってくださっていました。もちろん、職員は、早くから雪かきをしたり、横断歩道で見守りをしてくれたりしていました。寒く、冷たい中、本当に有り難いと思いました。
下校の時は、雪からみぞれのような雨にかわっていました。
それでも、子どもたちは、名残惜しそうに、雪を大切に持ったりさわったりしながら、帰って行きました。朝よりも、学校付近での車の通行が多いので、「後ろから車が来てます。」とか「道路を広がらないで歩きましょう。」と、大きな声で声掛けすることが何度もありました。
冷たい風や、日差しのあたたかさを交互に感じる日々の繰り返しで、春はやってきます。
子どもたちも皆様も、くれぐれも体調をくずされませんよう、願っております。
| 平成26年2月13日(木) ひまわり組 卒業生を祝う会 |
守山区教育振興会と守山区手をつなぐ育成会主催の「卒業生を祝う会」に、守山区役所講堂へ、ひまわり学級の子どもたちとでかけました。
会場には、区内の特別支援学校や特別支援学級の子どもたち、保護者の方々が集まってみえました。来賓には、名古屋ライオンズクラブの方々、区長様をはじめ区役所の方々もお越しくださいました。
卒業生は、一人ずつスピーチをしました。苗代の子どもたちは、とても落ち着いて話すことができていました。とてもりっぱな姿に、感心しました。これからも、自分らしく成長していってほしいと思っています。
子どもたちみんなと卒業生を祝うことができて、よかったです。
2・3限、矢田川河川敷に、1年生が、「たこあげ」にでかけました。
太陽は顔を出していましたが、風は冷たく今日も寒い日でした。
1年生の様子を見に行けなかったので、下校時、1年生の子どもたちに、「今日のたこあげは、うまくできましたか?空にあがりましたか?」と、声を掛けてみました。
すると、子どもたちは、にっこり笑って、「あがったよ。」と元気よく答えてくれました。また、「4年1組の教室の高さぐらいまであがったよ。」と、分かりやすく話してくれる子どももいました。
質問に、うまく答えられる姿を見て、1年生の成長を強く感じ、うれしく思いました。
今日の朝会で、「創立40周年記念学校要覧、ファイル、記念品」を今日必ず持ち帰りましょうと伝えました。。そして、先日の3年生が「昔の話を聞く会」で講師の方々にも話の聴き方がとてもよかったことや、たくさんの質問ができたことについてほめていただきましたが、これからも、「自分大好き、友だち大好き、学校大好き」をめざして努力を続けましょうと話しました。
学校要覧の中で、1点訂正がございます。
学校医 浅川 順一先生の氏名に間違いがございました。校医様には、直接お詫びに参りましたが、大変失礼をいたしました。この場を借りて、お詫びを申しあげるとともに、皆様にも訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。
住宅都市局や建設会社等の業者さんと一緒に、トワイライトルームのある棟の1年点検に立ち会いました。この棟は、トワイライトルームだけでなく、器具庫や更衣室等の学校が使用している場所も、含まれているからです。
いろいろな箇所を点検して見えましたが、私も、トワイライトルーム南側の窓の格子を動かしてみました。
トワイライトルームを点検しながら、「1年たっているのに、とてもきれいに使っていますね。」とほめてくださる方がみえました。子どもたちも、頑張っていると思います。ですが、トワイライトの先生方やAPさんをはじめ、いろいろな方々がきれいに清掃をしてくださっているおかげだと思います。いつもありがとうございます。
そういえば、今までに勤務した学校のトワイライトでは、トワイライトの方々と一緒に、子どもたちが、自分たちの使用するトイレや土間を清掃する時間が、活動の中にあったのを思い出しました。
苗代の子どもたちが、これからも、「来たときよりも美しく」を心がけてくれるといいなと思いました。
異学年で、52のグループに分かれた縦割りグループの子どもたちが、1月23日(木)〜2月7日(金)までの期間に分かれて、大放課(10:25〜10:50)、ディスク・キャッチャーのゲームをし、交流をしています。
ルールは、1〜4年の子どもたちが投げるディスクを同じグループの5・6年の子どもたちがキャッチします。そして、うまくキャッチできた得点を競うというものです。
明日で、全部のグループが終了します。児童会の役員の子どもたちも、司会等の仕事をしてくれています。
わずかな時間ではありますが、異学年の子どもたちがふれあいながら、運動を楽しむ機会にもなっています。
体育館では、大きな歓声が毎回響いています。
来週の10日(月)、子どもたちに配布する「創立40周年記念学校要覧、ファイル、記念品」が、今日、業者から届きました。4月から、教頭先生を中心に、いろいろと検討に検討を重ねて、よりよいものをめざしました。
ぜひ、お楽しみにしていただけたらと存じます。
| 平成26年2月4日(火) 入学説明会 3年 「昔の話を聞く会」 |
今日、10時から入学説明会を実施しました。
PTA役員や校外指導部の方々にもご協力をいただき、大変感謝をいたしております。
新1年生の人数は、137名(今日現在)で、5学級の予定です。
私のあいさつの中で、本校は、「愛のあふれる学校づくり」をめざしていること、そのために子どもたちには、「自分大好き、友だち大好き、学校大好き」になりましょうと伝えていること、授業を通して「コミュニケーション能力の育成」に重点をおいていることをお伝えしました。
新1年生の保護者の皆様が、話を聴いてくださる態度が、大変落ち着いていらっしゃったこと、時間にゆとりを持って会に参加してくださったことをとてもうれしく思いました。立春とは言え、寒い中、ありがとうございました。
そして、新1年生の保護者の皆様にお願いしたいことは、入学式に向けて、まずは健康第一に心がけていただくこと。さらに、身の回りのことで「自分一人でできること」を少しずつゆっくりと増やしていけるように、ご支援をお願いしたいということです。そのためには、お子様とご家族で一緒に取り組んだり、見守りながら小さな成長をほめたりしていただき、継続して頑張ることの大切さや、できた喜びを実感できるようにしてあげることが大切だと考えております。
入学式を職員一同、楽しみにいたしております。
3・4時間目、3年生は、学区女性会の3名の方々から、「昔の話」をお聞きしました。
今、3年生の教室の廊下にも昔の道具が展示してありますが、いろいろな道具や、その時々の行事でつくった食べ物、古銭や当時の写真や通知表等の品々をたくさん持ってきてくださいました。
3名の講師の方々のお話をお聴きしながら、平和の大切さや、物質的に不自由しない幸せに感謝するとともに、今まで以上に、自然が豊かで、子どもたちがいろいろな遊びを工夫し、家族としての役割がはっきりしていたという素敵な違いを強く感じました。
講師の先生方からは、3年生の子どもたちの 話を聞く態度が素晴らしかったこと、質問がたくさんできたことをたくさんほめていただきました。とてもうれしく思いました。
今日の朝会は、INGフラッグについて、児童会の役員から話をしてもらって、子どもたちに紹介をすることになっていました。しかし、運動場には水たまりがたくさんあり、ぐちゃぐちゃになっていたことと、欠席や体調が心配な子どもも多いということから、朝会を中止し、INGフラッグについては、来週に延期することにしました。
このINGフラッグとは、「いじめのない学校づくりに、子どもたちが自ら取り組もうとする意識の高揚を図る」ために、名古屋市立の小・中・高・特別支援学校の各学校が、いじめ防止に関するスローガンを全て掲載した幕のことです。
本校は、児童会の子どもたちが中心になって、「あたたかい言葉と仲間を大切に!」と決めてくれました。
これからも、「愛のあふれる学校」、「自分大好き、友だち大好き、学校大好き」を推進させるために、私は、子どもたちが、あたたかい言葉と仲間を大切にしていこうと、このスローガンを考えてくれたと思っています。
1時間目、全教室をまわって、子どもたちの様子を見に行きました。子どもたちの落ち着いた態度にほっとするとともに、欠席者の空席が、やはり気になりました。早く元気になってほしいと思いました。
今日は、節分です。
豆まきをして、かぜや病気の鬼も退治できるといいなと思いました。
本日、「かぜの予防についてのお願い」のお知らせを配布いたしました。そこにも書かせていただきましたが、かぜによる欠席が増えています。かぜの予防に心がけ、体調のよくない場合は、無理をせず早めになおしたいものです。
学級での早退及び、学級閉鎖という事態が起きては困りますが、万が一の場合は、緊急メールや学校ホームページでご連絡させていただくことになります。
「なごやっ子あんしんメール」の登録が、まだお済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひご登録をしていただけますと大変有り難く存じます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
子どもたちが、元気に登校してくれることをいつも願っています。
最近、私は、できる限り子どもたちの登校時間に合わせて小幡駅から学校に向かって歩き、正門前で、最終の分団が登校するまで登校の様子を見るようにしています。
また、今日は、30日でゼロの日ですから、学区やPTAの方々が、交通安全の見守りをしてくださいました。
いつも、交通安全の見守りをしてくださる方々は、子どもたちにあいさつをしてくださいます。その方々に、自分から進んであいさつをする子どももいますが、その数は少ないように感じます。また、あいさつをするときに、その方々をしっかり見つめてあいさつできる子どもは、さらに少ないと感じています。ほとんどの子どもは、見守りの方々が先にあいさつをしてくださるので、あいさつを返しているというのが現状のように思います。
ですから、今日も自分から進んであいさつできたり、しっかり視線を合わせ、アイコンタクトをしてあいさつできた子どもたちには、「いいあいさつができたね。」と笑顔で声を掛けるようにしています。そして、特に今日は歩道橋の所で、「学区の方々に、自分からあいさつをしましょう。」と、何度も声をかけました。
子どもたちのあいさつについては、学区やPTAの方々からも、ご指摘をいただくことがあります。
確かに、「あいさつ」は強制されるべきものではないかもしれませんが、学区のベストを着たり、横断中・交通安全の旗を持って見守りをしてくださる方々には、感謝の気持ちとともに、いつも、さわやかなあいさつのできる子どもたちでいてほしいと思っています。
| 平成26年1月29日(水) 3年 パンジーの世話活動 |
今日、3年生が12月に小幡駅に植え付けたパンジーの様子を見たり、世話をしたりしに出かけました。
出張があったので、3年生の活動を見ることはできませんでしたが、学校に戻ってきた子どもたちに、「パンジーは元気だったかな?」と尋ねると、声をそろえて、「元気だったよ。」「たくさん咲いていたよ。」と、うれしそうに教えてくれました。とても素直に、明るく返事ができる3年生をうれしく思いました。また、「お父さんを駅に迎えに行くと、いつもパンジーを見ています。」と答えてくれる子どももいました。学区の方々が、水やりなどの世話をやってくださっていると聞いています。学区の方々にも、機会をとらえて、感謝の気持ちを伝えたいと思っています。
| 平成26年1月28日(火) 保護者アンケートのお願い |
昨日、「学校だより2月号」とともに、「保護者アンケートのお願い」のプリントをお配りしました。
苗代小学校が、今年度学習面や生活面で重点をおいて指導したり取り組んだりしていることについて、学校だけでなく家庭でもどのくらい定着し、子どもの成長が見られるのかを把握させていただく資料の一助としたいと考えています。
大変お忙しい時期とは存じますが、2月7日(金)までに、ご提出いただければ幸いです。ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。
| 平成26年1月27日(月) 友だちの良さをほめて、笑顔で帰ろう |
朝会の話についてです。
まず、25日(土)と26日(日)に試合があったバスケット部の子どもたちの頑張りを話しました。試合を見ていて、「最後まであきらめない。」という気持ちが大切だということをあらためて感じたと話しました。
次に、先週の下校の様子で、汚い言葉を言いながら下校していく子どもを見て、残念に思ったことを話しました。ですから、毎日学校にいる間に学級の友だちの頑張りや良さを見付け、それを相手の目をしっかり見て、その友だちに伝えてほしいと話しました。できれば、同じ友だちではなく、いろんな友だちの頑張りや良さを見付けよう。そうすれば、学級の友だち一人一人の自信につながり、素敵な学年のまとめとなります。という内容を話しました。
子どもたちには、「学年のまとめ」を続けてほしい、ほめてもらって笑顔で下校してほしいと考えているからです。私も、子どもたちの頑張りや良さを伝えていきます。
6限、3年生がクラブの活動を見学しました。
クラブは、4年生から6年生までの子どもたちが、異学年交流のできる機会です。ですから、来年4年生になる3年生の子どもたちが、もうすぐ4年生になるという気持ちが高まるこの時期に、「クラブって、何?」を知るために実際の活動場面を見学するのです。
今年は、全部で21のクラブがあります。
3年生は、「いろいろなクラブを見てみよう」のプリントをもって、各クラブの場所を見学していました。そして、「○○のクラブが、おもしろそう。」「とても楽しそう。でも、私は運動は少し苦手だから。」等と、つぶやきながら、見学をしていました。
| 平成26年1月23日(木) トワイライトスクール運営連絡会 |
10時から、トワイライトスクール運営連絡会に、教頭先生と一緒に参加しました。
各種警報等発令時の対応、トワイライトスクール運営連絡会参加のルール等、次年度の運営について協議しました。
低学年の参加が多いこと、APさんをはじめとするトワイライトスクールの運営に参加してくださる方が多く、熱心にあたたかく子どもたちに接してくださっていることをお聞きしました。感謝の言葉でいっぱいです。
今後とも、学区や学校がトワイライトスクールと連携を取り合いながら、子どもたちの成長を見守っていくために、保護者の方々のご協力を今後ともお願い申しあげます。
平成26年1月22日(水) ゲストティーチャー 志水ヒロミチ先生 その2
|
2・3限に、ひまわり2組さんが、ゲストティーチャーの志水ヒロミチ先生と授業をしました。
2限は、「絵しりとり」をしました。言葉で「しりとり」を表現するのではなく、絵で表現する活動です。「言葉だったらすぐに分かるのに、絵でかくのは難しい。」という発言もありましたが、そんな時こそ志水先生の出番です。「こんな風にかいたらどうかな。」と、かいて見せていただきました。ですから、子どもたちは、安心して3分以内でかくことができていました。
3限は、絵しりとりでかいた絵の中から、自分のかきたい絵を選んで、「オリジナル時計」をつくりました。自分のかきたい絵は何なのか、その絵をどのように表現したらよいのかに迷うことなく、かくことに集中できていました。
志水ヒロミチ先生、ありがとうございました。
清掃の終わった後の放課に、3年生の子どもが二人で、「校長先生、お話があります。」と職員室にやってきました。どうしたのと尋ねると、守山商工会青年部主催の「子ども商店街」に出店するというのです。そして、手に持ったチラシを見せながら、「校長先生、ぜひ来てください。クレープのお店をやります。」と嬉しそうに話してくれました。
目的は、地域の子どもたちが将来の夢である商売での体験を通じ、社会性・主体性を身に付ける等というものです。
私は、「手洗い・うがいをしっかりして、がんばってね。」と、声をかけました。来週中には、体験の感想をゆっくり聞かせてもらおうと思っています。そして、子どもたちは、休日を有意義に過ごすために工夫しているなと思いました。
昨日は、バスケットボール部(女子)が市民スポーツ祭の大会に、サッカー部が名古屋市少年サッカー新人大会に参加しました。
同日に試合が重なっていたので、教頭先生と相談して、私は、会場が味鋺小学校のサッカーの応援にでかけました。
味鋺小学校は、私の母校です。私が小学生のころは、運動場の真ん中に木津用水が流れ、春にはメダカやオタマジャクシが泳ぎ、季節の草花が咲き、冬は表面に張った氷で遊びました。体育館やプールもありませんでしたが、自然がいっぱいで、近くの神社や堤防までマラソンをしたり、6年生で真新しい鉄筋の校舎で過ごしてうれしかったりしたことがとても懐かしく思い出されました。
苗代小学校の子どもたちにとって、味鋺小学校のように広い運動場は、勝手が違い試合がやりにくく、いつも以上に大変なことがたくさんあったと思いますが、一勝を勝ち取り、素敵なプレーもたくさん観ることができました。そして、何よりうれしく、感心したことは、新人大会ではプレーのできない6年生が、応援にかけつけてくれたことです。
プレーの最後には、いつものように全員で感謝の気持ちをこめた、「ありがとうございました。」のあいさつをしていました。さわやかで、すばらしいチームだと思いました。
来週は、バスケットボール部の素敵な姿を見付けに、応援に行きたいと思います。
保護者の皆様、早朝からのお弁当づくりや、大勢応援に駆けつけていただく等、ご協力ありがとうございました。
もちろん、今朝の職員室は、部活動の担当者と応援に駆けつけてくれた職員や、試合の結果を気にしてくれた職員が、子どもたちの頑張りや課題で盛り上がっていました。 あたたかい職場に、今日も感謝です。
昨日は、1・3・5年生が、今日は2・4・6年生が朝の運動で縄跳びをしました。2日に分けて実施するのは、安全面の配慮からです。
840名の全校児童が、全員で短縄跳びをするには、運動場のスペースが不足していて危ないからです。
それでも、子どもたちは、運動場いっぱいに広がって、元気よく跳んでいました。
本校では、冬の体力づくりに、短縄跳びは欠かせません。練習すればするほど、できる喜びを味わえるからでしょうか。
放課の時間にも、多くの子どもたちが取り組んでいます。
「二重跳びができたよ。」等と、応接室にいる私に自信満々に見せてくれます。
昨日の5限には6年生が、道徳 「お互いを尊重して意見をまとめよう」、今日の2限には2年生が、生活科 「自分はっけん」で、学校教育努力点の公開授業をしました。
6年生の学級では、ゲーム感覚の活動でしたので、子どもたちが早くやりたいという意欲を強く感じる授業でした。また、小グループで話し合う場面が、多い授業でもありました。どの子どもも、のびのびと発言する姿が特に印象に残りました。
2年生の学級では、短時間の中で全員が発表する授業でした。その中で自分の思いを伝える言葉として、「ジグソーパズルの最後の1枚をはめるときのような〜」、「自分ならできる、自分ならできる〜」「○年生のお姉さんに教えてもらったので〜」など、聴き手がイメージしやすい言葉で分かりやすく伝える子どもの姿を見ることができました。
| 平成26年1月15日(水) ゲストティーチャー 志水ヒロミチ先生 その1 |
2・3限に、ひまわり学級1組と3組 5・6年生の子どもたちが、志水先生と授業をしました。世界に一つしかない自分の絵の時計をつくるという授業です。志水先生は、とても優しく子どもたち一人一人に話しかけながら、絵の表現を高めていくサポートをしてみえました。子どもたちの思いをとても大切にしてみえる姿に、志水先生のお人柄がにじみ、教室中があたたかい雰囲気に包まれていました。
出来上がった作品の良さを、一人一人ほめていただき、子どもたちも、照れた表情をしたり、にこにこの笑顔を見せたりしていました。「楽しかった。」という子どもたちの感想も聞かれました。
ぜひ、ご家庭でも今日の作品を飾って、時計として愛用してもらえたらと思います。
志水ヒロミチ先生、ありがとうございました。
来週は、ひまわり2組さんが、志水ヒロミチ先生と授業をする予定です。
| 平成26年1月14日(火) PTA壁新聞コンテスト |
1月11日(土)、日本ガイシホールで、開催された「ファミリーデーなごや」にでかけました。苗代小学校PTAの方々に、大勢お会いしました。ブースでは、順番を待つ人で列ができましたが、私も並んで、ドングリペンダントをつくりました。ドングリには既にヒートンも付けられ、短時間でつくることができるように工夫されていました。材料のドングリや松ぼっくり集めに始まった準備が、とても大変だったことが予想できました。本当にお疲れ様でした。
全PTAの壁新聞をゆっくり見て、投票もしました。
その後、ステージでは、守山区のPTA役員が中心になってできた守山バンドの演奏が行われました。心あたたまる雰囲気の演奏に、たくさん手拍子をし、「音楽のおくりもの」の歌を一緒に歌い、楽しいひとときでした。
今朝、教頭先生から、「苗代小PTAは、PTA壁新聞で優秀賞をいただきました。」と賞状を見せてくださいました。うれしかったです。

| 平成26年1月10日(金) 交通事故ゼロの日 三連休 |
新年に入って初めての交通通事故ゼロの日の交通当番をしました。今朝は格別に風が冷たく感じられる日でしたが、学区やPTAの方々も見守りをしていただき、ありがとうございました。今年も、子どもたちが安全に登下校できることを切に願っています。どうぞよろしくお願いいたします。
明日から三連休です。
1月11日(土)は、日本ガイシホールで、「ファミリーデーなごや」が、開催されます。苗代小学校PTAは、守山区のブースを担当します。午前10時に開会式が行われ、午後4時までの予定です。ぜひ、応援にお出かけいただき、「どんぐりペンダント」または「松ぼっくりけん玉」をお子様と一緒に作りませんか?各学校PTAの活動を紹介する壁新聞コンテスト投票もあります。
PTAの方々が、協力していろいろな準備をしてきてくださいました。私も、おじゃまする予定です。
また、1月13日(月))成人の日は、守山区役所で成人式に参加させていただきます。苗代小学校の卒業生にもお会いできるので、楽しみにしています。
| 平成26年1月9日(木) 廃品回収 6年 公開授業 |
今朝、環境委員会の子どもたちと担当の先生達が、資源回収の活動をしました。寒い朝でしたが、一生懸命やってくれました。うれしい限りです。
4限と5限には、6年生の2学級が努力点の公開授業をしました。
3学期が始まったばかりですが、子どもたちは大変落ち着いた態度で、授業にのぞんでいました。6年生がめざす児童像は、「相手の意見を尊重し、自分の考えを伝えることができる児童」です。授業では、友達から受けた意見や考えについて、質問したりグループで検討しながらまとめたり、参考にしながら自分の考えにまとめたりする姿を見せていました。どちらの学級も、子どもたちが安心して発言したり話し合ったりしている姿が、とても印象に残りました。
| 平成26年1月8日(水) 3学期の目標を私に伝えてくれた子ども |
今朝、正門前で登校指導をしていると、子どもが、私に声を掛けて3学期の目標を教えてくれました。昨日の始業式で、「私と会ったときに、みなさんの3学期の目標を教えてもらえるとうれしいです。」と話はしましたが、その子どもの素直さと、私の話をしっかりと聴いていてくれたことに、とても幸せな気分になりました。思わず、私は、その子どもと笑顔で握手をしていました。
今日は、10日ぶりに子どもたちが登校する様子を見たり話しかけたりすることができてとても楽しかったです。
子どもたちは、始業式で、落ち着いた態度で話を聴くことができていました。転入生にも、苗代小学校の子どもたちがめざしている「自分大好き、友達大好き、学校大好き」を知ってもらい、今後もみんなで頑張ってほしいと願い、大きな声で子どもたちに言ってもらいました。
その後、次の2点について話しました。
1点目は、冬休み中、私が大の苦手な料理作りに努力したこと。苦手なことをやるからこそ、いかに短時間で工夫して料理をつくるのかを一生懸命考えることが楽しいと思えたこと。
2点目は、私の3学期の目標は、みんなの良さをホームページ「愛のあふれる学校づくり」で情報発信していくことであること。みんなにも目標に向かって、頑張り続けてほしいと思っていること。6年生は卒業まであと50日、1〜5年生は卒業式を含め51日であることを話しました。
3学期は、学年のまとめの時期です。みんなで一緒に目標に向かって頑張ることができるよう、互いに支え合う苗代小学校の子どもたちでいましょう。職員一同、力を合わせます。どうぞご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
| 平成26年1月6日(月) 今年もよろしくお願いします |
今日は、平成26年の仕事はじめです。
実は、昨日も学校へ寄りました。本校PTA会員様のご葬儀が執り行われたからです。心よりお悔やみを申しあげるとともに、お子様が学校にいる間は、せめて少しでも心穏やかに過ごせるように見守って参りますと、ご焼香をさせていただきながら強く念じました。
ところで、冬休み中に1名の転入生がありました。始業式で紹介いたします。
今後とも、この学校ホームページ「愛のあふれる学校づくり」で、学校の情報発信をしてまいります。今年もどうぞよろしくお願い申しあげます。
今日は、今年の仕事納めです。
私も業務士さんと、校内の戸締まりを確認しました。
冬休みに入って、業務士さんが、階段付近の壁を綺麗に塗装してくださっています。また、応接室の窓やカーテンも、ピカピカにしてくださいました。有り難いことです。
明日から1月5日まで、ホームページは、お休みをさせていただきます。このホームページを大勢の方々に読んでいただき、本当にうれしく思っています。
来年もよろしくお願いします。
今日は、私の子どもの誕生日です。毎年、この日は、子どもが生まれた日のことを思い出します。大雪が降り、とても寒い日でした。病院の窓を見ると、白い雪があとからあとから降ってきて、とても美しかったこと。痛くて、苦しくて、病院内に響き渡るような声で、「もう嫌だ!」と叫び、付き添いの母を恥ずかしさで一杯の気持ちにさせたこと。誕生したばかりの子どもを初めて抱き、落としそうでこわかったこと。等々。
子どもを通して、いろいろな体験ができています。子どものお陰で、自分も、少しは成長できたと思っています。
保護者の皆様方も、きっとそんな思い出をお持ちのことと思います。ぜひ、ご自分のお子様に、子どもたちが、もっともっと幼かった時のことを聞かせてあげてほしいと思います。
「あなたは、とても大切な存在であること。あなたの成長は、自分の力だけでなく、みんなのお陰でもあること。あなたのお陰で、私も(親も)成長できていること。」
私は、子どもの誕生日をそんな思いを大切にする日にしています。
サッカー部には、応援に行けず、子どもたちや指導の先生方に大変申し訳なかったです。 「全員の子どもを、試合に出すことができました。」と指導の先生が、さわやかな笑顔で話をしてくださいました。子どもたちには、試合に出場した時の緊張感や頑張りをこれからの試合や生活にどう生かしていくのかを考えて、行動してほしいと思っています。
バスケット部は、苗代小学校が会場校でした。子どもたちの足の速さに、びっくりしました。とてもパワーを感じました。男子は、シュートへの粘り強さに、女子は、シュートの確率がとても高いなと思いました。昨日の男子の試合も女子の試合も、とてもさわやかで、フェアープレーの気持ちの良い試合でした。子どもたちの素直さや、やさしさが試合ににじみ出ていました。子どもたちのプレーする姿を見ていて、苗代の先生方がスポーツを通して、子どもたちの心をきたえているということを確認できて、とても誇らしく思いました。男子の試合には、女子部員が、女子の試合には、男子部員が来て、応援したりモップをかけたりしてくれていた姿もうれしかったです。
保護者や職員の皆さん、心のこもった応援をありがとうございました。
卒業文集の原稿が、20日に完成しました。子どもたちが、一生懸命書いたページを1ページずつ読ませてもらっています。
子どもたちの思いをたくさん感じて、楽しい時間です。
今日と明日、バスケットボールとサッカーの区の指導会が開催されます。楽しみです。
終業式での話を紹介します。
「3学期には、1・2学期よりも具体的な目標を立てましょう。その具体的な目標を継続してやりましょう。そのために、何をどれだけ頑張るのかを冬休み中に考えてやってみましょう。」という内容について話しました。
最初に、今年の修学旅行で、座禅・抹茶体験をさせていただいた大仙院のご住職様から、みんなの願いが目標達成できるようにと書いていただいた書を見せました。この書のように、3学期も具体的な目標を立てて、頑張ってほしいと伝えました。
次に、私が、2学期、特に子どもたちが頑張ってきたと思ったことについて、自己評価をしてもらいました。気を付けの姿勢での話の聴き方、名札着用に始まり、一輪車、竹馬、学芸会でのせりふや動きの工夫、授業の発言、調べ学習のまとめや発表等です。
たくさん手があがりました。
そして、「創立40周年」の話をしました。
私が教員になった年は、苗代小学校創立5周年であったことや、その当時の苗代小学校付近の航空写真を見せ、校舎や周辺の様子等がどう変わったのかに気付いてもらいました。その記念すべき年に、今、みんながいること、これまでに大勢の子どもたちが素晴らしい伝統を築いてきたことを伝えました。
ですから、皆さんも具体的な目標を立てて、3学期も頑張りましょうと話しました。
下校するときには、子どもたちに「良いお年を。」と声を掛けながら送り出しました。子どもたちが、家族や学区とのつながりを深める冬休みを元気に過ごしてくれることを心から願います。
ご協力、ありがとうございました。
2学期最終の給食の献立は、ごはん、牛乳、コロッケ、カレースープきしめん、ふりかけでした。この中で、カレースープきしめんは、新献立です。
私は、昨日からこの新献立を楽しみにしていました。カレーうどんのように濃い味付けをイメージしていましたが、実物は、カレーの風味があっさりとしていて、とてもおいしいと思いました。
調理所の職員の皆さん、2学期もおいしい給食をありがとうございました。3学期もよろしくお願いします。
また、給食の献立表を見ると、毎月19日は「食育の日」と書いてあります。学校ではみんな一緒に食事をし、おしゃべりを楽しんでいます。冬休みも子どもたちが、家族とおしゃべりをしながら食卓をかこむ日が、たくさんあるとうれしいなと思いました。私も、とても苦手な料理作りを家族のために頑張ります。
| 12月18日(水) 6年生と音楽の授業 学芸会アンケート結果 |
1限に、6年生と2学期最後の音楽の授業をしました。私と一緒に学習した曲をメドレーのようにリコーダーで演奏したり、部分的に独奏や重奏をして実力を発揮してもらったりしました。その後、「○○の曲を歌いたい」という子どもたちのリクエストで、2曲歌いました。私は、子どもたちの間を歩き、一人一人の声を聴きながら歌ったり、強弱に気を付けて歌えるように指揮をしたりしました。昨日の合唱コンクールの余韻を感じさせる響きのある歌声を聴かせてくれました。また、一緒に歌いたいです。
明日、学校だより(冬休み号)で、学芸会アンケート結果をお知らせいたします。
在籍児童840名のうち、アンケートにご協力いただいた方は651名で、約77.5%となりました。苗代小学校が大切にしている、「自分大好き 友達大好き 学校大好き」についても概ね良い結果を頂けたと思います。ありがとうございました。
現在のところ、学芸会は、造形展と交替で隔年ごとに実施していきたいと考えています。学年児童数が多い、照明器具の明るさや観客席の広さ等については、本校の実態を見据えると改善が難しい点もあります。しかし、貴重なご意見を参考に、職員と話し合い、よりよい学芸会をめざしていきたいと考えます。
また、学芸会当日はともかく、それまでの子どもたちの様子はなかなか保護者には分かりにくい。子どもたちの保護者アンケートではなく児童アンケートこそとるべきだというご意見も聞いています。アンケートの記名についてのご質問も受けました。PTA家庭教育セミナーでもお話ししましたが、記名は強制ではありません。どなたのご意見なのかがはっきり分かり、保護者と担任や職員とのコミュニケーションが深まることを願っています。
先週13日(金)に、6年3組の歌声を初めて聴かせてもらいました。自分が心を込めて歌うことへの意欲を強く感じさせる歌声で、感心しました。
事前に、4学級全ての歌声を聴かせてもらうことができました。
さて、今回の合唱コンクールで、子どもたちが選曲した曲について、私なりの紹介をし本番の子どもたちの様子もお伝えできたらと思います。
6年1組の子どもたちの歌った曲は、「桜ノ雨」です。4分の4拍子の流れの中に、卒業を間近に控え、友との別れの寂しさや、これまでの思い出を振り返り、新しい未来への期待と不安を歌っています。そして、僕らは一人ではない、またいつか会おう。という気持ちを歌っています。ですから、6年生の子どもたちには、歌詞に表現された気持ちがイメージしやすいと思います。ただ、十六分音符やハーモニーに気を付けながら、気持ちの変化をどのように歌うかに難しさを感じます。
実に、子どもたちが指揮者をよく見て歌っていました。一人一人の歌おうとする意欲が声に込められていて、感情移入した自然な身体の揺れが素敵でした。心に思いを届ける歌声は素晴らしいと思いました。
6年2組の子どもたちの歌った曲は「手紙」です。NHKコンクールの課題曲にもなりました。4分の4拍子の曲です。この曲を聴いたことのある子どもたちも多いと思います。ですから、歌い手には歌いやすかったかもしれませんが、逆に聴き手には歌の仕上がりの善し悪しがはっきり分かってしまうという難しさを感じます。語る部分と、気持ちを強く届ける部分の変化を大切にして歌うことが、大切だと思います。
歌詞が、とても鮮明に、耳に届きました。そして、のばす声の支えがしっかりとしていて素敵でした。歌っている子どもたちの表情が、やわらかく、おだやかな笑顔で、とても素敵だなと思いました。自分の曲への思いをストレートに感じさせる指揮の仕方も、印象に残りました。
6年3組の子どもたちの歌った曲は、「地球星歌」です。8分の6拍子の流れの中に、地球の壮大なスケールや、そこに生きる生物全ての命の息吹を感じさせるような雰囲気をもっています。そのために、歌詞を大切に歌うことがとても要求される曲だとも思います。拍子の流れに乗りながら、流され過ぎず、思いの深さを伝えることの難しさを感じます。
その歌声のやさしさや、あたたかさを実に感じさせてくれる、素敵な合唱でした。最後ののばす声のフレーズが、金曜日よりもずっとうまく歌えていました。曲の雰囲気を大変うまくつかんだ曲に仕上がり、聴いていて、とてもやさしい気分に浸ることができました。
6年4組の子どもたちの歌った曲は、「未来への賛歌」です。4分の4拍子の曲です。シンコペーションを生かしたり、十六分音符でリズムを刻む部分となめらかさの変化を大切にしたりして歌うという技能が要求されます。また、最後のフレーズで、腹筋の支えをしっかりとして声をのばして歌うかどうかが大切です。
歌い始めてすぐに、声に勢いを感じさせる歌声になったと感じました。無理のない素直な声の出し方で、二部合唱の部分もきれいでした。強弱が、よく表現されていました。最後の声をのばす部分も、しっかり歌うことができていました。曲として、よくまとまっていました。
4限に、体育館は、子どもたちの熱気であふれていました。子どもたちが、気持ちを一つにして歌おうというパワーをたくさん感じることのできた楽しい時間でした。コンクールと言うよりも、合唱フェスティバルという雰囲気を醸し出していました。歌うことって、楽しいなと感じさせるように、合唱コンクール実行委員も力を発揮してくれました。
子どもたちが、今日までの努力を達成感として味わい、仲間を思いやり、仲間とともにこれからも成長してほしいと強く感じました。
今日の朝会は、まず税に関する習字の表彰を行いました。苗代小学校は、とても大勢の子どもたちが作品を応募をしています。その中でも、今回は、とくに優秀な成績をおさめました。子どもたちの頑張りを認めていただけたことに、感謝しています。
その後、教務主任の中西先生から、苗代小学校がずっと取り組んできているJRC活動について、JRCの言葉の意味をはじめ、大切にしている精神について話をし、JRC部の子どもたちが、明日から実施する募金活動について説明をしました。苗代小学校の子どもたちは、これまでに古切手やペットボトルのキャップを集めてきています。JRC部の子どもたちは、それらの活動が、何のためなのか、どんな思いがあって活動をしているのかをあらためてみんなに伝え、これからも、自分たちにできることを続けていけたらと思っています。
決して強制するものであってはなりませんが、こつこつと自分にできる範囲で、JRCの活動を続けていくことが、何より大切だと考えます。
守山スポーツセンターで、9時半から「守山区モリスちゃん杯学区対抗ディスクドッヂ大会」が、開催されました。子どもたちは、開会式が始まる前に、観覧席にいる私を見付けて手を振ってくれたりお辞儀をしたりしてくれました。うれしかったです。
会場には、学区の茂木様や保護者の方々が、みえていました。子どもたちが、今日まで練習を頑張ってきたことをその方々から、たくさん聞かせていただきました。残念ながら、試合は見ることができませんでしたが、監督の話を真剣な表情で聴いている子どもたちを見ることができました。3位に入賞したそうです。素晴らしい。
11時には、リコーダー部が出演する「名古屋リコーダーフェスティバル」の会場ウィルあいちへ移動しました。保護者の方々や担任の先生方が、応援に来てくださいました。練習の成果を発揮した演奏ができました。会場が、クリスマスの雰囲気に包まれたように感じました。
| 12月13日(金) 3年 パンジーの苗ポット植え付け |
9時ごろから、小幡駅のロータリーにある花壇に、パンジーの苗ポットを植え付けにでかけました。
子どもたちは、学校から一人3ポットずつ苗ポットを持って行きました。「パンジーの命を大切に、苗を落とさないよう袋をしっかり持って行こう。」と、小幡駅に向かいました。 小幡駅に着くと、既に総勢約15名ほどの守山土木事務所や緑の協会、学区の方々が、集まってみえました。
苗の植え方を指導していただいてから、子どもたちは、うれしそうに植え付けをしていきました。
植え付けを終え、子どもたちが集合した後、学区の余語様、茂木様、服部様の3名からご挨拶を受け、子どもたちの頑張りをほめていただきました。大変寒い中、子どもたちの頑張る姿をしっかり見て、認めてくださる学区の方々がいらっしゃることを子どもたちに覚えていてほしいと思いました。
そして、種から育てた大切なパンジーが、きれいに咲き、小幡駅を行き交う方々の心をやさしい気分にすることができたら、どんなにうれしいことでしょう。

5限に、分団会議がありました。分団長が司会をし、分団登校について2学期の反省をしたり、担当のPTAの方や先生から冬休みの生活についての話を聞いたりしました。 一斉下校では、子どもの交通事故が増えていること、右左右をしっかり見て横断すること、飛び出さないことを伝えました。
子どもたちの「さようなら」の元気な声が、素敵でした。
1限に、6年生と音楽の授業をしました。今日のめあては、音に集中して聴くことです。
伴奏を聴いて、リコーダー演奏の出だしを聴き取って演奏すること、楽譜を見ながら休符の拍を正確に聴き取って演奏すること、強弱を生かした伴奏から曲の山を聴き取って演奏することを「スワンダフル」「夢の世界を」の2曲を演奏する中で学習しました。
子どもたちは、伴奏や他のパートのリコーダー演奏をしっかり聴いて、演奏することができました。何より、曲を演奏し終えると、一瞬、音のない沈黙の間ができました。素敵なことです。演奏の余韻を感じ取れるからです。
6年3組の歌声を聴かせてもらえる日が、13日(金)に決まりました。うれしいです。
5日(木)は6年4組、9日(月)は6年2組、今日10日(火)は6年1組で、合唱コンクールの歌を聴かせてもらいました。あとは、6年3組の歌声を聴かせてもらいたいとお願いをしたところです。合唱祭までに、4学級の歌声を聴かせてもらえれば、うれしいなと思っています。
卒業への思いは、卒業アルバムの写真を撮影したり、文集を書いたりしている中で、少しずつふくらんできていると思います。そんな6年生に、合唱コンクールは、心を合わせて歌う楽しさを卒業までの思い出の1ページに加えてもらう機会だと私は考えています。
もちろん、合唱コンクールは、子どもたちが話し合って、担任と相談して、学年行事として「やりましょう」と決まった活動です。
今日までの歌声を聴いて、歌詞を大切にしている姿に、声を一生懸命出そうと頑張っている姿に、指揮者をしっかり見て歌っている姿に感心しています。
合唱コンクール当日までの子どもたちの成長を楽しみに、教室へふらっとお邪魔したいなと思っています。
昨日、出先で、側溝にたまった枯れ葉の清掃を黙々としていた大勢の学生達の姿を見ました。その話から、苗代小学校でも、ボランティアを頑張っている子どもたちがいることを紹介しました。相手を思いやって行動できる素敵な子どもたちのことを紹介したかったからです。
頑張った内容は、ご高齢の方々への年賀状作成、自主的な靴箱清掃、友達へのサポート、年末提灯パトロールへの参加についてです。
これからも、そして冬休みの期間も、誰かのために自分にできることを進んで行い、自分大好きになりましょうと話しました。そして、学校だけでなく、家族はもちろんのこと、学区の方々にも、もっと子どもたちのよさを知ってもらいたいと思っています。そのためにも、冬休みは良いチャンスです。
でもその時に気を付けることとして、座席を譲る時の例をあげ、「よかったら、おかけになりませんか?」と声をかけることが大切だとも話しました。自分が良かれと思ってやったことが相手には迷惑になったり、その方ができることを妨げてしまったりする等の場合があると考えているからです。
私も、つい親切の押し売りをしてしまうことがあります。自分にも言い聞かせるつもりで話をしました。
今日の午後、英語活動の先生が、6年担任に、「子どもたちが、カントリーロードの曲を英語で歌ってプレゼントしてくれて、とてもうれしかったです。」と話していらっしゃいました。その話を聞いて、近くにいた私までとてもうれしくなりました。
「カントリーロード」の曲を歌っている子どもたちの表情が、すぐに思い浮かんできました。
今、6年生は、17日(火)に開催する合唱コンクールに向けて、どの学級も練習に励んでいます。合唱コンクールの実行委員が中心になって、頑張っているそうです。
楽しみです。
今日の1限、6年生と歌の授業をしました。
歌には歌詞があります。歌詞は、学芸会の劇のせりふと同じで、誰に言っている言葉なのかという思いについて考えることが大切だと思っています。その思いがあれば、自然に強弱や速さ、曲の山などを工夫してどのように歌ったらよいのかを考えることができるからです。音楽科の学習という面から言えば、楽譜に書かれていることをしっかり見て、忠実に正確に歌うことは、確かに大切です。でも、歌う人が、なぜそのように歌いたいのかということは、歌で観客に気持ちや思いを伝える、「表現する」という上で、とても重要だと考えます。
また、子どもたちの合唱を聴かせてもらいながら、「歌で表現する方法」をみんなで学習しました。特に練習したのは、次の3点です。
1 口の中をしっかり開けて、歌う
2 大切な言葉の子音をはっきり歌う
3 腹式呼吸の仕方を学ぶ
昨日の校長会で、今月もまた子どもたちの交通事故についての話がありました。
命に関わる交通事故の件数が多いことや、その原因として、自転車に関する事故や飛び出しがとても多いと言う内容です。
子どもたちは、「ヘルメットをかぶること」や落ち着いて「止まる」ということはしっかり分かっていると思います。でも、大丈夫だと思っても念には念を入れ、「止まって右左右」の確認をしっかりしてほしいと思います。
命を大切にしましょう。
今日の1限、大なわ大会がありました。体育委員の子どもたちが、司会をはじめ大活躍をしました。
異学年交流が大きな目的です。子どもたちの連続して跳びたいという真剣な表情や、高学年と低学年のペアのほほえましい姿に、この活動の意義を感じました。

| 12月 3日(火) ペットボトル提灯で防犯パトロール |
昨夜、学区の方々や子どもたちが、小幡緑地南公園に集合し、苗代学区年末一斉提灯パトロールが開催されました。
私は、午後6時ごろに学校を出て公園に向かいました。正門では、子供会の担当の方や子どもたちが、待ち合わせをしていました。
公園に近付くと、公園の周りにはペットボトル提灯にろうそくがともされ、とてもきれいでした。その後、太鼓の演奏を楽しみ、セレモニーがスタートしました。学区連絡協議会長、守山警察署の方や守山区長様のご挨拶を受け、7時半ごろ、各町内に分かれてのパトロールが始まりました。
6年生が、カラフルな色に仕上げてくれたペットボトルが、ろうそくの光に映えて幻想的な雰囲気を醸し出していました。子どもたちもたくさん参加していました。
自分たちの学区を自分たちで守ろうとする学区の方々の思いや努力をしっかり子どもたちに引き継いでほしいと思いました。
朝会で、人権週間に関連して、「命の話」をしました。
私の体験談です。これまで、私は、12月に「死」に直面することがよくありました。悲しみや寂しさは、時が解決をしてくれることもあります。そして、自分の心には、その方との思い出が永遠に残っています。
けれど、残された家族や友達、周りの方の心は、傷つくのです。
だからこそ、自分の命も人の命も大切にすべきだと思います。
ぜひ、人権週間をきっかけにして、友達や周りの方のよさや、大好きな面をたくさん見付けてほしいと思います。
朝の職員打ち合わせで、養護教諭の先生から、「けが」についての話がありました。最近、校内でのけがで病院へ行く「けが」が、増えているからです。また、保健室で治療してもらったことを担任や担当の先生に話さない子どもが増えてきているようです。治療してもらって、安心して報告を忘れてしまうこともあるでしょう。また、養護の先生からは担任や担当の先生に連絡が入りますが、タイムラグがあっては大変です。
学校では、緊急の場合を除いて、体調が悪いときやけがなどで保健室に行く場合は、まず、担任や授業を担当している先生に、理由を話して保健室に行きます。ですから、子ども本人から直接報告をすることはとても大切です。自分の身体に関わる大切なことだからです。
子どもたちには、これまでにも各クラスで、「落ち着いて行動する」ことを指導してきています。
学校生活に慣れ、運動場では寒くても元気に運動する子どもが増えてきているからかもしれませんが、これからも、自分の身体も友達の身体も大切にする子どもでいてほしいと思います。
昨日は4年生が、今日は3年生が校外学習に出かけました。
4年生は、愛知県陶磁器工業協同組合で絵付け体験をしたり、瀬戸蔵ミュージアムで瀬戸の焼き物の歴史や焼き物づくりの現在と未来について見学を通して学んだりしました。
3年生は、キューピー工場で食品がつくられる様子を見学したり、働いている方の話を聞いたりして、ものづくりの仕事について学びました。
お弁当の準備等、ありがとうございました。
| 11月27日(水) ジョージ・ガーシュウィンとジャズ その2 |
ジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディー イン ブルー」、「ス ワンダフル」と、3年生で学習した既習曲の「聖者の行進」を教材として、6年生と音楽の授業をしています。今日は、その学習の2時間目です。
月曜日の授業で、「強弱や速度の変化」や「ピアノとオーケストラの掛け合い」について着目して感想を書くことができた、子どものよさを紹介したり、再度鑑賞して子どもたちとそれらを確認したりしました。その後、「聖者の行進」を二部で演奏したり、最後のフレーズを変化させてゆらしたりして、ジャズっぽい表現をしてみました。
私は、子どもたちの表情が、「あっ、そうか。」と変化していく姿を見ることができて、楽しかったです。
| 11月26日(火) 6年、ひまわり組(6年) スクールランチ試食会 |
守山東中学校へスクールランチの試食と中学校生活についての話を聴きに6年生の子どもたちがでかけました。出かける前に、6年学年主任の先生から、中学校の先生方がみんなに会えることを楽しみにしていること、今日はみんなのよさをしっかり見せましょうという話がありました。
外は冷たい風が吹いていましたが、早く整列できた子どもたちが、私に自分の選んだ献立のメニューについて、うれしそうに話してくれました。子どもたちは、とても楽しそうに出かけていきました
| 11月25日(月) ジョージ・ガーシュウィンとジャズ |
6年生の音楽の教科書に、ジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディー イン ブルー」がのっています。
先週の金曜日から、作曲家のジョージ・ガーシュウィン、彼の作曲した「ラプソディーイン ブルー」をはじめとする曲や、ジャズについて、にわかに学び始めています。今日も子どもたちが下校して、かたっぱしから彼の作曲した曲を聴いています。
なぜなら、子どもたちと一緒に授業する機会を得たからです。
アメリカで生まれたジャズと伝統的なクラシック音楽を合わせる試みを行った作曲家について学び、子どもたちの「ジャズって何?」の質問に、音楽を通して、少しでも答えられるようにしたいです。
午前中、校長会の修学旅行委員会の出張でした。
その帰り、小幡駅から学校に向かうと、広い道路沿いに銀杏並木があります。毎日、通る道なので、日に日に銀杏の葉が黄色に色付き、「きれいだな。」と思っていました。 そんな感じで、私は、今日も木を見上げていたら、自然に、「夢の世界を」の歌を口ずさんでいました。
「 ほほえみ かわして 語り合い 落ち葉をふんで 歩いたね
並木の 銀杏をあざやかに はるかな ゆうひを うつしだしたね 〜 」
秋の深まりを味わいながら、学校まで歩いていきました。苗代学区には、素敵な自然が、満載です。
午前中、生活科室では、守山中学校ブロックと守山東中学校ブロックの学校事務の学校間連携の会が行われました。各学校の事務職員は、1名か2名しかみえません。そこで、事務職員が、ブロック内で連携して執務を行うことで、事務の適性化・効率化を図ったり、事務支援センターの指導を受けたりして資質向上を図るというねらいがあります。
その会に私も参加させていただき、日ごろなかなか情報交換のできない2ブロック内の事務職員の方々とふれあうことができました。また、今どの学校でも話題になっている内容について、事務職員としての立場からのお話をうかがうことができて、大変参考になりました。
今日は、20日のゼロの日です。いつもでしたら、歩道橋のところで、交通安全指導を行うのですが、市校長会があり、できませんでした。
市校長会では、市教育委員会指導室と愛知県警の方から小学生を含む交通事故が多発していること、交通安全指導を今後も進めてほしいという話がありました。
先週、朝の打ち合わせでも、子どもが被害に遭った大きな交通事故について、職員に話をしたばかりです。
また、先日には、小幡駅に向かって歩いていると、自転車に乗った子どもたちと出会いました。ヘルメットをかぶっている子どもたちばかりでしたので、安心しましたが、うす暗い中でライトを付けていない子どももいましたので、声をかけたこともありました。
これからも、交通ルールを守って、ヘルメット着用やハンドアップにも気を付けてほしいと思います。
ご家庭でもご指導のほど、よろしくお願いします。
| 11月19日(火) 1年・ひまわり組(1年) 校外学習ー小幡緑地公園 |
1年生が、生活科の授業で、小幡緑地公園に木の実や葉っぱを取りに行きました。
午前中は、風も少なく日差しもあたたかかったので、とても快適な校外学習となって良かったと、先生方からうかがいました。子どもたちは、公園内をとても長い距離を頑張って歩いたそうです。
午後は、学校に戻り、疲れが出たせいか、眠そうな表情の子どももいたそうです。
木の実や色付いた葉を見付けて季節を感じたり、おいしいお弁当を食べたりして、有意義な時間を過ごしたようです。
次は、今日のドングリや葉等を使って、次の活動に進むそうです。
朝会の話をご紹介します。
1番に、学芸会での頑張りをほめました。みんなのチームワークのよさが、素晴らしい演技に表われていて、とても素晴らしかったことを伝えました。これからも、そのチームワークのよさを持続して、3月まで過ごしてもらいたいと話しました。
次に、学芸会アンケートに関する質問をして、子どもたちには、挙手で答えてもらいました。家庭で、学芸会の話をした子どもたちは、たくさんいました。家族にほめてもらった子どもたちは、多かったのですが、私の予想よりは、多くはありませんでした。そして、アドバイスをもらった子どもは、予想以上にたくさんいました。
とにかく、保護者の方々が、学校行事に関心をもち、子どもたちと話をしていただく機会となったことは、とても有り難いと思いました。ありがとうございました。
今日の午前中は、B児童が出演し、A児童は鑑賞でした。雨が体育館の屋根にあたって、大きな雨音が子どもたちのせりふを聞き取りにくくする場面もありました。しかし、そんなハンディーは何のその、子どもたちは、一生懸命演技に取り組んでくれました。
午後は、雨も上がりましたが、足下の悪い中、大勢のお客様がお越しくださいました。 私は、12:00過ぎから、体育館入り口で、あいさつをしながら、お客様をお迎えしていましたが、「開会のことば」が始まる前で、約150名の方がいらっしゃいました。 その後は、昨日と同じくらいのお客様が、常時鑑賞してくださいました。私は、今日も昨日と同じように、演技を終えた子どもたちを拍手で迎えました。満足げな表情をした子どもたちが、ほとんどでしたので、心から、よかったなと思いました。
来賓のお客様からは、「子どもたちの頑張りに感動した。」「よかった。」「楽しかった。」「すごいですね。」等とお褒めの言葉をいただきました。
苗代小学校の素晴らしい子どもたちに大きな拍手を送るとともに、お支えいただいた方々に感謝申しあげます。ありがとうございました。
保護者の皆様におかれましては、11月1日に配付させていただいた「学芸会アンケート」にご協力いただければ幸いです。よろしくお願い申しあげます。
今日の午前中は、A児童が出演し、B児童は鑑賞でした。
各学年の演技が終わった後、保護者席の後ろで拍手をしながら、笑顔で子どもたちを迎えました。晴れ晴れとした笑顔をみせてくれる子ども、照れくさそうに軽く会釈をしていく子ども、にこにこしてハイタッチをしていく子どもの姿をみることができました。とても楽しい時間となりました。
午後は、常時約250〜300名のお客様が、多いときは、約400名の方々が、子どもたちの演技を観てくださいました。寒い中、そして、隣の椅子との間隔が狭くて、窮屈な中で鑑賞していただいたことに、本当に感謝したいと思います。おかげで、子どもたちの練習の成果がしっかり発揮できました。ありがとうございました。また、子どもたちは、同じ演技をしても、苗代小の子どもたちと、お客様とでは、全くリアクションの異なる場面があったので、びっくりしたり戸惑ったりすることがあったかもしれません。でも、これが演劇のおもしろさだと思います。このことで、観客を意識し、演技することの大切さに、気付いた子どもがいたら、うれしいなと思いました。
明日は、B児童が出演します。とにかく、劇をみんなでつくる楽しさをたくさん感じてほしいと思います。
今日は、子どもたちの頑張りに、惜しみない、大きな拍手をありがとうございました。
1時間目から、校内の倉庫を教務主任さんとまわりました。どの倉庫も所狭しと物が置かれていました。実は、学芸会で使った用具で、残しておきたい道具をしまう場所のスペースを確認したのです。でも、片付けるスペースは、やはりほとんどありません。
工夫して、学芸会グッズとして、まとめておけるように段取りをしてもらいました。あとは、本番を待つのみです。
| 11月12日(火) 万全の体調で学芸会にのぞみましょう |
急に寒くなってきました。朝の登校時には、厚手の上着を着て登校して来る子どもが増えました。また、このホームページを打っている間にも、「寒い、寒い。」と言って下校していく部活動の子どもたちがいます。
放課中、日差しがあって、外で運動をすれば、子どもたちは薄着でも平気かもしれません。でも、この時期、自分で服装を調節する力が不足していると、かぜをひきやすくなります。
子どもたちには、明日の学芸会前日、そして学芸会の2日間を健康で、けが無く過ごしてほしいと思います。いつも以上に、体調管理をしてください。
また、学芸会の鑑賞には、ご観覧いただく方々にもマスクをご準備いただければ幸いです。体育館は、とても寒くなります。照明の関係で、ギャラリーのカーテンをひいて暗くするからです。当日の天候にもよりますが、体温調節ができるようにご準備をよろしくお願いします。
久しぶりに朝会を行いました。
名古屋市教育委員会児童表彰、赤い羽根共同募金と明るい選挙の作品表彰をしました。表彰された子どもたち一人一人に、これからも進んで取り組んでほしいという願いを込めて、声をかけました。すると、私の目を見て、はいと答えたり、しっかりうなずいたりしてくれる子どもたちがほとんどでした。表彰された子どもたちにとって、「自分大好き」に思える時間となったのではないかと思います。
その後、今週は、いよいよ学芸会を迎えますので、次のような話をしました。
1 手洗い・うがい・十分な睡眠・バランスのよい食事に気を付け、ベストコンディション で、学芸会を迎えましょう。
2 学芸会に向けて、自分の役割を落ち着いて果たしましょう。もしも、困ったことが起きた場合は、早めに周りの人に伝えたり、周りの人が手伝ってあげたりしましょう。
3 学芸会のことだけでなく、今やるべきことをいつも一生懸命やりましょう。
3の話をする時、昨日、11月10日(日)にディスクドッヂ愛知県大会へ出かけたことを話しました。試合を応援していて、今まで気付かなかった子どもたちのいろいろな姿がみえてきました。そんな子どもたちの姿を見ていて、学芸会に一生懸命になることはとても大切ですが、気持ちや時間を切り替えて、生活することも大切だと思いました。
ちなみに、ディスクドッヂ愛知県大会では、低学年の部は優勝。高学年の部は、準優勝の成績をおさめました。
素晴らしい子どもたちが、たくさんいます。
10時から生活科室で、家庭教育セミナーの講師をしました。
今日のねらいは、2点あります。
1点目は、参加してくださる保護者の方々に、苗代小学校のグランドデザインを少しでも身近に思っていただき、苗代小学校の目指す学校づくりを理解していただけるようにすることです。
2点目は、私の子育て経験を通して私のことを知っていただくとともに、学校づくりや苗代小学校の子どもたちへの思いを理解していただくことです。
参加者は、31名でした。その方々に、クイズ形式にした6問の問いに答えていただきました。その後、「愛のあふれる学校づくり」のキャッチフレーズである「自分大好き 友達大好き 学校大好き」について、説明したり、学校づくりで大切にしていることを話したりしていきました。私の子育て経験の話では、いつも周りの人に支えられてきたことに感謝していることを伝えました。
次に、会の始めにBGMで流した「Believe」の曲を歌いました。皆さんのおかげで、気持ちよく声を出して、歌うことができました。最後に、参加者全員でも、歌いました。私は、今後、この曲を聴いたり歌ったりする時に、今日の家庭教育セミナーのことを思い出すことでしょう。
貴重な機会をいただけたことに、心から感謝しています。そして、私にとっては、あっという間の楽しい1時間でした。ありがとうございました。
学芸会当日通りに、リハーサルをしました。
どの学年も、子どもたちのせりふが、生き生きとして、自分の役への気持ちが、高まってきているのを感じました。歌も、声が良く出ています。
せりふや歌にのせる動きも、ずいぶん自然になってきていました。
私は、いつ学芸会を迎えても大丈夫のように思いました。
あとは、本番当日まで、一人一人が、自分の体調をベストに保ち、落ち着いて自分の役割を果たすためにどうしたらよいかを実行することです。
お時間が許す限り、ぜひ、どの学年の劇もご覧頂けたらと思います。体育館が、超満員になることを期待しています。
正門を入ると、「エーデルワイス」のリコーダーの響きがきこえてきました。こんなに、早い時間になんだろうと思っていると、児童会の子どもたちが募金運動のために準備をしているようです。それでも、よく分からないと思っていると、児童会担当の先生が、「みんなのエーデルワイスの曲をきいたら、きっとやさしい気持ちになるよ。」と話していました。「募金活動にご協力をお願いします。」という言葉だけでなく、みんなにもやさしい気持ちを届けようと児童会の子どもたちがアイデアを出したそうです。
素敵な取り組みに、私も正門で一緒にリコーダーを吹きたくなりました。「エーデルワイス」のもつやさしい曲の雰囲気を生かして演奏することで、登校してくる子どもたちの笑顔をたくさん見ることができました。募金活動は、明日も続きます。
最近、教室から、子どもたちの歌声がよくきこえてきます。学芸会の影響が大きいとは思いますが、歌の大好きな私にとっては、歌声のきこえる学校をとてもうれしく感じています。
歌声を聞くと、子どもたちの歌っている様子が、手にとるように思い浮かびます。そして、その歌声が、どんどん素敵になってくるのは、うれしいものです。
① 一生懸命大きな声を出そうと、のどに力を入れた歌声から、のどの奥を開けて楽に声が出るようになる。
② 息つぎを短く速くして、出だしの言葉がはっきりきこえるようになる。
③ 真面目な表情から、笑顔で歌って響きが明るくなる。
などという姿です。
私の声帯は、いつも一緒に響いています。
今朝、門でPTAの方々とハロウィーンの扮装をした子どもたちが、あいさつ運動をしました。私も、正門で、元気な子どもたちの声と、PTAの方々の笑顔に迎えていただいたお陰で、さわやかな気分になりました。ありがとうございました。
新1年生の児童数は、今日現在148名です。
その子どもたち一人一人に、5年生の子どもたちが、受付のある体育館から付き添ったり、各会場で役割を果たしたりしてくれました。5年生の子どもたちは、新1年生の子どもたちが、不安にならないようにとても緊張しながら、一生懸命心配りをして責任を果たしてくれました。
各会場をまわり、5年生の子どもたちの頑張る姿を見ることができて、とても笑顔がこぼれてきました。5年生の子どもたちの一生懸命さや一途な気持ちを感じ、心が動かされたからです。
本校では、次年度を見据え、6年生ではなく5年生の子どもに就学時健診の仕事をしてもらっています。いわば、来年入学してくる新1年生と新6年生の出会いの機会です。
5年生の子どもたちが、あと半年で最高学年になるんだという気持ちを高める機会となったのではないかと思います。
5年生の皆さん、ありがとう。お疲れ様でした。
今日もペンギン歩道橋で、交通当番をしました。子どもたちの服装に目を向けました。朝と夕方の寒暖の差があるので、半袖の子どもから厚い生地の上着の子どもまでいろいろです。また、急に寒い日があったせいなのか、学芸会で声をよく出すせいなのか、マスクをしている子どもが増えました。
子どもたちは、学芸会の練習に一生懸命です。いつも以上に声を出し、歌い、劇の音楽を聴いています。
そんな日が、学芸会が終わるまで、まだ続きます。
ぜひ、手洗い、うがい、熟睡、バランスの良い食事、適度な運動をしてほしいと思います。ご家庭でのご協力をよろしくお願いいたします。
先日、学芸会の案内を配付させていただきましたが、リコーダー部の出演(12:25〜)について明記されておりませんでした。後日、学芸会の確認事項、保護者アンケートとともに、再度配付させていただきます。ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげます。
4時間目に、3年生と音楽の授業をしました。
「気持ちをそろえて(表現しよう)」というテーマです。
はじめに、クラッピング(手拍子)を主役にした曲を二部で表現しました。始めのかけ声(ワン トゥー ワントゥースリーフォー)を進んで掛けてくれる子どもが、予想以上にたくさんいました。意欲のある姿を見ることができて、うれしかったです。ピアノの伴奏にのって、子どもたちのクラッピング(手拍子)の軽い音がうまくそろって、浮き浮きしてきました。子どもたちも、にこにこ笑顔でした。
その後、3年生の劇(最後の場面)で歌う、「バイバイ ボサノヴァンバ」を聴かせてもらいました。高い音は、眉毛を上に上げ、口の奥を開けて歌いました。練習する中で、のどを締め付けて歌う子どもが、少し減りました。
この学級でも、歌うことが好きな子どもたちをたくさん見付けることができました。
一緒に授業ができて、幸せです。
劇団 うりんこの西尾栄儀先生をお招きして、学芸会の演劇指導をしていただきました。各学年の持ち時間は、それぞれ40分。劇を発表し、その後、子どもたちへの全体指導、最後に職員への指導という流れで行いました。
全学年を通して、ご指導いただいた内容を大まかにお知らせします。
・ せりふを言っている人を見て、そのせりふをしっかり聴こう。
・ せりふの声は、パワーを込めて、お腹から声を出そう。
・ せりふは、誰に、何を伝えるために言うのかをじっくり考えて言おう。
・ 動きは、せりふを誰に何を伝えるために言うのかを考えれば、自然についてくる。
・ せりふに気持ちをのせるためには、間、声の強さや速さを工夫することが大切。
西尾先生は、各学年の子どもたちの演技のよさをたくさんほめてくださいました。そして、具体的に演じてみせながら、子どもたちにご指導くださいました。演技の違いを示してくださるので、とても分かりやすい指導でした。最後に、「演技は急にはうまくなるものではないと思う。だから、せりふを言う相手や劇をみている人を思い、誰に何を伝えたいかを考え、どういうせりふの言い方や動きをすれば、伝えたいことがうまく伝わるかを何度も繰り返し練習して、みんなの力を合わせよう。」と話してくださいました。
子どもたちには、今日の演技に自信をもって、でもまだ、学芸会本番までには日数があるから、みんなの演技力を少しずつさらに高め合いながら、劇をつくりあげてほしいと思います。
台風の心配はどこえやら。今日は、とてもよい天気に恵まれました。
昨年度よりも、子どもたちの参加が増えたと、多くの方々からお聞きして、とてもうれしく思いました。第3回を迎えたこのイベントに参加して、学区のチームワークのよさをあらためて強く感じました。
全てのブースを見学したり、スタッフの方とお話をしたりしながら、もしも、この苗代小学校が避難所になったらと考えていました。どこに防災トイレを設置して、どこから水をとり、ゴミの集積場所や重傷なけが人や病人をどこに等。
一人でも多くの学区の方々と、お近づきになりたいなと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
リコーダー部の子どもたちは、素敵な演奏を披露してくれました。演奏の機会をいただき、ありがとうございました。
以前、朝の運動で大縄跳びをしているとお伝えしました。
今日も、6年生は、1年生がうまく跳ぶことができるように、細やかに、そしてやさしくアドバイスをしている場面を何度も見ました。そのおかげで、跳べた時の1年生の笑顔も素敵でしたが、他学年の子どもも1年生に負けられないと、真剣な表情で跳ぶ様子が持続できていて素晴らしいと思いました。
3時間目には、6年生と音楽の授業をしました。
「歌を通して、仲間について考えよう」というテーマです。
「語り合おう」の曲では、歌詞にあるように隣の子と向かい合い、見つめ合って歌ったり、どんな仲間を思い浮かべて歌ったかをインタビューしたりしました。「ほほえみが 今 よみがえる やさしさが」のところで、歌を聴いた人が、「やさしさ」を感じとれる歌い方を練習しました。子どもたちの歌声は、なめらかにつないで歌い、張りのある声で、曲の山を感じ取ることもできました。
最後に、学芸会の最後の台詞を入れて、「すてきな友達」を歌いました。伴奏を弾きながら、アップライトのピアノの黒い部分が、鏡のように子どもたちの表情をうつしてくれました。
歌声だけでなく、口の開け方や、身体がゆれている様子などがうつり、 「歌うことの大好きな子どもたちが、たくさんいてとてもうれしいなと思いました。
また、一緒に歌う機会をつくりたいものです。
今日、3年生の子どもたちが、台風27号に備えて、苗代ガーデンに置いてあるパンジーの苗ポットを1年4組の階段付近に移動してくれました。苗は、適度の水分や太陽とは仲良しですが、大雨や強風は大の苦手だからです。
やさしい子どもたちです。
今日は、一日中、とてもお客様の多い日でした。
いつものように、放課にも、窓を「コンコン」とノックしてくれる子どもたちもいましたが、「お客様だから、ごめんなさい。」と言わなくてはなりませんでした。
子どもたちとおしゃべりする時間がなくて、物足りない日となりました。でも、あるお客様が、「人気者ですね。」と言ってくださいました。
私にとって、子どもたちとふれあえる幸せをあらためて感じる日となりました。
| 10月22日(火) 3年 パンジーの苗ポットづくり 5年 脱穀 |
午前中は、緑の協会と、守山土木事務所の方々が、ゲストティーチャーとしてお越しくださいました。ポットに土を入れ、3年生の子どもたちが種から育てたパンジーの苗を入れました。一人で30個のポットを作ってくれた子どももいました。
午後は、学区の岡田様にお越しいただき、5年生の子どもたちと一緒に脱穀をしていただきました。30キロの袋に約3袋になりました。精米をして、何キロのお米が収穫できるか楽しみです。
朝会で、まず二人の図書館大使の発表、「歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール」入賞の表彰を行いました。
その後、「愛ポスト」の手紙について説明し、先週の2日間に届いた手紙を本人の許可を得て読みました。それぞれの手紙には、「自分大好きになったこと、友達大好きになったこと、学校大好きになったこと」が書かれています。これからも、自分や友達のよさを見付けたり、そのよさを伸ばしたりしてほしいと伝えました。
私は、「人には、必ずその人なりのよさがある」と信じているからです。
みんなで、お互いのよさを見付け合いましょう。
| 10月18日(金) 「なえしろ あそぼう祭」の打ち合わせ |
10月27日(日)に行われる「なえしろ あそぼう祭」の打ち合わせのために、「苗代消防団」の方が2名、来校されました。当日は、放水訓練をしていただけるそうです。結局プールから水を取り、バックネット付近に放水することになりました。
消防団の方々が、きびきびと号令を掛けたり、その号令に合わせて短時間にてきぱきと動かれる様子を見せていただけたりすることでしょう。緊急時に備え、訓練をしてみえます。皆さんで、大きな拍手を送りましょう。
5年3組と4組が、苗代ガーデンの稲刈りをしました。台風のせいか、田には水がまだ残っていました。稲刈りには、長靴が最適です。
子どもたちは交替で鎌を使って稲を刈り、わらで稲の束をつくりました。そして、フェンスに干していきました。
子どもたちは、私の予想以上に、うまく鎌を使うことができていました。でも、わらで稲の束をしばるのは、大変そうで、四苦八苦していました。明日は、1組と2組が稲刈りをします。

久しぶりに、ひまわり組の3学級と1年生の4学級の廊下や教室に出かけ、授業の様子を参観しました。学芸会の練習が始まり、Bチャイム4時間授業ですが、子どもたちは大変落ち着いて学習していました。安心しました。
ある学級で、友達へ手紙を書いて、学級内のポストに入れる取り組みをしていることを知りました。その時、「校長先生にもお手紙を書くね。」と伝えてくれる子どもがいました。「うれしいわ。じゃあ、先生もポストをつくるね。」と答え、すぐに空き箱でポストをつくりました。
そのポストの名は、「愛ポスト」です。
苗代小学校のグランドデザインのテーマは、「愛のあふれる学校づくり」です。ですから、「愛ポスト」としました。そして、ポストには、「私に伝えたいこと、みんなが笑顔になったこと、自分大好きになったこと、友達大好きになったこと、学校大好きになったことがあったら、お手紙を入れてください。」と書きました。
下校時、正門前の横断歩道で、できあがったポストを見せながら、「明日から、お手紙を受付けます。」と、子どもたちに知らせました。
「お返事もらえますか?」と、尋ねる子どももいました。
明日から、楽しみです。
学年・組・名前を忘れずに書いてくれれば、お返事を出すこともできますね。
職員室前の廊下に置きました。(写真 参照)
今も、台風の吹き返しの風が、強く吹いています。個人懇談会の往復に、けがのないよう気を付けていただければと思います。

今日から個人懇談会が始まりました。ただ、台風26号の接近により、暴風警報がいつ発令されるかもわかりません。下校後の子どもたちの時間の過ごし方も心配です。外にでかける場合は、行き先や帰宅時間、誰と一緒なのか等、しっかり保護者の方に伝えてでかけるようにしてほしいと思っています。また、明日も、台風情報に注意が必要です。ご家庭でのご指導も、よろしくお願いします。
さて、先日、こんなお電話を頂戴しました。
「マンション敷地内の通路で、自転車でレースのような遊びをしている小学生がいた。通行する方と接触して大変危険であった。」という場面を見かけたというものです。
遊び場所が限られているのは分かりますが、自分や学区の方がけがをしてからでは大変です。
周りの方々の迷惑にならないよう、自分もけがをしないよう、自分で考えて正しく行動できるようにしたいものです。
これまでにも、学区の方々は、指導してくださっていると聞いていますが、安全に注意できる子どもでいてほしいと思いました。くれぐれも気を付けましょう。
日差しは少し暑い日でしたが、心地よい風も吹き、とんぼが大会を応援するかのように運動場で飛んでいました。
私は、あいさつの中で、子どもたちと一緒に、「ファイト、ファイト、がんばろう!」と声を出して、大会を楽しんでほしいという気持ちを伝えました。
今日の子どもたちの参加者は、180名と聞きました。
そして、子どもたちのために、これまで子供会の方々をはじめ、多くの保護者や学区の方々が大会を支えてくださったことに大変感謝しています。
もちろん、大会ですから勝負の結果はとても気になります。でも、試合の中でチームの仲間に声をかけ励ましたり、応援してくださる方とのふれあいの場面が合ったりすることは、子どもたちにとって、とても貴重なことです。本当に、有り難いことです。今後とも、苗代の子どもたちをどうぞよろしくお願いします。
今、朝の運動は、大縄跳びをしています。
6年生が大縄をまわし、同じグループの子どもたちが2人組で一緒に跳びます。ペアの2人の子どもたちが息を合わせるために、縄の動きに合わせて首を揺らして、一生懸命跳んでいました。6年生がペアの1年生にやさしく接していたり、縄を跳んだ1年生がにこにこ笑顔だったりしている姿に、私は、ほんわかした気分になりました。
明日は、運動場でキックベース大会が開催されると聞いています。参加する子どもたちが、怪我がなくゲームを楽しんでくれるとうれしいと思います。
| 10月10日(木) トワイライトスクール臨時運営連絡会 |
13:00から、トワイライトスクール臨時運営連絡会が開かれました。
6月から9月までの平均参加者数や、学年水泳出校日のトワイライト参加者数が、最高105名もいた日があったことをお聞きし、とても驚きました。
また、より安全な下校を確保するという観点から、3年生以上の児童が、児童のみで下校する時間(保護者のお迎え無しで下校する時間)について協議しました。原則、暗くなる前に自宅に到着できる時間と考えています。
詳細は、トワイライトだよりで、お知らせがあるそうです。
明日は、3連休前の金曜日です。そして、来週15日(火)からは個人懇談会が始まります。子どもたちが、授業後の時間を有意義に過ごしてくれることを願っています。家族や自分のために、友達とのよいつながりを深めるために何ができるかを考え実行してほしいと思っています。
| 10月9日(水) 2年、ひまわり2組(2年) 「城山公園に行こう」 |
今日、2年生の子どもたちが、「城山公園に行こう」をテーマに校外学習にでかけました。出発ぎりぎりまで、天気が心配でしたが、城山公園だけでなく、タワーも見学させていただくことができたと、喜んで帰ってきました。
学校の方では、大放課途中からたくさんの雨が降ってきたので、子どもたちがずぶ濡れにならなかったかと気がかりでした。でも、タワーの見学中で濡れなかったと知って安心をしました。よかったです。
予定時刻よりも15分遅れで、学校に到着しました。
今回の修学旅行では、在籍151名中、1名の欠席は大変残念でしたが、学校に無事到着できて、大変ほっとしています。
子どもたちが、素直で、とても子どもらしく修学旅行を楽しんでいる様子を見るのはとてもうれしく思いました。反面、最高学年としては、卒業までの約半年間での課題が、いろいろな場面で浮かんできました。そして、その課題の一つ一つをこれからも素敵な子どもたちの行動力と意欲を核として、学年全体としての成長として高めて行ってほしいと思いました。
修学旅行で学んだことを、これからどのように生かしていくのかが、重要だと強く感じています。
学校に戻った時のあいさつで、今日の座禅体験での話をもとに、「今日から、今から」を大切に、子どもたちとみんなで一緒に頑張ろうと話しました。
何とか修学旅行を無事に終えることができ、心より感謝しています。
7日(月)〜8日(火)は、6年生、ひまわり3組の子どもたちと修学旅行にでかけます。
安全第1。そして、今日まで準備してきたことが、しっかりと発揮できて、楽しい思い出となるよう、元気にでかけます。
学校にいる子どもたちも、元気に過ごしましょう。そして、皆様、どうぞよろしくお願いします。
9月25日(水)1年1組、2年1組の授業をスタートに、全学級の研究授業を職員に公開しています。
本校の努力点研究の主題は、「言語活動の充実によるコミュニケーション能力の育成」です。
そこで、授業の中では、自分の思いや考えを言葉で、分かりやすくはっきりと話したり話す相手を意識して表情や声を工夫したりして話す子どもをめざしています。また、じっくりと最後まで話を聴いたり、感想や意見を伝えたりできる子どもをめざしています。そうすれば、よりよい人間関係を築き合う力であるコミュニケーション能力が育つと考えています。
そのために、いろいろな教科や・領域で、発表や話し合い等の活動を行い、子どもたちが、分かりやすく伝える方法を身に付けたり、話し方を工夫したりして、日々の生活にも生かしたりできるように授業づくりを進めています。
話し方名人や聴き方(聞き方)名人が、どんどん増えていくような授業づくりをしているところです。
ご家庭でも、子どもたちが。話し方名人や聴き方(聞き方)名人になれるよう、これからもご協力をお願いいたします。
1・2時限に、4年生の子どもたちと一緒に、「矢田川クリーン大作戦」に参加しました。 このクリーン大作戦は、6月6日(木)に続いて、2回目です。
ごみは、予想以上に少なかったので、私は草取りを中心にしました。
子どもたちは、「えっ、草でもいの?」と尋ねてきたので、「だって、野球部やサッカー部がいつもここへ練習にきてるでしょう。草にひっかかってつまずいたり、イレギュラーバウンドしてボールがとれなかったりしたら、かわいそうだよね。」と話すと、「そうか!」と言って、大勢の子どもが草取りもしてくれました。
ある野球部の子どもは、「練習の前に、草取りしている。みんなが、喜ぶよ。」とも、話してくれました。
しばらくすると、学区の方々の姿が、堤防の西の方からたくさん見えてきました。学区の方々も、クリーン大作戦に取り組んでくださっていたからです。子どもたちとあいさつを交わしながら、清掃をしてくださる方がいらっしゃって、素敵だなと思いました。学区の方々とふれあうよい機会ともなりました。学区の素晴らしさを感じました。本当に有り難いことです。
 
10月23日(水)に苗代ガーデンの稲の脱穀をすることになりました。今日の夕方に、脱穀をしてくださる 学区の岡田様が、打ち合わせに来てくださいました。
5年生とひまわり1組の先生方で話し合いをしました。脱穀までに、子どもたちと一緒にやっておくこと、前日や当日にたくさん雨が降っていると23日ではなく、25日(金)に延期すること等を打ち合わせしました。
いよいよ稲刈りの日が、近づきました。楽しみです。
今日から、10月です。衣替えの季節です。
昨日、歩道橋で交通安全の見守りをしている時に、守山東中の生徒が、長袖の制服で登校するのを見かけました。
天気予報では、まだまだ暑い日もありそうです。子どもたちが衣服の調節ができるように工夫して、体調管理にくれぐれも気を付けてほしいと声を掛けています。特に、6年生は、来週月曜から修学旅行です。ご家庭でもご協力をよろしくお願いします。
さて、今日3・4限は1・2・5年生が、5・6限は3・4・6年生が芸術鑑賞会をしました。演目は、劇団うりんこの「ぼくってヒーロー?」です。心の弱い少年が、変身ベルトをもらったことがきっかけで、失敗を繰り返しながらも、少しずつ成長していきます。そして、自分の心を強くして行くには、今自分にできることをこつこつと一生懸命続けていくことが最も大切だと教えてくれる、観た人の心に残る素敵な劇だと思いました。
劇が終わった後、子どもたちは、私に、「楽しかった。」「おもしろかった。」「私、涙が出ちゃった校長先生は泣きましたか?」等と感想を伝えてくれました。
今年は。創立40周年記念として、観劇会の費用は、マイスクールプランとPTA会費からの補助を受けて実施しています。(個人負担は必要ありません。)
今日は、久しぶりの朝会でした。後期の児童会役員、学級委員、各種委員会委員長の認証式、リコーダー部の表彰を行いました。
認証式後には、認証された子どもたちだけでなく苗代小みんなの協力が無ければ、スムーズに仕事はできないことを伝え、みんなで協力してがんばりましょうと話しました。
また、リコーダー部の表彰後には、守山区小中学校連合音楽会での素敵な演奏のように、「なえしろあそぼう祭」に向けて、練習に力を合わせてがんばりましょうと話しました。
最後に、9月の授業参観アンケートで、保護者の大勢の方々がほめてくださった内容と、「全員がはっきりとした大きな声で発言や発表をしよう、背中が丸くならないように姿勢に気を付けよう、これからもいつも進んで授業に参加しよう」と話しました。
昨日と今日の2日間、3年生と一緒に教室掃除をする機会がありました。
子どもたちは、自分の担当の仕事を黙々とやっていました。感心しました。
子どもたちだけでは心配ですが、私も手伝えるので、いつもは動かさない台、教師用の机、オルガンも動かして、床をきれいにしました。
子どもたちの机と椅子を運ぶ時に、鉛筆、のり、ハンカチが、落ちてきました。机の中は、きちんと整理していても道具箱や教科書等の学習用具でいつもいっぱいです。ですから、慌てて片付ければ、うまく片付けられないこともあります。
私は、担任をしているころ、子どもたちに、「整理・整とん・清潔・清掃が、成績アップの一番の近道」と話し、落ち着いて学習する上での環境づくりに気を付けていたことを思い出しました。ご家庭でも、時間を有効に使って学習する上で、大切なことではないでしょうか。
私の身の回りも、いつもすっきりと整理・整とんできているように、心がけます。
守山東中学校の体育大会から学校に戻ると、大放課でした。それで、運動場で久しぶりに子どもたちの遊ぶ様子を見ることにしました。
どの子どもたちも楽しそうにしていて、元気いっぱいにしていました。
そのうちに、4年生の子どもたちが8の字跳びをしているのが目にとまりました。縄をまわす子どもはどの子どもも一生懸命まわしているのですが、縄が長すぎてたるんでしまっているのです。そのため、タイミングをとるのが難しいのか、子どもたちは、すぐにひっかかっているのです。ついつい、声をかけたくなって、私も一緒に縄をまわす役をやりました。はじめは、30回を跳ぶことも難しかったのですが、3限と4限の放課には、担任の先生の協力もあって、150回も跳ぶことができました。縄を跳ぶたびに、子どもたちの笑顔を見ることができて、楽しい時間を過ごせました。
4年生の子どもたちが、8の字跳びの楽しさを味わえたなら、うれしいです。
今日も、いろいろなお客様をお迎えしました。
○ PTA地域ふれあい実践講座 (10:50〜12:00)
子どもたちに豊かな体験活動を①〜身近なものでビックリ!科学実験&工作〜
講師 かがくのひろば主宰 小 林 順 子 氏 他1名
保護者の方々といっしょに、3種類の作品づくりをしました。2メートル近くも飛んでいくストローロケット、全員が皿を回し続けることができた喜びを味わった紙皿の皿回し、和紙を細かく折って彩色してできたきれいな模様の染め抜き。
お二人の講師の先生方の笑顔に包まれ、素敵な作品づくりや、それを使った遊びができました。とても楽しい時間となりました。
○ 修学旅行事前検診 (13:30〜14:50)
学校医 浅 川 順 一 氏
いよいよ、修学旅行が目前となりました。学年や学級での準備は着々と進んでいるようです。とはいっても健康が一番。みんなが、元気で、参加できることを願っていま す。
学校医の浅川先生、検診をしていただき、ありがとうございました。
6年生の子どもたちは、検診が済んだといっても油断をせず健康管理に努めましょう。 今日の検診に欠席だった子どもたちは、早めの受診をお願いします。
○ 4年 環境教育講演会 (13:45〜14:30)
講師 動物写真家 小 原 玲 氏
小原氏の話をじっくり聴いている4年生の姿を見て、とても感心しました。質問をする子どももたくさんいました。また、小原氏のご家族が、ゴマフアザラシとふれあった時のお話をお聞きしたり、かわいらしい写真も見せていただいたりしました。そのような講演会の中で、子どもたちの笑顔をたくさん見ることができました。
そして、小原氏が、地球上の人々が努力しなければ地球温暖化はとまらないこと、自然を好きになることの大切さ、自然が喜ぶだろうと思うことをやり続けることの大切さを語ってくださった時の子どもたちの真剣な表情が、素敵でした。
私は、小原氏に、来年度も、子どもたちのために講演をしていただきたいと強く思いました。
○ 守山土木事務所 大 澤 由 希 氏 (13:00〜13:45)
守山区民まつりで配付される「守山土木だより」に、3年の総合的な学習 「みどりいっぱい 生き物いっぱい」の授業(9月10日実施)で、3年生がパンジーの種まきをした様子を掲載していただけることになりました。
3年生の先生と一緒に原稿を見せていただいた後、大澤氏が、種まきした後のパンジーの成長の様子を見てくださいました。先日の台風の時には、3年の先生方がパンジーを心配して見に来てくださったと聞いています。
小幡駅前に、パンジーが美しく咲くように3年生はがんばっています。
今朝も、「元気、さわやかさ、笑顔」のあいさつを子どもたちとかわすことが、できましたか?
休日や連休あけの登校指導で、子どもたちとあいさつを交わしていると、いつも以上に子どもたちの様子がよく分かる気がします。
私は、自分から「おはようございます。」と、できる限り、声をかけるようにしています。そんなとき、私の目を見て、よくとおる声であいさつを返してくれる子どもから、とても元気のでるパワーをもらいます。下や前を向いたままで、あいさつを返す子どもには、私の今日のあいさつでは、「元気、さわやかさ、笑顔」が、その子どもの心にうまく届かなかったのかなと思います。聞こえないようなかぼそい声であいさつを返す子どもには、何かあったのかなと気に掛かり、「大丈夫?」と声をかけたり、やさしく笑顔を返したりします。そして、そんなときこそ、学級では、友達の意見や話を聴くだけでなく、自分の意見や考えをみんなに伝えてほしいと思ったりもしています。また、体育館通路の階段に座り込んで休んでいく子どもたちには、「少し休んだら教室へ行こうね。」と促したり、話したいことがあれば話のできるきっかけづくりもしています。
そんなささいな関わりの積み重ねが、とても大切だと思っているからです。
子どもたちには、いつでも、だれかが見守っていてくれているという安心感をもち続けていることが特に必要です。ですから、子どもたち同志も、意見や考えは違っても、互いに大切に思っていることを伝え合ってほしいと思います。そうすれば、だれもが、子どもたちが、保護者や私たちを必要とするときにSOSを発することのできる存在でいられると思っているからです。
子どもとどう関わるのか、見守るだけでよいのかは、一人一人の子どもによって違う場合が、多くあります。でも、その子どもを大切に思っている気持ちに、違いはありません。その気持ちは、これからもしっかりと伝えていきたいと思います。
人は、自分の力で、何をなすべきかを考え、正しく行動しようとします。でも一人でできることは、ほんの少しかもしれません。
| 9月20日(金) 交通安全の取り組み と あいさつ |
今日は、20日のゼロの日です。朝の登校指導は、歩道橋の場所で行いました。
いつものように学区や保護者の方々が、大勢立ってくださいました。
そして、守山区長の山田様をはじめ、守山警察署の方々も来てくださいました。
子どもたちの朝のあいさつは、はっきりとよく聞こえる声でした。でも、歩道橋の階段のせいか、相手の目を見て笑顔で言える子どもは、正門の所のあいさつに比べて少なかったです。
あいさつをする時、あいさつをする相手に、「元気とさわやかさ」、そして、「笑顔」を伝えてほしいと、いつも思っています。私も、子どもたちと一緒に、そんなあいさつが自然にできる学校であってほしいと願っています。
明日から三連休。
ご家庭でも、お休みだからこそ、「元気、さわやかさ、笑顔」のあいさつを子どもたちとなさっては如何でしょう?
昨日の午後は、先生方の出張が重なり、私も5・6限に4年生の2学級で音楽の授業をすることができました。苗代小学校では、初めての機会でした。朝から、子どもたちと授業するのが、とても楽しみでした。
1学級は、指揮をしながら歌唱をし、声を遠くに響かせたり高い声を楽に出したりする学習をしました。もう1学級は、リコーダーの二部合奏で、お互いのパートの音を聴いて演奏したり、音がだんだん高くなっていく部分をだんだん強く歌う歌い方を練習したりしました。
どちらの学級も、のどの奥をあけて遠くに響かせたり、にこにこ笑顔で歌ったりすることが、とても上手にできていました。練習をする中で、私の歌い方の真似のできる子どもがたくさんいて、感心しました。子どもたちの反応が、とても素直で、楽しく授業ができました。幸せな気分でいっぱいにいなりました。
保護者の皆様、2・3限の授業参観には、多数ご参観をいただきありがとうございました。今日の授業参観について、9月3日付で配付しました「9月授業参観のお知らせ」裏面の保護者アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。
さて、子どもたちや職員の頑張りを今日は、学校評議員の方々にもご覧いただきました。学校評議員とは、保護者や地域の方々のご意見を幅広くお聞きする立場の方のことです。本校は5名の方がいらっしゃいます。
その学校評議員会では、学校経営方針のグランドデザインや、具体的な取り組みについてご説明し、授業の参観をしたり給食も召し上がっていただいたりもしました。また授業参観で校内を歩いていただきながら、施設・設備の状況についても見ていただきました。
学校評議員の方々からは、言語活動の充実に重点をおいて取り組み、コミュニケーション能力の育成をめざしているという方向性についてご理解をいただきました。そして、学校評議員の方々とお話をしていく中で、今後も、学区や保護者から信頼を得るためには、「開かれた学校」であり続けることが最も大切だとあらためて強く感じました。
今後ともご指導のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。
| 9月17日(火) 守山区小・中学校連合音楽会 と 東階段の補修工事 |
9月13日(金)、守山区小・中学校連合音楽会が、名古屋市教育センターで開催されました。苗代小学校は、リコーダー部の子どもたちが練習の成果を発表しました。
アラジンの「ホール・ニュー・ワールド」を演奏しました。演奏する始まりの姿勢がピシッと決まっていました。その姿勢とは相反して、リコーダーから流れてくる音色はとてもやわらかい響きで、曲の山を意識した素敵な演奏でした。
音楽会最後の講評でも話しましたが、これからも音楽に魅力を感じ、友達と音楽をつくる楽しさや、ハーモニーを味わう喜びを感じることができるように、子どもたちには、ずっと音楽が好きでいてほしいと願っています。
守山区の音楽顧問校長として、一日中、素敵な演奏を聴くことができた幸せに、感謝します。
台風18号の影響は、如何でしたか?
学校は、15日(日)夕方〜16日(月)まで、非常配備となりました。
実は、14日(土)〜16日(月)の連休中に、東階段(1階〜3階)とその付近のフローリング張り替えの補修工事をしていただきました。
明日の授業参観等で、ご覧いただければと思います。
フローリングが薄くなり、コンクリートが透けて見えるようになっていた危険な箇所が、きれいに安全になりました。でも、これまで通り、落ち着いた歩行に気をつけてほしいと思います。

昨日、学校保健委員会を開きました。
まず、定期健康診断結果等の報告をしました。
次に、学校医・歯科医・眼科医・薬剤師の先生方が、PTAや職員からの質問に対してていねいに答えてくださいました。
1時間という限られた時間でしたが、大変有意義な時間となりました。
ご指導ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
また、PTAの方々、ご出席をいただきありがとうございました。
9月12日(木)
気持ちを伝える話し方・相手の話したいことをやさしく受け止める話の聴き方 |
2学期が始まって、10日が過ぎました。子どもたち全体の雰囲気は、とても落ち着いています。放課は、暑くても外で元気よく遊ぶ子どもたちがたくさんいます。また、3年生以上は、一輪車も使用できるようになり、楽しんでくれています。
しかし、一人一人に目を向けると、まだまだ夏休みの気分が残っているせいか、暑いせいなのか、友達との会話で言葉が乱暴になりすぎたり、相手からすぐに目をそらして話したり聴いたりする子どもの姿をよく見かけます。
毎日の学校生活の中では、ほんの少しの気持ちの行き違いから始まるトラブルがあります。「そんなつもりじゃないよ。」とすぐに伝えられる子どももいますが、黙ってしまう子どももいます。
ですから、いつも話す相手の目をじっと見て、落ち着いてゆっくりと、気持ちを伝える話し方をしてほしいと思っています。
また、私は、話を聴くことよりも話すことに時間をかける傾向があり、反省することがよくあります。
ですから、これからも、子どもたちの話したい、聴いてほしいという姿を大切にして、子どもたちに笑顔で接し、会話を楽しみたいと思います。
清掃中に避難訓練をしました。子どもたちは、それぞれの清掃場所から避難し、いつものように、運動場の真ん中に集まりました。
各教室からの避難は、とても静かにできていました。
集合した後、次のことをポイントとして話しました。
・ 落下物がないかを確認し、頭を守って、姿勢を低くする。
・ 率先、避難をする。
・ 放送や先生たちの指示がよく聞こえるように、静かに避難する。
今日の避難訓練は、子どもたちと担任がそろって教室から避難するのではなく、子どもたちだけで避難する場所もありました。緊急時、自分たちで判断する場面を見据え、今後も、いろいろな方法で訓練をしていきたいと考えます。
| 9月10日(火) 4〜6年 お話会 と 3年 総合的な学習 |
4〜6年の読書タイムは、「宙の会」の方々に、「ごんぎつね」の読み聞かせをしていただきました。BGMの音楽にのって、スクリーンにはごんぎつねの挿絵が映し出され、ストーリーは進んでいきました。子どもたちは、静かに耳を傾けていました。
今年は、ごんぎつねの作者である「新美南吉」さんの生誕100年にあたる年です。各地で記念行事も開催されています。このお話会をきっかけに、新美南吉さんの他の作品を読んだり、読み聞かせに興味をもったりする子どもが増えるとうれしいなと思いました。
宙の会の皆さん、素敵な読み聞かせの会をしていただき、ありがとうございました。
2・3限に、3年の総合的な学習 「みどりいっぱい 生き物いっぱい」の授業で、守山土木事務所から5名、名古屋市みどりの協会から2名の方々に来ていただき、「パンジーの種のまき方」を教えていただきました。土を入れた「セルトレー」に、約1.5ミリの種をまき、種が乾燥しないように新聞紙をのせて、そっと水をまくという方法です。
その後、子どもたちは、各教室に戻って種まきをしたり、学んだことをプリントに記入したりしました。
授業が終わった後、応接室で、今日来てくださった先生方に、パンジーを上手に育てた体験談を聴かせていただきました。
1 水をやりすぎて、根が窒息しないようにする。
2 ふたばが、2〜3枚でてきたら、よく日の当たる場所に置く。
3 葉に、虫がついていないかをこまめに調べる。
子どもたちの種まきをしたパンジーが、元気に育つとうれしいです。
| 9月9日(月) リコーダー部の発表 と 整理・整頓 |
朝会の時間に、体育館でリコーダー部の発表を聴きました。
なめらかな曲の感じが、とてもうまく表現できていました。演奏を聴いた子どもたちや職員から、たくさんの拍手が起こりました。
演奏が終わった後、リコーダー部の子どもたちに、「演奏は、とても素敵でした。音楽会当日、ドキドキ緊張しても息を深く吸って、いつも通りに演奏できるようにしましょう。応援しています。」と伝えました。
1・2時間目に、体育館器具庫の整理・整頓をしました。
いろいろな用具が、とてもたくさんあります。子どもたちだけでなく、PTAや学区の方々が、使いやすいように、どこに何が入っているのかが見やすく、どこに片付けたらよいのかが分かりやすくしたいと考え、整理・整頓をしました。
道具は、片付ける場所をいつも同じにしておくことが大切です。
体育館を使う機会があれば、使い勝手について、ぜひ教えていただければと思います。また、表示も工夫したいと考えています。
整理・整頓をすることは、何よりも「安全」につながります。そして、出し入れの時間を短縮でき、活動の時間が有効に使えます。
今日の整理・整とんで、私の心はすっきりしました。
臨時校長会から帰ると、保健室廊下で、とても静かに身体測定の順番を待っている3年生の子どもたちをみかけました。保健室をのぞくと、中にいる子どもたちも、行儀よく身長と体重をはかっていました。
もう一度、私が廊下で待っている子どもたちの顔を見ていると、私に微笑んだり、手を振ってくれたりしてくれました。
臨時校長会での話を聴いて、「いじめはしない させない 見過ごさない」について、具体的に各学校での取り組みを今後も工夫すべきと強く感じてきただけに、子どもたちの素敵な姿をうれしく思いました。
昨日の大雨や雷の影響は、如何でしたか?
学校の方は、夕方運動場に約8㎝位水が上がりましたが、校舎への浸水はありませんでした。ほっとしています。
また、今朝の登校時や、朝の会で担任から被害についての聞き取りをしてもらいましたが、特に問題があったとは聞いていません。
ただ、職員は、交通機関がストップして帰宅困難になった方が数名と、道路の冠水の影響で、はらはらしながら運転したという方が大勢見えました。
とにかく、大変な1日となりました
9月に入り、学区の稲穂が、みるみる大きくなっているのに気付きます。
苗代ガーデンの稲穂も、それに負けず劣らず、8月下旬に入って、ぐーんと成長しました。写真を添付します。

昨日、リコーダー部の部活動練習を見学に行きました。
暑い教室の中で、パート練習に励んでいました。私は、自分のソプラノリコーダーを持って行ったので、ソプラノのパート練習の仲間に入れてもらいました。6年生の親切な子どもが、楽譜を見せてくれました。その楽譜には、「スラーやdim.」等の記号がきれいな色で強調されていました。今までの練習の足跡が、よく分かる記録が残っていて、素敵だなと思いました。
私もソプラノパートを一緒に演奏してみました。
子どもたちは、フレーズを大切にして身体をゆったりと揺らしたり、曲の山を意識して音を強くしたりして演奏していました。
13日(金)の守山区小中学校連合音楽会が楽しみです。
はじめに、6年生の保護者の皆様にあいさつをしました。
いつものように、「自分大好き 友達大好き 学校大好き」をめざしていることをまず伝えました。そして、子どもたちや職員の素敵な姿や頑張りをホームページでアピールしているが、どのくらいの方がご覧になっていらっしゃるかを知るために、保護者の皆様に挙手をしていただきました。私の予想以上に多くの方が見てくださっていることが、挙手をされる姿で分かって、とてもうれしく思いました。
ありがとうございます。
次に、修学旅行の引率者、天災(地震・津波・噴火)に対応する保険について話をしました。
他の先生方からは、レジュメにしたがって、パワーポイントも活用しながら、説明をしていただきました。
これまでの修学旅行に関わる子どもたちの姿や反応を交えて、ご説明をした部分は、特に分かりやすかったのではないかと思います。
子どもたちが元気で、安全に修学旅行を終えることができることが、一番大切です。
そして、修学旅行を通して、日本の伝統文化のよさにふれたり、仲間や先生方とのつながりを深めたりすることができれば、素晴らしいと思います。
ご支援・ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。
「自分大好き 友達大好き 学校大好き」をがんばるために、2学期は特に、「気持ちや理由を詳しく話しましょう。」と伝えました。その後、みんなが夏休み中にがんばったたり続けたりしたことについて尋ねました。たくさんの手が、さっと上がりました。特に感心したのは、学区や地域のイベントに参加している子どもが、予想以上にたくさんいたことです。
礼の仕方やタイミングが、バッチリ。起立している時の姿勢や態度もバッチリ。
2学期も、みんなと一緒に成長しようという「がんばろうパワー」が、わいてきました。
2名の転入生を迎え、うれしい始業式となりました。
今日も大勢の職員が出勤しました。
9月2日(月)の始業式に元気な笑顔で登校してくる子どもたちの姿を思い浮かべながら、きびきびと仕事をしてみえました。
2学期も、子どもたちや職員の素敵な姿をお知らせしていきます。ご支援・ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。
台風15号が発生しています。
夏季休業中、各地で大雨や土砂崩れ等の大きな被害に見舞われた地域のニュースが報道され、心が痛みました。
日ごろから、「避難グッズの点検や早めの避難」に心がけましょう。
また、9月2日(月)始業式をはじめ、緊急に対応しなければいけない場合は、緊急メール等でもお知らせをしますが、「『暴風警報発令』等の対応について」及び「『東海地震注意情報』が発表された場合の対応について」(平成25年4月23日付 配付)をご参照ください。よろしくお願いします。
今日の午後は、4・5年生の先生方が全員で、学芸会の準備を中心に、一生懸命取り組んで見えました。既に廊下には、衣装ケースがたくさん並んでいます。
子どもたちも、2学期の準備は始まっているのでしょうか?
健康に、安全に、そして、2学期の自分なりの目標に向かって準備を進めましょう。
演劇の研修会に参加しました。
相手(台詞を言う相手、演技する人全員、観客)を大切に思うことをベースに、演じる上でのポイントは、「集中・コミュニケーション・想像」と学びました。そして、台詞の大切さをワークショップで、実際にやってみて強く感じました。
やはり、子どもたちには、学芸会を通じて、演じる楽しさを一番に感じ取ってほしいです。そのためには、自分の台詞は、誰に、どんな目的で、何を伝えようとしているのかをたくさん考えて言って、演じてほしいと思います。そして、相手に伝えることのできた喜びを味わってほしいと思います。
学芸会は、コミュニケーション能力を育てる上で大変有効な手だてとなる行事だと、あらためて思います。
今日、「至福の時が流れる」と言われることで定評のある場所で、心地よいゆったりとした時間を過ごす機会がありました。
その場所で、接客する方々の素晴らしい立ち居振る舞いや、話し方に、同じ人として、とても魅力を感じました。
そして、同時に先週の21日(水)午後に、2つの研修会に参加したことを思い出しました。その時の一人目の講師は、子どもたちのための合唱曲をたくさん作曲された方で、二人目の講師は、望ましい人間関係をつくるために必要なマナーを教えてくださる方でした。
どちらも全く関連が無いように思われるかもしれませんが、私は、どちらも、「相手を大切に思う」という気持ちがとても重要だということを改めて学んだことを思い出したのです。
子どもたちと一緒に、「自分の思いを伝えることと、相手を大切に思うことのバランス」を大切にしたいと感じた1日でした。
長久手市へ、劇を観に出かけました。
演技者一人一人の台詞の間や掛け合いのタイミング、演技者の動きに合わせて舞台上でつくる効果音、簡易な道具を工夫して効果的にストーリーを分かりやすく演出する方法について学ぶことができました。
学芸会で活用できそうなアイディアが、たくさん盛り込まれた劇でした。
演技する一人一人が、お互いに心を開き、信頼し、相手のことを思い、身体全身を集中させて、何を表現しようとしているのかをつかんで自分が演じることが、大切だと感じました。
今日は、観客として、劇の楽しさにふれることができました。子どもたちに、伝えていきたいと思います。
お世話になったり、ご無沙汰をしたりしている方に、近況報告を兼ねて、手紙を書きました。その方のお顔や、お人柄に接した出来事を思い浮かべ、思いをはせるひとときを大切にしたいと思います。
子どもたちも暑さに負けず、残り少なくなった夏休みを有意義に過ごしてくれていることを願っています。
3年前から、毎年夏季休業中に検査を受けるようにしています。検査に関わってくださる方々は、とても親切なのですが、やはり緊張します。そのせいか、検査室を移動するたびに、不安になります。全ての検査結果が今日すぐに分かるわけではありませんが、医師の面接もしていただきました。
それにしても、検査方法がもっともっと簡単に、速く、そして安価にできたらいいなと思います。
まるで、予防接種を受ける子どもの気分になった1日でした。不安にならないように、自分の健康管理をこれからもしっかりしなくてはと強く思いました。
今日も校内では、部活動を頑張る子どもたちの声が、たくさんきこえます。そして、職員室では、夏季休業中に学んだ研修について話したり、2学期行事の打ち合わせ等が進んだりして、元気で活気のある職員の声がしています。
子どもたちが元気でいることは、何よりうれしいことですが、それを支える職員が健康で元気であることもうれしいものです。
私も自分の健康管理をするために、明日人間ドックを受けます。食べ過ぎ、運動不足を指摘されることは自覚しています。
苗代小の子どもたちが、元気で、毎日を大切に過ごしてくれていることを願います。
私は、料理づくりの大好きだった母のおかげで、おいしいものを食べるのは大好きです。でも、自分で料理することは大の苦手です。しかし、夏季休業中は、食事を自宅で食べる機会が多くあります。そこで、苦手なことを少しでも楽しめるようにしたいと考え、短時間で調理するための工夫をしています。「苦手なことだから、短時間で手早くつくる方法を工夫する」ということです。
失敗はつきものですが、工夫することは楽しいものです。私の料理を食べてもらう家族には、まだまだ申し訳ないと感じるメニューや味しか出せませんが、「愛はいっぱい入ってるよ」と心の中でさけんでいます。
苗代小の子どもたちが、孤食でなく、「おいしいよ」と言える家族との食事ができているといいなと思っています。
午後、9月に開催される私的な会の講師との打合わせをしました。出席者は約300名の予定で、昨年度の10月ごろから準備は進められています。毎年、どんな講師の方をお招きをするとよいのかを考えることが、主催者にとっては大変な仕事のひとつです。
今年は、「日本の伝統文化にふれ、親しむ」をキーワードに、花舞伎(舞を舞いながら花をいける。歌舞伎ではありません。)をしていただく方に講師を依頼できました。
時期的に、9月9日の「重陽の節句」が近いことから、菊づくしでという内容も打ち合わせました。この講師の先生との出会いで、私は、日本の四季を感じ、いとおしむ心を大切にして生まれてきたいろいろな伝統や行事について、振り返るよい機会となっています。
子どもたちにも、日ごろ身近なものをよくみて、季節を感じようと話しています。
そういえば、先日、学校にくる途中で、とんぼをみかけました。毎日残暑は厳しいけれど、季節は、刻々と移り変わっています。
| 8月16日(金) 自分らしく充電できたことに感謝 と 守山警察署からのお知らせ |
残暑、お見舞い申しあげます。
皆様、暑さに負けず、お元気でお過ごしのことと存じます。
8月1日(木)〜8月15日(木)までは、ホームページ「愛のあふれる学校づくり」コーナーをお休みを頂きました。お陰様で、自分らしく充電することができました。
研修の実施された日程の早い順に、ご報告します。
< 管理監督者のためのメンタルヘルス研修 >
管理監督者に求められるメンタルヘルス対応で特に心に残ったことは、「折れない心」をつくるためには心の不安は自然の反応であり、悩みを強みにする考え方が必要であるということです。
これからも、「いつもと違う」を大切にして、子どもたちや職員を見つめます。
< 発達障碍児の視覚認知特性についての研修 >
まず、発達障害ではなく発達障碍であることを学びました。そして、環境整備をすることの重要性を学ぶとともに、個別に配慮する上で、支援の具体的な方法やポイントを学ぶことができました。
「何がみえているのか」ということを確認することの大切さに気付くことができました。
< 発声法の実技研修 >
音域を拡げるために、おもての声(地声)に裏の声(ファルセット)を混ぜていく方法で講師の歌い方をまねしながら声を出しました。継続して声を出すことは重要です。講師の先生が、「きこえる声は、マナーです」とおっしゃった言葉が、強く心に残りました。
学芸会の指導や練習に取り組む先生や子どもたちに伝えたいと思います。
< 教育展望セミナー 全体会 >
大会主題 学校をどう変えるべきか
「いま、学校に求められる変革」というテーマで、パネルディスカッションも行われました。私は、「自分大好き 友達大好き 学校大好き」について、子どもたちや職員、保護者や学区の方々に、どんなふうに進めているのかをより具体的に分かりやすく、情報発信し続けることが大切であるかということについて、改めて考える機会となりました。
この大会で学んだことを苗代小学校の学校評価に生かしていきたいです。
< 学校問題解決支援チーム講演会 >
警察署と弁護士という立場の方々からの講演を聴きました。学校は、関係機関と連携をしながら、子どもたちの健全育成や問題解決するとどんなよさがあるかについて、具体的に学ぶことができました。学校の果たす役割について、考え直す機会ともなりました。
< 研修会 「 朗読と音楽でたどる南吉の青春 」 >
今年は、新美南吉 生誕百年の年です。彼が好んでよく聴いていたクラシックの曲を生演奏で聴いたり、アナウンサーによる朗読を聴いたりしました。生徒に慕われていた南吉氏のエピソードや、心あたたまる作品に触れ、子どもたちに作品を読んであげたくなりました。
< 音楽科の学習会 >
音楽科の授業づくりについて、約30名の先生方と学び合いました。私は、「よい授業を目指して」では、なぜ教材研究をすることが大切なのかということを苗代の職員にも伝えたいと思いました。また、1時間の授業でどんな力をどこまで育てるのか、何をどのように工夫させるのか等を明確にする、音楽を聴いてどう感じたのか、どうしてそう思ったのかという理由や根拠を明確にする等についても同様に思いました。
研究授業や学芸会の取り組みの中で、苗代の職員に話す機会をつくりたいと思っています。
守山警察署生活安全課からのお知らせ
最近、自転車の窃盗事件が多発しています。短時間でも鍵をかける、二重のロックをする等に心がけましょう。
交通ルールを守って、交通安全に心がけましょう。
8月1日(木)〜8月15日(木)までは、ホームページ「愛のあふれる学校づくり」コーナーをお休みします。
今日午後からの研修に始まり、いろいろな研修や出張に出かけ、力量向上に努めます。また、私の苦手な料理や家事を頑張り、家族に少しでも喜んでもらおうと思っています。
8月16日(金)には、ご報告をします。
苗代小学校の子どもたち、そして、保護者や学区の方々、くれぐれも、お身体をご自愛ください。
少し間が開いてしまいましたが、区PTAバレーボール大会について、ご報告します。
7月27日(土) 於 守山スポーツセンター 守山区PTAバレーボール大会が開催されました。私は、9時に開会式と聞いていたのですが、私が観客席に着くと、残念ながら、開会式は終わったところでした。苗代小学校PTAの代表が、選手宣誓をされる場面を応援できなくて、本当に申し訳なく思いました。
苗代小PTAの試合は、11時開始。それまで、座席から他の試合を見せていただきました。どのチームも、ラリーは長く続きますし、サーブやレシーブのミスは、ほとんどありません。さすがに、守山区は、平成24年度名古屋市PTAバレーボール大会優勝校のいる区です。レベルの高さを感じました。
いよいよ苗代小PTAの試合になりました。対戦相手は、瀬古小PTA。とても緊迫した試合で、大接戦でした。選手の方々は、本当に悔しかったことと思います。惜敗でした。
それにしても、応援するPTAの方が数名でとても少ないという感想をもちました。何か理由があるのかもしれません。でも、この行事は、あくまでも守山区PTA行事です。苗代小PTAバレーボール部員やOBの方々だけでなく、苗代小PTAとして応援すべきだと思います。(もちろん、PTA会長はみえていました。)
本当に良い試合でした。部員の皆さんの頑張りを大勢の方々に、観ていただきたかったです。
大変勝手な思いを書かせていただきました。ご無礼な点はお許しください。
今日の学年水泳は、天気が悪く、中止となりました。
いつもより気温が低いせいか、朝から昼頃になってもずっと、せみが鳴いていました。その鳴き声を聞きながら、書類を見ていると、「ああ、夏季休業だな。」となんだかゆったりした気分になりました。今日も、30名以上が出勤しています。
今日も、5・6年の子どもたちは元気に学年水泳に参加してくれました。月曜日が学年水泳最終日です。
今日までの学年水泳参加者の人数をお知らせします。
・ 7月22日(月) 1年 と ひまわり組 91名 ( 在籍 115名 )
2年 と ひまわり組 113名 ( 在籍 145名 )
・ 7月23日(火) 1年 と ひまわり組 88名
2年 と ひまわり組 109名
・ 7月25日(木) 3年 と ひまわり組 110名 ( 在籍 162名 )
4年 91名 ( 在籍 133名 )
・ 7月26日(金) 5年 と ひまわり組 94名 ( 在籍 135名 )
6年 と ひまわり組 104名 ( 在籍 153名 )
リコーダー部や水泳部の子どもたちが、下校途中のころに、強い雨が降り大きな雷が鳴りました。保護者の方々が、かさを届けてくださったり、心配して学校に来てくださったりしました。ありがとうございました。でも、子どもたちと入れ違いになってしまった方々もみえました。大変申し訳ありませんでした。
| 7月25日(木) 3・4年 学年水泳 と 業務士(用務・給食)さんの仕事 |
4・3年の学年水泳が、無事に終わりました。
苗代小ホームページや天気予報を早めに確認していただいたり、学年水泳の有無を電話で確認してくださったりする方もみえました。
子どもたちは、元気で夏休みを楽しんでいるようです。安心しました。
また、トワイライトの方々が、学年水泳に来る子どもたちに、とても配慮してくださっていますので、安心です。ありがとうございます。
2名の業務士(用務)の方々には、安全点検で補修すべき箇所として出てきた、教室の子どもたちのロッカーや床の補修等を、そして、1学期の汚れを取り除いていただくために、全教室のカーテンの洗濯をしていただいています。
暑い中での作業なので大変ですが、子どもたちのために頑張ってくださっています。そして、業務士(調理)の皆さんは、安全衛生等の研修をはじめとする出張がある中で、調理所の環境整備を頑張ってくださっています。
子どもたちにとって、業務士さんの仕事は、あまり見えてこないことが多いようです。でも、子どもたちには、業務士さんが、「縁の下の力持ち」のような、なくてはならない大切な存在であることを知っていてほしいと思っています。
| 7月24日(水) 3・4年 学年水泳 中止 と 学芸会に向けて |
朝から土砂降りで、本日の3・4年 学年水泳は中止になりました。子どもたちに会えなかったのは残念でしたが、明日の天気予報は、晴れとのこと。明日が楽しみです。
実は、今週の職員室では、2学期に実施される学芸会の話題で連日盛り上がっています。いろいろな台本を読んで学年で相談したり、各学年の情報を交換したりしています。また、家庭科室には、学校にある大道具が所狭しと並べられ、今回の学芸会で活用できるものがあるかどうかを品定めもしています。
夏季休業中しか、学年でじっくりと話し合う時間も余裕もないというのが、現状です。
それにしても、先生方の計画的な取り組みや意欲的な姿勢に感心する今日このごろです。
今日で、1・2年の学年水泳は終了しました。
2年生の大勢の子どもたちが、小林先生の話を真剣に聴いた後、自由時間を楽しむ姿を見ることができました。にこにこの笑顔が一杯で、観ている私まで楽しくなりました。 明日からは、3・4年生の学年水泳が始まります。
学年水泳には、最適の暑さと天気でした。
私の予想以上に、子どもたちは大勢参加しており、うれしく思いました。
交通指導員さんから、次のようなお話をうかがいましたので、お知らせします。
近所の子どもたちや、兄弟姉妹と一緒に登校して来る子どもが多く、とてもほめていただきました。しかし、時間的に余裕があるにもかかわらず、慌てて走って来る子どもが多くて、「危ない!心配!」ということもお聞きしました。
慌てず「右左右」を良く見て、横断歩道や歩道橋を歩いて、安全に登下校しましょう。
学年水泳に欠席されるのは、全く構いません。また、欠席が事前に分かっている場合は、既にご連絡をいただいております。しかし、事前にご連絡がなく、参加の有無が分からず、本日、担任が保護者に連絡をとるケースがありました。お子様が、登校の途中で何かあっては大変です。担任が不安にならないように、お電話等で欠席連絡をいただけると大変助かります。
欠席連絡を入れていただいた保護者の皆様、ありがとうございました。
在籍843名のうち、今日の欠席は、16名でした。
体育館での終業式は、1年ぶりだと聞いていますが、1学期に大切にしてきたことを今日の終業式の中で確認しました。
自分から進んで行う礼(おじぎ)、大きな声でのあいさつ、話し手の方をじっと見て話を聴く態度が、とても立派にできました。
1点目、「命を大切にしよう」では、「いじめをしない・させない・許さない」の中で、特に夏休みは、子どもたちに「許さない」を特にがんばってほしいと伝えました。
2点目、「交通安全」では、1学期に話してきた、「ハンドアップ・右左右・ヘルメット」について、子どもたちに質問をし答えてもらいながら確認をしました。質問をすると、すぐに大きな声で答えを言うことのできる子どもが大勢いました。心強いです。
3点目は、今日は、通知表を持って帰るが、結果を見て喜んだりがっかりしたりするだけでなく、何が良くて何を変えていくことが大切かをしっかり振り返り、今日からどうしていくのかを大切にしようと伝えました。
私も、みんなのおかげで、1学期のホームページを継続することができました。なぜなら、子どもたちが素敵な姿をたくさん見せてくれたからです。そして、苗代小学校の教職員が子どもたちのためにがんばってくれたからです。
みんなに、心をこめて、「ありがとう。」と伝えました。
保護者の皆様、学区の皆様、ありがとうございました。そして、夏季休業中・2学期もどうぞよろしくお願いします。
子どもたちが下校する時間に、正門で見守りをしました。校舎西横断歩道付近では、スクールガードリーダーさんが、歩道橋の手前では、川崎先生が見守りをしてくださいました。
ほとんどの子どもたちは、たくさんの荷物を持っていました。既に、昨日の下校時に、道具箱を持ち帰った子どももいるようです。計画的に、荷物をもち帰ることのできている姿を見て、感心しました。
長いようでもあり、短かったようでもある1学期だと、私は感じています。
今週に入り、保護者と面談する機会や、個別に子どもたちと話す機会が、たくさんありました。それらの機会から1学期を振り返り、2学期に向けての方向性が見えてくることもありました。有意義な時間でした。これからも、遠慮無く話をさせていただけたらと思っています。
いよいよ、明日は、1学期終業式です。
テレビ放送で、はじめに、自分の命も人の命も、かけがえのない大切なものである。だから、「命を大切にしよう。」と話しました。
次に、命を大切にするためには、自分や人が、「いじめ」だと思うことは、やめましょう。また、「これは、いじめだ。」と感じたことは、とめたり、周りの人に伝えましょう。と話しました。傍観者は、いけません。命を大切にするために、いじめは、してはいけないことであると何度も話しました。
最後に、困ったことがあったら、周りの友達や大人の人に必ず相談をしようと話しました。
そして、これからも、自分の命も人の命も大切にし、「自分大好き、友達大好き、学校大好き」でいましょう。と伝えました。
担任の先生からも、話を聞き、生活・学習アンケートをしました。
| 7月16日(火) 緊急アピール「児童生徒の皆さんへ」 |
7月10日、名古屋市南区の中学生が、尊い命を失うという大変痛ましいことがありました。そのことを受け、今日、臨時校長会が行われました。
教育長、指導室長、名古屋市校長会長の話を聴きました。
今回のことは、二度と再発をさせてはいけないことです。本校でも、明日、全校児童に向けて、緊急アピール「児童生徒の皆さん」を配付するとともに、話をします。
1 命は、何にもまして大切なものである。
2 いじめは、「しない・させない・許さない」。
3 自分も人も大切な存在である。困ったことは相談しよう。
一度失った命は、決して戻ってきません。先祖から引き継いだ命は、親から子へとつないでいくものです。だから、自分の命は、自分だけのものではないと思います。
みんなが、これからも一つ一つの命を大切にしてくれることを信じています。
これまでに朝会や学年、各担任から、根気強く指導を続け、ご家庭でもご協力をいただいてきました。そのおかげで、子どもたちが大きな事故に合わずに過ごせております。ただ、夏季休業中を控えて、1学期の生徒指導で特に指導してきていることについて、ご協力のお願いをいたします。
夏季休業中、下記のような子どもを見かけましたら、やさしく諭したり、命にかかわる可能性のある場合は、厳しく声を掛けてとめたりしていただき、子どもたちの健全育成にご協力をいただきたいと思います。もちろん、苗代小学校の子どもだけでなく他の学区の子どもが遊びに来る機会もあると思いますが、私は、苗代小学校の子どもと同様に大切に考えるべきだと思います。
どうぞよろしくお願い申しあげます。
1 安全に、仲良く、コミュニケーションを大切にする
マンションの共有部分・エレベーター・屋上・駐車場などの場所で遊んだり、大きな声を出しながら通行したりする。近道だからと他人の土地を通行する。学区の方から注意されると逃げるということがありました。また、手紙などの方法で、人の悪口や汚い言葉を書いたり言ったりする。相手に自分の話したいことを分かりやすく説明できなかったり、じっくり話し合わなかったりしてトラブルになったり、怪我につながったりすることがありました。
学校の指導では、「いじめ・暴力・体罰は、決して許さない、見過ごさない」をベースにし、話をじっくり聴く。相手に伝え続けることをあきらめない。ということを大切にして指導してきています。また、人の迷惑にならない時間や場所、安全な遊びを安全な場所で、人の心や体を傷付けることは許さず勇気を出して止めたり大人の人に知らせたりしようということも大切に指導してきています。
2 田を大切にしよう
それぞれの田へ水を供給するために使用している板をはずしたり、持っていってしまったりすることがありました。また、おたまじゃくしをつかまえる、水の流れに興味があって田へ入る、石を投げ入れるという子どももいました。
学校の指導では、 「他人の土地に入ることはいけない」ということはもちろんですが、稲の生育に大きく影響する、お米の収穫量が減ってしまうということをしっかり伝えることを大切に指導しています。
3 みんなの公園を大切にする
みんなが座って休憩したり、おしゃべりを楽しむベンチに靴で上ったり、○○禁止と表示してあっても守らなかったり、公園の入り口付近に自転車を乱雑に置いて、通ろうとしても狭くて通れなかったりすることがありました。
学校の指導では、「公園はみんなのもの。早く来たからといって独占しないで 譲り合って仲良く。自分より小さい子どもやお年寄りを大切にする。ルールやマナーを守ろう。」ということを大切に指導しています。
夏季休業中は、子どもたちが家庭や地域に居る時間が増えます。今後も学校は指導を継続します。しかし、学校が、家庭・学区・地域と連携し、情報を共有することが、子どもたちの健全育成には大変有効です。今後とも、どうぞよろしくお願いします。
2限、体育館で、5名の守山土木事務所の方々をお招きして、お話をうかがいました。 この講演で、子どもたちは、守山土木事務所の方々が、私たち守山区民のために、どんな仕事をしてくださっているのかということを学びました。
お帰りになる時、今日見せていただいたプレゼンの内容のデータを学校にくださいました。子どもたちが、今日学んだことをまとめたり、もっと調べようと思ったりした時の参考にできるからです。
ありがとうございました。
1・2限、たてわりの班で活動するチャレンジ集会を行いました。
ボーリング・まと当て・10秒止め・ペットボトルラクロス・バランスタワー・あいうえおファクトリー・風船キャッチ・フリースローの8種類のゲームの中から、班でやってみたいゲームを選んで、なかよく楽しくゲームをするという集会です。
職員室では、迷子や忘れ物対応が大変でした。
子どもたちの様子を見たくて、私も集会に参加しました。8種類のゲームの中から4種類もやることができました。
お店屋さん役の子どもたちは、呼び込みをしていました。1年生の子どもが、6年生と一緒に画用紙を持って、「○○にきてください!」と、大きな声を出していました。成長を感じました。また、ゲーム会場では、黒板に第1〜3位迄の成績が書かれていたり、各々の子どもたちが担当の場所をきちんと片付けたりしていました。ゲームのやり方を親切に説明してくれる子どももたくさんいました。楽しそうに活動していました。
私も一緒にゲームをやらせてもらいました。
ペットボトルラクロスでは、うまく飛ばせない私の球を高学年の子どもが一生懸命受けてくれました。
バランスタワーでは、12個も空き缶を高く積んで見せてくれる子どももいました。
私は、「苗代っ子 夏祭り」という言葉が頭に浮かんできました。子どもたちのよさをたくさん発見し、ふれあいを深めることができて、とても楽しかったです。
子どもたちも、たくさんの楽しさを味わっていてくれていれば、うれしいと思いました。
今日までの、企画・準備・当日の運営、お疲れ様でした。
6年生と一緒に、午後から名古屋能楽堂へ出かけました。
苗代小学校の他にも、大和小学校、葵小学校、楠小学校、松原小学校、祖母懐小学校の子どもたちが、来ていました。
会場に入ると、私は、能舞台のすばらしさとともに、能楽という日本が海外に誇る伝統芸能が醸し出す緊張感を感じました。
今日の演目は、能 「殺生石」、狂言「柿山伏」でした。
子どもたちは、コミカルで分かりやすい「柿山伏」では、声を出して笑っていました。能は、逆にシーンと静かにしていました。
どちらも著名な方々が、能と狂言の演技が終わった後、子どもたちの質問に答えてくださったり、日本の無形文化財である能や狂言(能楽)を大切にしていこうという気持ちを話してくださったりしました。
子どもたちにとって、日本の伝統芸能を鑑賞することが大切であるということを実感できた有意義な機会でした。
今日も朝からとても暑い1日です。
朝会の話は、「暑さに負けずに、学習や生活のまとめをしよう」です。
お茶の入った水筒を持っていない子どもが、極数人いました。家庭の事情かもしれませんが、少しびっくりしました。
暑さ対策として、屋外では帽子をかぶる、ハンカチで汗をふく、顔を洗ったりうがいをしたりする、お茶をこまめに飲むという話をしました。授業中にしっかり勉強するためにも落ち着いて生活するためにも暑さ対策は大切です。
今週も暑さに負けず、1学期のまとめをしっかりしてほしいと思います。
ひまわり 2組の子どもたち、長江先生、と一緒に、松下先生の英語活動に参加しました。
頭・肩・ひざ・足・手を英語で歌いながら、身振りをしました。子どもたちが、嬉々として取り組む姿から、何度も同じ言葉を繰り返して歌ううちに、自然に覚えていく様子がよく分かります。計算問題と同様、繰り返しの学習は、有効だととてもよく分かりました。
その後、おいしいお菓子のチャンピオンを決めるゲームもしました。このゲームでは,
Which do you like 〜 ? I like 〜 .
という文を使って、いろいろなお菓子の名前を覚えることができました。
子どもたちは、英語で繰り返し話すという活動で、自分一人でも話せるようになっていきました。
ゲームのやり方を工夫し、少しずつ変化させるだけで、子どもたちは意欲的に取り組むことができていました。そんな子どもたちの様子を見ながら、一緒に参加して、とても楽しい気分になりました。
追伸 6限が終わって、職員室に私を訪ねて来た子どもがいました。手には、何やら段ボールらしき物を持っていました。その子どもの話を聴くと、朝会で話した、「授業中に挙手を頑張ろう」と話したことについて、「1週間で、100回挙手をしたよ。」ということを段ボールに書いて、誇らしげに報告に来てくれました。
良く見ると、一人ではなく、友達と一緒に取り組んだようです。
めあてをもって取り組む、苗代小学校のよさを強く感じました。素敵な自分を続けられる元気をその子に伝えたくて、私は、思わず握手をしました。自分の頑張りを私に伝えに来てくれて、ありがとうございました。
5限に分団会議を行いました。
PTA校外指導部の方々は、2時間も前から生活科室に集まって、準備をしてくださいました。ありがとうございました。分団会議の中では、子どもたちの登下校の様子で、良い点はほめてくださり、さらに問題点はしっかりと話をしてくださいました。
これからも、分団会議で直接子どもたちに話していただくとともに、教頭・教務・担任、PTA校外指導部にご連絡をいただければ幸いに存じます。
「危険なこと、やってはいけないこと」についての指導は、速く対応することと、繰り返し指導することが大切です。また、学校としてすぐに対応すべきこと、保護者や関係諸機関と連携をとって指導すべきこと、保護者を支えて指導すべきことがあると考えます。 そして、子どもたちが成長した点についてもご連絡をいただければ、子どもたちのやる気もアップします。合わせて、どうぞよろしくお願い申しあげます。
天候が悪く、「苗代学区犯罪なしの日パトロール」が、中止になりました。学区の方々とふれあう機会が減ったことは、とても残念です。
今日も清掃中、生活科室を片付けました。昨日に引き続きの作業ということで、手際よく、さっと棚から用具を出して整理したり、昨日の続きの作業をもくもくとやったりしてくれました。おかげで、何とか、戸棚への収納を完了しました。
後は、戸棚の中に何が入っているかを表示するだけです。
昼放課になって、6年生が生活科室をのぞいてくれました。以前の学芸会で使った小道具を見付け、懐かしがっていました。6年生とおしゃべりできて、楽しかったです。
清掃中、5年生の子どもたちと一緒に、生活科室の片付けをしました。
けん玉、こま、しょうや、だるま落とし、カップ等が、みるみるうちに各引き出しに整とんされ、とてもきれいになりました。生活科室担当の5年生の子どもたちが、頑張ってくれたおかげです。とてもうれしく思いました。
来週になると下校時間が変更になり、トワイライトの子どもたちも生活科室を利用するかも知れません。できる限り、広いスペースを使えるように、戸棚を有効に活用したいと思っています。明日も、子どもたちと一緒に頑張ります。
| 7月 1日(月) 守山東中学校区青少年育成推進会議 |
守山東中学校会議室に於いて、10:30〜第1回全体会が開催されました。この推進会議は、守山東中学校区内の青少年の健全育成を目的として開かれています。メンバーは、茂木武彦会長(苗代学区区政協力委員長)をはじめ、総勢28名で構成されています。私も苗代小学校長として参加しました。
具体的な事業としては、平成25年度は、青少年健全育成ポスターの作品募集、キャリア教育への取り組みが計画されています。
会の中で、2小学校(小幡小学校・苗代小学校)1中学校(守山東中学校)や、守山区役所まちづくり推進室、守山警察署の方々から、守山区内の現状をお知らせいただきましたが、現在は、比較的落ち着いているとお聞きしました。
今後とも、守山東中学校区の地域・保護者・学区や関係諸機関が連携を取り合いながら守山東中学校区の青少年の健全育成を進めていくことを確認しました。
ひまわり組の子どもたちと、小幡小学校へ、「のびのび運動会」に出かけました。
この運動会は、8月8日(木)開催の「特別支援学級・特別支援学校連合運動会」(於日本ガイシホール)の練習を兼ねており、のびのびと運動を楽しんでほしいという願いも込められています。
参加校は、守山小、小幡小、白沢小、小幡北小、吉根小、苗代小、守山東中、志段味中の8校でした。保護者の方々も応援に来てくださって、子どもたちもはりきっていました。
苗代小学校が、各学年ごとに自己紹介をする場面では、スピーチもポーズもしっかり決まって、素敵でした。全員で取り組んだ「マスゲーム」や「ミッキーマウスマーチ」は、動きをしっかり覚えていましたね。
「みんなでリレー」は、緑のテープで囲まれた四角のトラックを一生懸命走っていました。カーブの所は、とても走りにくかったと思いますが、みんなの声援や拍手に応えて、力一杯走る姿は、とてもさわやかで、元気パワーをたくさんもらうことができました。
今日の「のびのび運動会」で、ひまわり組さんの素敵なところをたくさん見付けることができて、心があたたかくなりました。ひまわり組の皆さん、楽しい時間をありがとうございました。
6月27日(木)〜7月9日(火)まで、英語活動アシスタントの松下由香先生が、第3・4学年の子どもたちに、英語活動をしてくださいます。もちろん、担任の先生も一緒に英語活動に取り組みます。
5限、4年2組が英語活動をしている場面を少し見せていただくと、自己紹介の活動をしていました。
smile ( 笑顔 )
eye contact ( 話す相手の目をしっかり見て )
clear voice ( はっきりした声 )
この3点をポイントにしていました。
子どもたちは、 My name is ○○ .
と、すらすらと英語で話し、自己紹介をした人どうしで握手をしていました。照れくさそうに会話する場面もありましたが、笑顔は教室にたくさんあふれていました。
貴重な4時間の活動です。ぜひ、進んで活動に取り組み、楽しんでほしいと思います。
地域ふれあい実践講座(第2回)が、開催されました。今回も講師には、教育セラピストの桑原規歌先生をお招きしました。「子どものやる気と意欲を高めよう〜脳科学を子育てに生かす〜」という演題でした。今回も、ご講演やワークショップをする中で、私の感じたり、心に残ったりしたことをご紹介します。
・ 根気強く、言葉を理解しよう
脳は、自分が言葉で伝えたことは、相手にも伝わったと思いがちである。でも、話し手の体験と聞き手の体験は違うので、自分が使う言葉の意味は、必ずしも聞き手の解釈と同じとは限らない。お互いが、言葉の意味をしっかりと話し合い、確認することが大切である。 また、言葉にならなかった部分を聴くことが大切である。
・ 抽象的な言葉を具体的な言葉にしよう。次に向けて、何をするかを大切にし、一緒に考えよう。
<心がけたい質問の仕方>
「うまくいかなかったこと(うまくいったこと)から、何が分かった?」
「次は(次も)、どうやったら、うまくいくと思う?」
「まず、何から始める?」
次回の地域ふれあい実践講座(第3回)は、9月25日(水)、「子どもたちに豊かな体験活動を① 〜 身近なものでビックリ!科学実験&工作 〜」です。 楽しみです。
守山警察署の戸田様、尾崎様の2名をお招きして、防犯教室を開催しました。連れ去り防止のVTRを見た後、「つみきおに」のお話を聴きました。つみきおにとは、不審者に連れ去られないように気を付けるポイントのことです。
つ ・・・・・ (知らない人に)ついていかない
み ・・・・・ みんなと一緒に(一人で遊ばない、家の近い子と帰る)
き ・・・・・ (いつ、どこで、誰と遊ぶのかを)きちんと知らせる
お ・・・・・ (助けて、いやだ等)大きな声を出す
に ・・・・・ 逃げる
そして、代表児童が、この「つみきおに」のポイントを生かして、模擬体験をしました。
不審者役の尾崎様に、「いやだ!」とはっきり言ったり、急いで逃げたりすることができていました。
本当に不審者に出会うことがあっては、大変ですが、もしもの時のために訓練をすることは大切です。「
全員で、「助けて!」と大声で叫ぶ練習もしっかりできました。
守山警察署の方々、ご指導をありがとうございました。
| 6月24日(月) 「 今の苗代小学校の伝統を創るのは、誰ですか? 」 |
朝会の話をする中で、金曜日に発見した「 緑の町に 」の楽譜を見せました。
そして、「これまでの苗代小学校の伝統を創ってきた方々は大勢いらっしゃるけれど、今の伝統を創っているのはここにいる皆さんです。未来の苗代小学校の方々に、恥ずかしくない自分でいましょう。自分大好きでいられるように努力しましょう。」と伝えました。子どもたちは、大きな声で、「 はい! 」と返事をしてくれました。私も、みんなと一緒に、努力します。
学区の方から、1年生を上手に連れていく分団もあるけれど、「 1年生の歩く速さを考えず、後ろを振り返りもしないで、下を向いて歩いている班長が多い。1年生が、走るようにしてついて行く様子を見た。1年生が、大変そう。班長は、しっかり前を向いて、1年生と手をつなぎ、元気よく歩いてほしい。 」という内容のお電話をいただきました。
学区の方々は、皆さんの事をいつでも見てくださっています。うれしいことです。そして学区の方々は、「 苗代小学校の子どもたちならば、きっとできる。 」と思ってみえるのです。その期待を裏切らないように、どんなことにも前向きに努力したいものです。
頑張っている班長さん、これからもよろしくお願いします。
今朝は、廃品回収日でした。正門・東門・南門で、子どもたちが、「廃品回収にご協力をお願いします。」と、声を掛け、資源ゴミの整理を一生懸命していました。雨がぱらつく天気のせいか、先月よりも廃品の量は少ないように思いましたが、雨に濡れながらの作業は、大変でしたね。お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。
1時間目から、40周年の要覧に活用する資料を整理するため、応接室の戸棚を掃除しました。すると、すごいお宝を見付けました。
校歌 「 緑の町に 」の作曲者である、 「 森 一也 」様の直筆原譜が見つかりました。額に入れて、飾ろうと思います。
今朝は、南門東側で交通当番をしました。0(ゼロ)の日は、町内や、PTAの方々が大勢見守りをしてくださっています。とても有り難く、うれしいことです。
ほとんどの分団は時間を守り、低学年の歩く速度に合わせることもできていました。また、私には大勢の子どもたちが、朝のあいさつをしてくれました。でも、交通安全の見守りをしてくださる方には、あまりあいさつができていない姿がみられました。
交通当番をしてくださる方に、感謝の気持ちを込めて、元気よく朝のあいさつ、「おはようございます。」と言ったり、「ありがとうございます。」という言葉を伝えたりしてほしいと思いました。
あいさつの言葉は、気持ちを届けるには、とても有効な言葉です。
今日のなかよし会は、「あくしゅで こんにちは」ゲームをしました。
向かい合った友達に、「○年○組の○○です。」と自己紹介をして、じゃんけんをするゲームです。その中で、グループのメンバーの名前を覚えていき、これからもなかよく活動していこうとする気持ちを高めることをねらっています。
私は、ひまわり1組の教室で活動していた23と24グループの様子を見ました。恥ずかしそうにじゃんけんをする子どももいました。しかし、「じゃんけんに何回勝ちましたか?」と私が質問すると、笑顔ですぐに返事をしてくれる子どもたちばかりだったので、今日の活動は、楽しかったんだなと思いました。次の活動まで、グループのメンバーの名前をずっと忘れないということは難しいことかもしれませんが、一緒にゲームをした友達の顔は、覚えていてくれると思います。
| 6月18日(火) 航空写真撮影 と 「 お電話に感激 」 |
苗代小学校創立40周年を記念して、航空写真を撮影しました。
朝、8:40頃から、子どもたちの準備、整列が始まりました。全部で5色(緑・黄・赤・青・水)あるビニルのエプロンを一人が1枚ずつ身に付け、みんなで苗代小学校の校章をつくりました。もちろん、教職員も入りました。
「エプロンを上にあげて。」の合図で、エプロンの色を目立たせて撮影をしました。
その後、1年生から順に、各クラス一列ずつに整列しました。全員が、屋上にいるカメラマンに向かって、笑顔を見せるようにして撮影しました。
曇り空とは言え、約一時間の間、運動場で撮影するのは、大変でした。でも、みんなの思い出になればうれしいです。
この写真は、学校要覧やクリアファイルに使用する予定です。
夕方、とても感激する内容のお電話を頂戴しました。
それは、苗代小学校にお孫様がいらっしゃるというお祖父様からの電話です。
「このホームページをとても楽しみにしています。」という内容です。実は、この方からは、以前、ホームページが不具合のために更新できなかった時、ホームページ更新へのねぎらいの言葉とともに、「楽しみにしている。更新されていないがどうしたのか。」と問い合わせのお電話もいただいた方です。そして、私は、以前から、直接、御礼をお伝えしたいと思っていた方でした。今日は、出張から戻った時、タイミング良くお電話をいただいていたので、偶然、直接お話をすることができました。
私は、その方に、「いつも、ホームページをみています。楽しみにしています。」とおっしゃっていただくことが、とても励みになり、うれしいのですという気持ちをお伝えしました。
私は、遠い地に住んでいらっしゃるその方が、孫の学校である苗代小学校ホームページの「愛のあふれる学校づくり」をみてくださっていることが分かって、とても感激いたしました。これからも、苗代の素敵な皆さんのことをたくさんお知らせしたいといういうパワーがあふれてきました。ありがとうございました。
朝会で、「夏の生活」表紙絵入賞者の表彰を行いました。表彰状を受け取る子どもたちは、とても緊張した表情をしていました。
素敵な絵をかいてくれてありがとう。朝から子どもたちをほめることができて、うれしかったです。
追伸 夕方、守山東中学校の生徒(苗代小学校卒業生)が、3人やって来ました。用件は、「吹奏楽部が、7月7日(日)15:30開場、16:00開演。守山文化小劇場で、サマーコンサートを開きます。 入場無料なので、大勢の方にぜひ聴いてもらいたいです。」と、チラシをもって来てくれました。3人は、とても、礼儀正しく、さわやかでした。
素敵な苗代小学校の卒業生だなと思いました。
朝から暑い日となりました。その暑さの中、学校薬剤師 浅井 忠則様が、プールの水質検査に来てくださいました。
水質検査の結果は、異常なし。よかったです。
1・2限 1年生が、3・4限 4年生が、水泳学習をしました。
応接室でパソコンに向かっていると、子どもたちのうれしそうな歓声が、にぎやかに聴こえてくる場面と、先生の指導する声しか聴こえてこない場面があります。子どもたちが先生の指示をしっかりと聴いて、水泳学習に取り組んでいる様子が、手に取るように分かります。素敵な子どもたちです。
早速、子どもたちの姿を見に行きました。
プールには、笑顔が一杯あふれていました。
1・2限、体育館で、学校歯科医 長谷川 孝 先生をお招きし、歯みがきの指導をしていただきました。保護者の方々が、約10名も参加してくださいました。私は、歯磨き指導への保護者の方々の関心の高さをうれしく思いました。
染め出しをした後、最初に3分、次に2分、歯みがきをしました。ほとんどの子どもは、染め出しの赤い色はとれました。でも、歯と歯の境目や隙間、奥歯のくぼみの部分が、赤く残っていることに気付いた子どももいました。
今日の歯みがき指導で、大切なことは、「歯をていねいに一本一本みがき、自分の歯を大切にしよう」ということです。自分の歯並びや、自分の歯のみがき方のくせを知り、いかにみがき残しを減らすのかということです。今日をきっかけに、子どもたちが、歯みがきの大切さを理解し、毎日の歯みがきに生かしてもらいたいと思います。
いつまでも、自分の歯で、おいしいものをたくさん食べられるよう、歯を大切にしてほしいと思いました。
追伸 長谷川先生は、用具を忘れてしまった子に、とても親切に対応してくださいました。本来ならば、学校で、持ち物忘れの子どもに対応すべきところを、申し訳ありませんでした。
長谷川先生の優しいお人柄にふれ、「歯を大切にしてほしい」という熱い思いと、一人一人の子どもを大切にするという姿勢を強く感じました。子どもたちにはもちろん、私にとっても多くの学びを頂戴できた、貴重な時間となりました。
歯科医の長谷川先生、お忙しい中、苗代の子どもたちのために歯みがき指導をしていただき、本当にありがとうございました。
| 6月12日(水) 3年 水泳学習・5年 田植え・6年 能楽堂体験学習事前指導 |
今日は、朝からどんどん気温が上がり、暑い1日となりました。その暑さに負けないように、子どもたちは頑張りました。その中から、次の3点についてご報告します。
今年度初めての水泳学習を3年生が行いました。ルールを守って、安全に楽しくできました。2年生で学習した内容を中心に、復習をしました。
10時からの出張に出かける時、少ししか植わってなかった苗が、12時頃に戻ってきたら、すっかり田植えが終わっていました。苗がかたまって植わっている所も、少しありますが、農業の初心者です。5年生の子どもたちの頑張りに、私は、大きな拍手をおくります。
昨年度も来ていただいたゲストティーチャーの やがみ様 を お招きしました。能の面(おもて)や「扇子」の体験をしたり、能を見せていただいたりしました。張りのある声に、子どもたちはびっくりしていたそうです。6年生の子どもたちが、今日の体験活動で能楽堂へでかける日が、ますます楽しみになってもらえたらいいなと思いました。
今日から水泳学習がスタートしました。
今日午前8時ごろの水温は23度、気温は24度。水泳学習の可否を決めるめどを、次のようにしています。
・小学校低学年は、水温23度以上、気温25度以上。
・小学校中学年・高学年は、水温22度以上、気温24度以上。
したがって、1・2時間目の2年生の水泳学習は否。3・4時間目の6年生の水泳学習は可と判断しました。
しかし、6年生は、プールに入ろうとしたところで、雨が、ザーッと降ってきて、中止となってしまいました。せっかく準備をして、水泳学習を楽しみにしていた子どもたちには、とてもかわいそうでした。
ちなみに、水泳学習は、どの学年も9時間完了です。
何よりも安全に、子どもたちが、水に親しむ機会となるように指導します。
「一に管理、二に指導。」を大切にします。
先週から、5年生が苗代ガーデンの田の「代かき」(しろかき)をしています。
「代かき」とは、堅い土を起こす「田起こし」の作業をした後、田に水を張った後に行う作業です。なぜ、「代かき」の作業を行うかというと、田に水を入れた後、土の表面を平らにして、水の深さを揃え、田から水をもらさないようにしたり、田植えをしやすくしたりするために行う作業だそうです。ドロドロの状態にまで、土を混ぜ合わせることが大切になります。
子どもたちは、トラクターの機械ではなく、昔ながらの方法で、足を泥だらけにして、土を混ぜ合わせていました。
ドロドロの土の感触を体感し、楽しんでいる子どもが、たくさんいました。泥だらけの足をきれいに洗う経験も、貴重な体験になっている子どももたくさんいました。
社会の米づくり、「農家の人々の苦労や工夫」の学びにつながる大切な活動です。
実体験のできる苗代の子どもたちは、本当に幸せです。
| 6月7日(金) すくすく育つ苗代ガーデンの野菜、 6年 ペットボトル提灯づくり |
4月から、各学年が丹精を込めて育ててきている野菜に花が咲き、実を付け始めたものもあります。
そして、苗代ガーデンの田は、水田となっています。
毎日の水やりと草取りは、とても大変ですが、作物の成長はとても楽しみです。
6年生が、ペットボトル提灯づくりに取り組みました。
このペットボトル提灯は、年末の安全な街づくり県民運動の一環として実施される防犯パトロール(苗代学区連絡協議会主催)で使用されます。
子どもたちは、思い思いの模様をペットボトルに描きました。
年末のパトロールが、学区の方々と子どもたちがふれあう機会となり、子どもたちのつくったペットボトル提灯が、パトロールをする方々の心と心を明るくつなぐ役目を果たすことができたらうれしいなと思いました。
全部で、ペットボトル提灯は、約300個完成しました。
1・2時間目の総合的な学習の時間 ー 環境 で、「矢田川のゴミを0にしましょう」というめあてで、クリーン大作戦にでかけました。子どもたちは、一生懸命にごみをとり、次のような感想を書いてくれました。(順不同)
・いろいろなゴミがあった。タバコのポイ捨てがとても多かった
・隅々まで探すとゴミが一杯あった。こんなにゴミがあるとは思わなかった。
・川になぜゴミがあるのかな?矢田川が、こんなにゴミで汚いとは思わなかった。
・みんなが、気持ちよく遊べるように、これからもきれいにしたい。
・ゴミを捨てないように、ゴミを持ち帰る。
・ゴミを捨てるのは簡単。拾うのはとても大変。
・ゴミの分別が難しかった。でもできるようになってよかった。
・もっと、ゴミ拾いを一杯やりたい。これからもゴミ拾いをやりたい。
毎年秋には、学区の方々と一緒にクリーン大作戦をしています。今年も実施する予定です。
夕べ、学校を出ると、「かえるの合唱」が聞こえてきました。そうです、田にたくさんいる「かえる」が鳴いているのです。それも、1種類の鳴き声ではなく、3種類は聞こえてきました。疲れが吹っ飛び、ほっとした気分になりました。
私が田に近づくと、かえるは鳴くのをやめ、離れるとまた鳴き始めました。田に水が入り、かえるが大喜びしているようです。でも、苗の生育には、かえるがいても大丈夫なのでしょうか。
そんなことを考えながら、小幡駅まで歩いていきました。苗代学区は、素敵です。
さて、運動会が終わって、子どもたちも先生たちも勉強モードにチェンジしています。 来週からは、家庭訪問も始まります。短時間ではありますが、保護者の方とコミュニケーションをとる貴重な機会です。どうぞよろしくお願いします。
家庭訪問のため、下校は13:20ごろです。下校後の遊びについては、日ごろから指導をしているところですが、安全に、仲良く、お家の方の迷惑とならないように、過ごしてほしいと思います。特に問題は起きないとは思いますが、危険な遊び、お小遣いの使い方等について、何か問題がおきましたら、まずはご家庭でご指導いただくことが大切ですが、担任を通じて学校にもご連絡いただければ幸いです。
今朝、学校へ行くと、学校付近の田植えが、終わっていました。苗が、きちんと植えられています。とてもきれいで、なんだか落ち着きます。これからは、毎日、苗が育っていくのを見ることができるので楽しみです。
実は、私が小学生のころ、自宅の近所には田や畑がたくさんありました。毎日学校へ通う間に、いくつもの田や畑を見て登校をしていたので、とても懐かしく思えるのです。
今日の午前中、校長会の出張があったので、守山区役所から学校に向かって歩いていました。ちょうど、そのとき、田の作業をしていらっしゃる方と出会うことができました。突然ではありましたが、自己紹介をして、「田の盛り土の件では、ご迷惑をおかけしました。」とお声を掛けさせていただきました。
「教頭先生に話したよ。」と答えていただき、少しほっとしました。
また、お話できたら、うれしいと思いました。
創立40周年の運動会。私にとっては、苗代小学校での初めての運動会。とてもすばらしい1日となりました。素敵な子どもたち、保護者・学区の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
毎日インターネットで天気予報を見ながら一喜一憂をしました。結果的には、やさしい日差しの中、風も適度に吹き、運動会には最適の日となりました。
閉会式で、各学年の表現については、お話しをしましたが、それに加えて、どの演技も、子どもたちの笑顔がたくさんあふれ、「ベストを尽くした」という達成感・満足感を味わうことができたんだと感じられる表情が、いっぱいでした。私は、ハッピーな気分になりました。とてもうれしいことです。苗代の子どもたちが、ますます大好きになりました。
今後とも、子どもたちを支えていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
全学年ではありませんが、運動会前日の練習を観ることができました。
本番さながら、真剣に、楽しく、自信をもって演技をしていました。
今日までの練習を振り返り、ぜひ、明日は、ベストコンディションで、落ち着いて演技を楽しんでほしいと思います。
午後、6年生は、「学校大好き」の気持ちを一杯に表して、運動会の準備に取り組んでいました。とてもたくましく、うれしく感じました。お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。
今日は、連絡がたくさんあって申し訳ありません。
連絡1 運動会に万国旗を飾るのをやめます。もうすでに存在しない国の旗がたくさんあること、逆に新しく誕生した国がたくさんあるのにそれらの国の旗がないこと、そして、何より、高い場所に登らなければ旗をつないでいるひもが垂れ下がり、子どもたちの演技に支障がでるかもしれないと考えたからです。
運動会には、万国旗が必要とお考えの方もいらっしゃると思いますが、ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
連絡2 明日も、水分補給が、しっかりできるように、お茶をたくさん持たせてください。もちろん、保護者の方々も、暑さ対策と水分補給にご配慮ください。
連絡3 これまでに、運動会当日は、荷物を一つにまとめて登校しましょうと子どもたちに伝えてあります。座席に教室の椅子を自分で運びます。リュックサック等の肩にせおえるものであれば、両手があき、安全に椅子を運べます。また、衛生面が気になるお子様も、座席の下に(地面に)、遠足の時のようにリュックサック等を置いておくこともできます。
お子様が、自分で考える機会としてあげてください。そして、お子様から相談があれば、アドバイスをお願いします。
連絡4 北に向かって下校する子どもたちに、正門前の横断歩道を渡って、そのまままっすぐに歩道橋に行くよう、担任を通じて指導しました。左側通行になりますが、学校の北西の角を東から西へ通行する車には、少し子どもが見やすくなると思いました。
もちろん、今日も、先生方が、交通指導をしてくださいました。
学校付近の田に、水が入りました。
おいしいお米ができるように、田を耕し、水を引き、道路とあぜ道の境には盛り土がしてあります。そして、除草剤が、まいてある田もあるそうです。
米作りの過程を間近に見ることができるのは、大変幸せなことです。そして、子どもたちにとって、どろんこは、とても魅力的ではありますが、作物の成長をじゃますることを、やってはいけません。
おいしいお米をつくるために、努力や工夫をしていらっしゃる方々が、苗代の学区には大勢いらっしゃいます。学区の特色を大切にできる子どもでいてほしいと思っています。
追伸 安全を第一に。田や畑の作物の成長のじゃまにならないように、登下校、 下校後の外での遊び方等について、盛り土のない道側を歩くことを含めて、 学校で指導します。ご家庭でもご協力をよろしくお願いします。
それから、苗代の子どもたちには、苗代学区の米作りについて、お話を 聞かせていただく機会をつくることが、とても大切だと感じています。
名古屋も昨日、例年に比べ11日も早く、梅雨入りしました。今朝も雨がたくさん降っていました。
歩道橋を渡る子どもたちは、いつも通り整然と順番を待ち、一列で歩いていました。
安全に気を付け、落ち着いて歩いていました。私は、「歩道橋を歩くときは、早歩きにしましょう」と何度も声を掛けながら、歩く様子を見ていました。
1年生の子どもも、さっさと歩いていました。とても、成長を感じました。
慌てて歩道橋を歩く必要はありません。でも、じっと歩道橋の下で順番を待っている苗代小学校の友達のことを考えることのできる子どもでいてほしいと思っています。
昨日の練習に比べ、全員の気持ちが揃っていて、声がよく出ていたそうです。(私は残念ながら出張に出ていて、見ることができませんでした。)
学校に戻り、練習の様子をいろいろな先生から聞き取りしました。よかったです。
| 5月27日(月) 運動会全体練習 ー 開会式・閉会式・応援 |
いよいよ、運動会まで約1週間となりました。曇り空に、適度な風が吹き、「運動会当日もこのくらいの暑さだったらうれしい。」という声が聞こえてきそうでした。
開会式・閉会式では、けじめのある態度で臨んでいました。応援の練習では、応援団長のかけ声に合わせて言うせりふは、1度で覚えることができました。ただ、最後の言葉を長く伸ばして言う子どもがいるのが気になりました。長く伸ばすと、タイミングが取りにくく、間延びした感じがします。応援は、明日も練習をします。
朝から良い天気と心地よい風が吹き、運動には最高の日になりました。
私が運動場に着くと、子どもたちが真剣な表情で試合に臨んでいました。来賓テントの私に気付くと、声を掛けたり、手を振ったりしてくれる子どもたちがたくさんいて、とてもうれしくなりました。
日差しが強く、暑い中での試合でしたが、フェアープレーで、メリハリのある態度の子どもたちなのが、とても素敵だなと感じました。
表彰式の運営も、もちろん子どもたちがやっていました。急きょ、私が挨拶をさせていただく機会を得ました。子どもたちが、今日の大会でも、「自分大好き、友達大好き、子供会大好き」になれたことが、とてもよかったと思ったことを話しました。
挨拶が終わると、子どもたちから、「歌を歌って!」と声がかかりました。
そこで、「おめでとう、おめでとう、心がひとつになりました。」と、即興で歌いました。
ASO部、子供会、学区の皆様、苗代の子どもたちのために、楽しい大会を開催し、お力添えいただき、本当にありがとうございました。
| 5月24日(金) 山本友希子先生( 第3学年3組 )の研究授業 |
3時間目に、第3学年3組で、国語の研究授業がありました。
< 単元 > 音読しよう ー 「よい聞き手になろう」
< 目標 >
・ 話の中心をはっきりさせて、話したいことが相手に伝わるような話し方でスピーチできるようにする。
・ 友達の一番話したいことを聞き取り、感想を述べたり質問をしたりできるようにする。
グループに分かれ、話し手になったり、聞き手になったりする「お話タイム」を行いました。「お話タイム」とは、グループごとに一人が話し手となり、自分の書いた作文を2回読みます。その他の子どもたちは、話し手の作文を聞いてメモを取ったり、質問や感想を書いたりしました。その後、聞き手が質問し、話し手が答え、話し手と聞き手を順に交替していくというものです。
話し手は、すらすらと作文を読んでいる子どもが、ほとんどでした。気持ちを込めて読んでいる子どももいました。グループの子どもたちが、同じ話題で作文を書いているせいか、聞き手は、質問や感想を短時間で書くことができていました。これは、自分の伝えたい内容、話し手の作文に対する質問や感想をグループ(少人数)で伝え合う授業でした。
今後も、今日の授業を生かして、自分の伝えたい内容を分かりやすく、はっきりと伝える話し方や、話し手の伝えたいことが何かをじっくりと聴き、自分の思ったことや感じたことを質問や感想として話すことができる子どもへとより成長していってほしいと思います。
今日の授業は、「自分大好き、友達大好き、学校大好き」になるために大切な力を学ぶ上で重要な授業となりました。
PTAと守山区生涯学習センターとの共催で、地域ふれあい実践講座(第1回)を行いました。講師には、教育セラピストの桑原規歌先生をお招きし、「信頼関係と絆を深める〜子育て・子ども支援のスタンス〜」という演題でした。ご講演やワークショップをする中で、私の心に強く残ったことをご紹介します。
・ 親が幸せになろう。子どもと親は、心のへその緒でつながっているー 親自身が、自分のことを好きになり、幸せになることが何より大切である。親自身の心が安定していれば、子どもに良い影響が出る。
・ 親が、子どもを「この子はこういう子」と決めつけると、本当に子どもはその通 りになる。ー脳は、イメージ通りの自分、人に扱われたようになろうとする性質がある。
・ 過去ではなく、子どもの未来に目を向けよう。ー子どもが失敗した時、責めてはいけない。「次は、どうするの?」を大切に話す。
今日のお話の内容には、自分が教師として大事にしてきたことが、たくさん盛り込まれていました。そして、それを脳科学という視点から分かりやすく説明していただいたように思いました。
次回の地域ふれあい実践講座(第2回)は、6月26日(水)、「子どものやる気と意欲を高めよう 〜 脳科学を子育てに生かす 〜」です。 楽しみです。
今日の4時間目、体育館で、浅井浩一先生をお招きして、リコーダーの講習会をしていただきまし。
いろいろな大きさのリコーダーの音色の違いを演奏を通して、聴かせていただきました。子どもたちに親しみのある、ディズニー・ドラえもん・ジブリのテーマ音楽等の曲が、次から次へととびだしてきました。子どもたちが口ずさむ場面も見られました。
旋律だけでなく、前奏や後奏も工夫されていました。また、複数のリコーダーを駆使した演奏も、披露してくださいました。
全員で演奏した曲では、素敵な音色を出すために、タンギングがとても大切だということを学びました。浅井先生の演奏を聴いていると、とても簡単にいろいろな曲が、演奏できてしまう気分になりました。
3年生の子どもたちにも、いろいろな曲にチャレンジしてほしいと思いました。
浅井先生、素敵な演奏をありがとうございました。
今日は、1年生の練習を見ました。
速度が、少し速い曲なのに、テンポにのって踊っています。ある部分だけ、かけ声を言います。その上、隊形も変化します。
大勢の中から、ご自分のお子様がどこの場所で踊っているのかを見付けるのは大変かもしれません。
1年生の算数の勉強のように、お子様に、「前から(後ろから)何番目?」と聞いてみてください。また、目印になるものや、近くにいるお友達の名前を聞いてみてください。
子どもたちは、みんな練習に一生懸命取り組んでいます。ぜひ、ご家庭でも話題にしていただけたら、うれしいです。
水分補給の為の水筒やお茶の準備、毎日着ている体操服の洗濯等、大変お世話になります。ご協力に感謝いたします。
3年生 競遊 「棒引き」 の練習を見ました。私は午前中から、応接室で書類の作成をしていたのですが、元気な子どもたちのかけ声に誘われて、運動場へ引っ張られるように演技を見たくてたまらなくなりました。
棒引きは、棒の引っ張り方を間違えると、ケガにつながることがあります。
とかく勝敗に必死になり過ぎると、危険な引っ張り方をしてしまいがちですが、3年生の子どもたちは必死な中にも冷静に演技をしていました。私は、ほっとしました。安全に気を付けて演技できる3年生の子どもたちの素晴らしさと、先生方のご指導のお陰です。
中津川での3日間、とても良い天気に恵まれ、全ての活動を滞りなく行うことができました。
まとめて言えば、「5年生最高!、苗代の教職員最高!、留守番をしてくれた皆さん最高!」という言葉で表現できます。
3校合同の入所式では、苗代小学校が3校の代表となりましたので挨拶をしました。一緒に生活した猪子石小学校・内山小学校の校歌の歌詞には、「仲良く」という言葉が入っています。そこで、みんなで入所式に歌う「よろしく中津川」の歌詞のように「仲良く」を大切にして、今以上に「自分大好き・友達大好き」になれるように努力し、楽しい時を過ごしましょうと伝えました。
3校を代表して、苗代小学校の代表児童が挨拶をしました。とてもはきはきとした声で、気持ちを込めて話してくれました。
その後、たくさんの活動がスタートしました。どの活動でも子どもたちの担当者が役割をしっかり果たし、みんなも気持ちよく盛り上げていました。かっこいい子どもたちでした。もちろん、先生方のすばらしい指導もありますが、「子どもたち一人一人が、たくさんの子どもたちの中で育っているんだ」という面を強く感じました。決して、トラブルがゼロだった訳ではありません。でも、多くの子どもたちと生活できる苗代小学校のメリットを痛感しました。
また、中津川の自然からも、たくさんのプレゼントをもらいました。青い空、木陰の涼しい風、鳥のさえずり、付知川の流れの音、木や薪のにおい、北斗七星の輝き、三日月の美しさ・・・・・・・・・。どれも素敵でした。
私は、みんなと一緒に過ごした大切な時間をとても幸せに感じました。
バスを降り、学校に向かって歩いていると、学校からぞくぞくと苗代の教職員が出迎えに来てくださる姿が、目に飛び込んできました。疲れが吹っ飛んでしまう喜びを感じました。
中津川野外学習を終えた5年生の子どもたちが、学級・学年の活動の中で、さらに、「素敵な なかま」として育っていくことをこれからも期待しています。
今後ともご協力・ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
とても良い天気に恵まれ、絶好の野外学習日和になりました。今日から2泊3日で、中津川野外学習に行ってきます。5年生の留守の間、登校・掃除等、子どもたちがいろいろな面で、5年生をサポートしてくれます。大変ですがよろしくお願いします。
5年生の活躍は、17日にご報告いたします。
あと約30分で、出発です。「いってまいります。よろしくお願いします。」
「宙の会」の方々が、2年生に読み聞かせをしてくださいました。
教室の黒板には、タイムスケジュールや机・椅子の配置について、子どもたちへの指示がかいてある学級もありました。
表情や声色を工夫したり、子どもたちに質問をしながら読み進めてくださったりしました。子どもたちは素早く質問に答え、自分の椅子から伸び上がるようにして興味深く聴いていました。そして、お礼もしっかり言えました。
子どもたちの「ありがとうございました。」の声に、「こちらこそ」とおっしゃってくださる方がみえました。
その後、家庭科室へお邪魔すると、「宙の会」の方々が打ち合わせをしてみえました。絵本を開いて、「この本、いいね。」等とおっしゃったり、今日の読み聞かせについて振り返っていらっしゃいました。
苗代小学校の子どもたちは、とても幸せだなと感じました。
本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
朝からとても暑い1日になりました。
安心メールの配信も無事に完了し、保護者の方々が続々と学校に集まってくださいました。そして、黄色いヘルメットをかぶった子どもたちが、運動場に整列し、いよいよ引き渡しの開始です。
保護者の方々は、整然と子どもたちのところへ迎えにきてくださいました。待ち時間が長く、暑かったにもかかわらずご協力をいただき本当にありがとうございました。
率先避難の大切さ、子どもたちとの避難場所の確認について、話をさせていただきました。
1時間目、6年生の外国語活動を参観しました。
Jamie先生の英語は、とてもきれいな発音です。大切なところは、何度も繰り返して話してくださったり、ゆっくり言ってくださったりするので、子どもたちも、たくさん手をあげて答えていました。それに、なにより笑顔が素敵で、子どもたちも自然に笑顔になり、楽しそうに活動していました。今日は、教頭先生も飛び入り参加をしてくださったので、とても盛り上がりのある時間となっていました。
5月8日(水)は、ひまわり組、1・5年生の子どもたちが、校医の浅川先生に内科検診をしていただきました。午後1時半から3時半まで、検診は続きました。全く休憩時間はありませんでした。
また、5月9日(木)は、2・4年生の子どもたちが、歯科医の長谷川先生と奥様に歯科検診をしていただきました。9時からスタートして、12時すぎまで検診は続きました。その間の休憩時間はわずか5分程度でした。
大切な苗代の子どもたちの検診とはいえ、校医の先生や歯科医の先生方には大変申し訳ないと思うとともに、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
ぜひ、子どもたちには、検診の結果を受け、早めに治療を受ける。今後も健康に気を付けたり、適度な運動を心掛けたりする。また、これからも歯磨きやうがいをていねいに行い、定期検診を進んで受ける。むし歯、歯肉炎、歯周病に気を付けるなど心掛けてほしいと思いました。
今後とも、ご家庭のご協力をよろしくお願いいたします。
交通指導員の佐藤様に、体育館で交通安全教室の講話をしていただきました。
交通安全に関わる「はひふへほ」のルールを学び、自転車の乗り方や点検の仕方を教えていただきました。
子どもたちは、落ち着いて真剣に聴いていました。その後、マジックも見せていただきました。
2〜4限には、4名の交通指導員様にもサポートしていただき、1・3・5年生の交通安全訓練をしました。
子どもたちが交通安全に気を付けて生活してくれることを願っています。 |
 |
追伸 昨日の放課後の遊びについて、朝の打ち合わせで、教務主任から教職 員に話をしてもらいました。担任から、子どもたちに考える機会を与え、他の人 の迷惑になっていないかどうかを振り返ったり、いつもなぜだろうと考えたりでき るようになってほしいと考えたからです。
午前中に、お客様がいらっしゃいました。
その方とお話をさせていただく中で、子どもたちが学区の自然にふれて楽しんで生活していることを知りました。でも、子どもたちが遊んでいる場所は、田や畑で水路もあり、側溝もある場所でした。
そのお客様も私も、お話をする中で、子どもたちには、身近な自然とふれあうことは、豊かな心を育てる上でとても大切なことだと考えていることが分かりました。自然を慈しみ、大切に思う気持ちが育つと考えるからです。
でも、私は、作物を育てるために耕し、種をまいたり苗を植えたり、あるいは、田に水をためているのに、その努力を踏みにじるかのように、邪魔をすることがあれば、それは子どもだからこそ、何の為にそうなっているのかを疑問に思ったり、考えたりしてほしいと思いました。
また、気付くことができないならば、考えるようにしてあげたいとも思いました。
身近な自然が減ってしまった今の子どもたちだから、「悪気はない。ちょっとしたいたずら。」と何も言わずに許しましょうという考え方もあるかもしれませんが、まだまだ身近な自然が残っている「苗代小学校の子ども」だからこそ、「何の為に、耕した跡があるのか、水がはってあるのか等に気付くことができる子どもたちでいてほしいと思います。
その場にいて、子どもに教えてあげられないならば、看板等を立てる等、子どもが気付くようにする工夫も必要だと考えます。
お客様と話をすることで、無邪気な子どもたちのことを知ることができました。
お客様に感謝いたします。
5時間目に、6年生の練習を見せてもらいました。
学級通信の中で、子どもたちの頑張りを担任から教えてもらっているからです。土台になっている子が、痛みに耐え、上に上がる子のことを思い、上になる子は怖さに耐えている姿が、とても印象に残りました。
今後の成長が楽しみです。
風が強く、少し寒い日となりましたが、昨日とはうってかわって良い天気となりました。延期せずに遠足に出掛けることができて良かったです。私も、どこかの学年と一緒に行きたかったのですが、校長会の出張と重なりました。
残念です。次年度は、重ならないように計画します。とても反省しています。
出張から学校に戻ると、あっという間に、1年生が学校に到着。
続いて、2年生、3年生というように、学年順で無事に学校へ到着。
「半袖は、寒かったよ。」
「遠かった、たくさん歩いた。」
「やっと、学校に着いた!}
と言いながら、みんな笑顔でうれしそうでした。元気に戻ってきてくれて、本当によかったです。
欠席や早退した子どももいましたが、遠足を通して、新しい学級や学年の友達、先生方と心がふれあい、仲良くなれたように感じました。
明日も、弁当持参です。ご家庭にはお手数をおかけしますが、遠足の意義は、高いと思いました。
今日は、雨の降るあいにくの天気でしたが、4年生は見学に出掛け、6年生は体験活動をしました。
4月19日(金)には、4年生の3・4組が、今日は4年生の1・2組が見学にでかけました。徒歩で見学に出掛けられるなんて、とても便利なことです。
また6年生は、先週から、火起こし体験をやっています。今日は、体育館北の所でやっていたので、すぐに焦げ臭いにおいがしてきました。でも、天気の加減もあってか、煙は出ても、火がつくまでにはなかなか至らず、大変そうでした。
日ごろ、家庭からゴミを出せば収集車が取りに来てくれたり、スイッチを入れれば、火がついたりするという便利な生活に慣れています。
今日の見学や体験は、子どもたちの学習に役立つことでしょう。
ご家庭でも、話題にしていただければ、うれしいです。
今年度初めての、授業参観が開催されました。子どもたちは、緊張をしながらも落ち着いて授業に臨んでいました。多くの保護者の方々が、来校してくださいました。学校への関心の高さに感謝を申しあげるとともに、責任の重さをあらためて感じました。ありがとうございました。
その後、体育館において、PTA総会が開催されました。
全ての議事が、審議されました。
各報告が承認され、原案通り、可決・決定されました。
平成24年度の役員の労をねぎらい、平成25年度役員を始めとする組織づくりがなされ、会を閉じました。
今後とも、PTA活動へのご協力をどうぞよろしくお願い申しあげます。
今日は、運動をするには少し汗ばむくらいの日でした。
授業後は、部活動の練習がありました。
どの部活動も、挨拶に始まって挨拶に終わるということが、とてもしっかりできています。とても素敵なことです。
部活動で、技能向上は大切なことです。でも、それ以上に、苗代小学校の部活動は、部活動を通して、人として大切なことを学んでいるということをとても感じます。子どもたちの頑張りが、爽やかです。私の心は、いつも元気をたくさんもらえます。
今朝は、強い雨が朝から降っていました。
学校の北にある歩道橋の付近では、PTA会長の杉浦様が立ってくださり、三方向からやってくる子どもたちを見守り、声を掛けてくださっていました。
子どもたちは、整然と1列を守って並び、譲り合いながら歩道橋を渡っていました。本当に素晴らしい子どもたちだと感心しました。もちろん、教員も毎日、数カ所のポイントに立っていますが、子どもたちを支えてくださっている方々に感謝の気持ちを届けたいとあらためて思いました。
日ごろから、交通安全にご協力いただいている皆様、ありがとうございます。
子どもたちが、安全に登校することが、何よりも一番大切です。
それにしても、全員が歩道橋を渡るのに、とても時間がかかりました。天気の良い日に比べ、約15分程度遅くなりました。
| 4月23日(火) 学級懇談会(1・2年、ひまわり) |
今日は、学級懇談会(1・2年、ひまわり)を実施しました。とても大勢の参加がありました。
PTA学級委員選出の会も、スムーズに終えることができました。
子どもたちを見守り、支えていただける苗代小学校の保護者の皆様に感謝申しあげます。
ところで、今日の午前中には、高学年の体力診断・運動能力調査(4〜6年)を実施しました。子どもたちは、私と目が合うとにっこりしていましたが、きっと心の中はドキドキしていたことと思います。「良い記録が出ることを願っていますね。」と声を掛けました。子どもたちは、一生懸命に取り組んでいました。
子どもたちには、事前に担任から、今回の50メートル走の記録をもとに、運動会の紅白対抗リレーの選手を決めることを伝えました。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
今日の朝会で、児童会役員・委員長・学級委員の認証式を行いました。
一人一人の子どもに、「よろしくお願いします。」と声を掛けながら、認証状を手渡していきました。認証状を受け取る子どもたちは、良い姿勢をして、真剣な表情の子どもたちばかりでした。子どもたちのやる気を感じました。
その後、全員の子どもたちに、今認証された子どもたちに、しっかりと協力をして「自分大好きになりましょう。」と伝えました。
さて、明日は「子ども読書の日」です。読書をすればするほど、いろいろな言葉を知ることができ、その言葉はどんな時につかえば良いかが分かるようになります。これからも、どんどん本を読みましょうと伝えました。
今日は、とても強い風が吹きました。朝、私の帽子は何度も風で飛んでいきそうになりました。そんな天候の中、学級懇談会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。
保護者の方々を待つために、子どもたちが、廊下で静かに勉強したり、絵をかいたりしていました。感心しました。金曜日は、3年生がトワイライトの無い日なので、残念だなと思いました。
学校の玄関付近には、「ハナミズキ」が満開です。
苗代ガーデンでは、チューリップが美しく咲いています。
私は、小幡駅から徒歩で学校に通っています。その途中で、たくさんのきれいな花を見ることができます。この時期は、いろいろな花を発見でき、とても楽しく通勤できます。子どもたちにも、花を楽しんでほしいと思う今日このごろです。
| 4月17日(水) 中津川野外学習説明会・学級懇談会(5・6年) |
今日、上記の会が開催されました。
5年生は、中津川野外学習の説明会終了後、学級懇談会、PTA学級委員選出の会も行いました。会が全て終了し、保護者の方々が担任と一緒に椅子の片付けをしてくださいました。5年生の担任が、大変感謝いたしておりました。ありがとうございました。
そして、6年生の学級懇談会の様子を見に行くことができなくて、大変申し訳ありませんでした。
PTA学級委員をお引き受けいただきました方々、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。また、PTA学級委員選出の会にむけてのご準備や当日の進行役をしてくださった方々、お疲れ様でした。
皆様、今後ともどうぞ宜しくお願い申しあげます。
2時間目に、今年度初の避難訓練をしました。入学して間がない1年生もしっかりとした態度で、避難訓練をしていました。担当の先生からは、全学年が静かに短時間で避難できたことをほめていただきました。
私は、「率先避難」の大切さ、「防災ノート」の活用等について話をしました。
今日の避難訓練は、火災を想定した訓練でした。
今後も、「おかしも」の合い言葉を守って、素早く避難できる子どもたちでいてほしいと思います。「おかしも」の合い言葉は、下記のようです。
お ・・・ おさない
か ・・・ かけない
し ・・・ しゃべらない
も ・・・ もどらない |
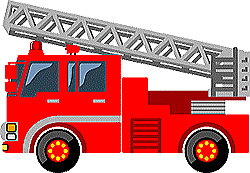 |
12日(金)区政協力委員会、15日(月)学区連絡協議会が開かれ、その会で学区の代表の皆様に、着任のご挨拶をさせていただきました。前任の野田誠司校長先生と同様、どうぞ宜しくお願い申しあげます。
15:00から、トワイライトの開校式がありました。100名の参加者がありました子どもたちは、整然と入室し、話を聞く態度もとてもよかったです。手品を見せていただいたり、ギターの伴奏に合わせて、「さくらさくら」「ふるさと」「こいのぼり」の曲を歌ったりしました。私も一緒に歌わせていただきました。
事前に、各担任のご協力をいただき、トワイライトへの12日の出席人数を把握しました。多いことは十分予想していましたが、とても大勢になりました。
子どもたちの笑顔をたくさん見ることができました。楽しい時間でした。 |
|
今日は、離任式でした。朝から、前任校の千成小学校へ出掛けました。
千成小学校では、「笑顔と未来の地域人」をキャッチコピーに学校づくりをしてきました。千成小6年の代表児童が、「これからも笑顔あふれる学校になるよう頑張ります。次の学校でも笑顔を伝えていってください。」と励ましてくれました。
苗代小学校では、、「自分大好き、友達大好き、学校大好き」をキャッチコピーに
「愛のあふれる学校づくり」を目指していきます。千成小学校の子どもたちに恥じない学校づくりを頑張ろうと、決意を新たにしました。
今日、6名の調理をしてくださる方々のお一人お一人と面談をしました。
給食の献立について、子どもの感想をどんどん聞かせて欲しいとおっしゃってみえました。
子どもたちは、いつも給食を返却する時等には、「ごちそうさまでした。おいしかったです。」と声をかけています。これからも、おいしい給食をつくってくださる調理員さんに、感謝の言葉や給食の感想を自分から進んで伝えることのできる子どもでいてほしいと思いました。
着任式で、
「 なかよくしましょう 広い心で なかよくしましょう 中島博子 」 という歌で、私は、自己紹介をしました。
子どもたちが、私の名前を覚えてくれたらうれしいです。
始業式では、私は、苗代小学校を「愛のあふれる学校にしたい」と伝えました。そのために、「自分大好き、友達大好き、学校大好き」を頑張りましょう。そして、1・2年生には、「自分大好き」を、3・4年生には、「友達大好き」を、5・6年生には、「学校大好き」を特に頑張ってほしいと伝えました。
今年度は、児童 843名、教職員 49名でスタートしました。
子どもたちの下校時に、私が西門に立っていると、「校長先生の名前の歌をもう一回歌ってください!」と子どもに言われることがあります。
私が、「なかしまひろこ」の文字を使って歌にしたものです。少し照れくさいですが、名前を覚えようと思ってくれているのかなと思うと、うれしくなります。 |
![]() |
115名の1年生が、入学しました。
落ち着いて、じっくりと話を聴いている1年生に感心しました。来賓の方々も、1年生の落ち着いた態度や、しっかりとした声で返事が出来ている姿をほめてくださいました。
私は、1年生の子どもたちに、「 自分大好きになりましょう。 」と伝えました。
入学式の式辞の中で、1年生の子どもたちに、「ご入学おめでとうございます」と言う言葉を掛けると、「ありがとうございます。」と、かわいらしい声が返ってきました。
そして、私が、保護者や学区、教職員に「皆さんは1年生の応援団ですよね!」と問い掛けると、その声に応えて、「はい。」と大きな声で返事をしてくださいました。この2つの言葉のキャッチボールが、ずっと私の耳と心に残っています。
ありがとうございました。 |
nyuugakusiki.jpg) |
午前中、6年生が入学式の準備と教室の机やいすの移動の仕事をしてくれました。6年生としての初仕事です。自分から進んで、仕事に取り組んでくれました。とても感心しました。
仕事が終わりに近付いたころ、私は、6年生の各教室をまわって、「ありがとう。お疲れ様。」と声を掛けに行きました。
その時、「私の名前は、○○○○です。」と教えてくれる子どもがいました。
礼儀正しく、そして、気軽に声を掛けてくれた6年生に、私の心は、ほんわかしました。
入学式の準備は、勿論、完璧です。
写真は、準備の終わった体育館です。
私は、教務主任の先生と入学式の流れを会場で最終確認しました。
|
 |
4月2日(火)に保健室へ初めて入りました。居心地のよい、あたたかい雰囲気のお部屋でした。その時、養護の先生から、「昨年度、正門の突起部分でつまずき、けがをした子どもがいたんです。」と教えていただきました。
そこで、業者さんに依頼し、突起部分を撤去してもらいました。
これで、けがが減ったらうれしいです。
突起部分は、とても頑丈で、金属をカットする丸い刃を3枚も使って、撤去しました。
撤去した部分の穴には、コンクリートを埋めて、平らにしてもらいました。
その後、コンクリートで埋めた部分をペンキで色付けしていただきました。
カットした突起は、今、応接室に置いてあります。
|
![]() |
今年度、5年生の中津川野外学習は、5月15日(水)〜5月17日(金)です。
ですから、5年生は新しい学級づくりの時期から、中津川野外学習の準備が始まります。
そのため、5年生の担任は、中津川野外学習の説明会に備えて下見に出掛け、準備を進めています。
昨日実施された中津川野外学習6校打ち合わせ会で、苗代小学校が、第2本館の入所式担当校に決まりました。
5年生の子どもたち、担任の先生方と一緒に、私も準備を頑張ります。
今年度の中津川野外学習は、次の6校が同日に宿泊します。
(五十音順)
・ 第1本館 大杉小学校
香流小学校
東白壁小学校
・ 第2本館 猪子石小学校
内山小学校
苗代小学校
他校の子どもや先生方とも、挨拶したり、良さを見付け合ったりできると、うれしいですね。 |
 |
学年末・学年始め休業中に、調理所に新しい食器洗浄機が入ったと教えていただいたので、初めて調理所に入りました。
調理所は、とてもきれいに片付いていました。
ピカピカの食器洗浄機も見せていただきました。今までは、とても古い機械で、作業が大変だったそうですが、これからは、手を少し伸ばして食器を送るだけで、きれいに洗浄出来るそうです。6名の調理員さんが、とても喜んでみえました。
うれいことです。
調理所の方々は、職員室ではいつも私から一番遠くの席に座ってみえます。お話できないと寂しいので、私は「時々調理所へ、お邪魔させてください。」とお願いをしました。6名の調理所の方々は、快く、「どうぞ、いらしてください。」とおっしゃってくださいました。うれしかったです。
調理所の方々ともお話しする機会を増やしたいです。 |
![]() |
今日、名古屋市教育センターの訓辞式で、苗代小学校長の重責を拝命いたしました、中島博子です。中村区 千成小学校からまいりました。どうぞよろしくお願い申しあげます。
この「愛のあふれる学校づくり」のページで、子ども、教職員をはじめPTAや学区の皆様の素晴らしさをたくさんお知らせしていきたいと思っています。 |
職員室で、教職員の皆さんにお会いし自己紹介をしました。
職員室のあたたかい雰囲気が、とても気に入りました。
一日も早く、皆さんの顔と名前を覚えたいと強く思いました。
|
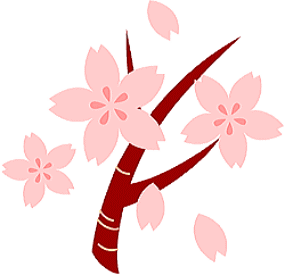 |
|
|