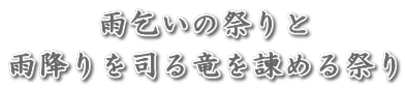
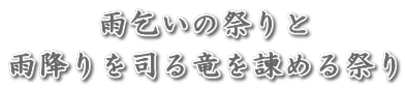
美濃路は、岐阜県垂井町追分と名古屋市熱田を結んでいました。この58kmの街道沿いには、いくつもの祭りがあります。面白いのは、その土地に住む人々の祭りへの願いが違うことです。
美濃路の宿場町の終点(起点)である垂井町は、濃尾平野の扇状地の始まりにあたる場所です。したがって、少し小高い場所にあります。川の水は、大雨でない時には伏流水として地下を流れるものも多くあります。水無川となることも多々あります。そんな垂井町での表佐太鼓祭りなどは、雨乞いの祭りです。水田に十分に水がたまらないと、豊作にならないからです。
でも、枇杷島に伝わっている梵天祭(ぼんてんさい)は、雨が降りすぎないことを願う祭りです。治水ができなかった時代は、日本では竜(=大蛇)があばれて大雨が降り、洪水になるという人々の思いがありました。梵天様であったり、弁財天であったり、土地によって竜を慰め祈ったり感謝したりする神は違うものの、神にもすがる気持ちで祈りをささげてきたことでしょう。
歴史として残っているのは、明和四年(1767)7月、庄内川氾濫し溺死者2000人という「愛知縣神社名鑑」の記述などですが、それ以前にも、太古の昔から何度も大きな水害は起きていたことでしょう。
もちろん、美濃路の墨俣宿、起宿あたりも水害が多く、雨が降り続かないようにという祈りがあったことと思います。雨ごいの祭りと雨が降るのを引き起こす竜を諫める祭り、祭りには古来からのそこに住む人々の思いが詰まっているのでしょうね。
そんなことで始まった梵天祭ですが、江戸時代中期には名古屋城下に広がり、名古屋に住む多くの人々が祭りを楽しんでいたようです。現在は、枇杷島夏祭りで、子どもたちの健康を願う稚児梵天として引き継がれています。
| |
|
| 梵天祭の行われる神明社 | 梵天・稚児行列出発地の八幡社 |
Network2010 尾張名所図会 梵天祭 http://network2010.org/article/947
名古屋神社ガイド https://jinja.nagoya/top/nisiku/biwajima-sinmei-hakusan-aidono
「災害多発地帯の『災害文化』に関する研究」1992 東北大学(研究代表者・首藤伸夫) https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-04201110/
岐阜の旅 表佐太鼓踊り https://www.kankou-gifu.jp/event/detail_5746.html